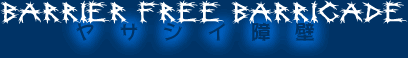
薄暗いコンピュータルームで、解析されたカードのレポートに目を通していた海馬瀬人は、瞼の裏に鈍い疲労を覚えてモニタから顔を上げた。
傍らの電子時計がとうに日を越えてしまった時刻を示している。
( ・・・もうこんな時間か )
あともう少し。
せめてレポートの最後まで目を通してから寝ようと、とうに冷めてしまったコーヒーカップに口を付けた瞬間。
ばたん、と傍若無人な音がして、廊下に面した大きめの防弾ガラス越しに、すぐ外の扉が開くのがわかった。
外界の明かりが差し込んで、照明一つない無骨な船尾の非関係者侵入禁止区域を照らし出す。
何事だといぶかる彼の目の前を、見覚えのある少女がとてとてと、遠慮もへったくれもない足取りで横切って行った。
( ・・・・・・・・・・・・・・なんだ今のは )
繰り返すが、関係者以外立入禁止である。
確かあの小娘は少し前にも迷い込んでいたのを送っていったことがあり、その時はっきりそう教えておいたはずなのだが。
いぶかしみながら、扉を開けて様子を伺えば、狭い鉄橋ひとつ隔てた向こう側にいる少女の姿が見えた。
( ・・・・・・? 何をしているのだ? )
しばらく観察するが動く様子は無い。
少女は外を見ていた。
客室側よりも大きく区切られた窓の、その窓枠に腰掛けて、二重ガラスの向こう側に視線を馳せている。
本来人が入ってくるように設計されてはいない場所だ。
照明などあるはずもないが、壁の半分以上を占領する窓から入ってくる月明かりのおかげで、その場所だけが切り取られたように青白い。
照らし出された少女の横顔は、人形のように表情が無かった。
このまま放っておいたら朝までそこに居座られそうだ。
そう思って彼は近付いた。
窓から入る光を避けるように、やや距離を置いたところで立ち止まると、少女が気付いて頭を上げる。
「・・・・・・海馬さん」
どうやら寝ぼけているわけではないようだ。
入っては行けない場所にいることを見咎められて、罪の意識を覚えているふうでもない。
「何をしている」
できるだけ、苛立ちを表に出さぬようにして彼は話しかけた。
「・・・眠れなくて」
ありきたりな返事だった。
だがそれでこんな場所に来る、その理由にはなっていない。
「部屋に戻れ。・・・ひょっとして寝る場所がないのか?」
決闘者の分しか部屋数が用意されていないことを思い出して、彼は尋ねた。もしそうなら磯野にでも言って関係者の部屋を一つ空けさせようとも考えたのだ。
だが、少女は軽く首を振った。
「いえ、舞さんの部屋に」
大きめのソファセットは杏子と二人で寝ても十分な広さだ。
御伽と本田が城之内の部屋で寝ていることを考えればさほど不自由はない。
「でも・・・あんな舞さんを見ているのはつらくて・・・」
孔雀舞はマリクとの闘いで精神の闇をさまよっている。
孔雀が倒れてからずっと、この娘は傍で付き添っていた。ために彼の決闘の観戦もしていない。
そのことを思い出して「看病疲れか」とふと口にした。
「疲れた・・・というわけではないんです。ただ・・・あたしにできることが何もないのがつらくて・・・」
「この場合誰がついていようとできることは何もない。お前ひとりが自分を責めたとて何ひとつ事態は変わらんぞ」
聞きようによってはひどい言葉遣いだった。そんなことはない、お前のせいではないのだからとでも言ってやればいいのだろうが、あいにく彼の辞書にはいたわりなどというオブラートは存在しない。
「それは、そうなんですけど・・・」
早く戻れ、とうながしても少女は腰を上げようとはしなかった。
窓の外は雲が厚くなって、時折月を隠すようになっていた。黒雲も混じりはじめているところを見ると、下界は晴れているのだろう。
夜間の飛行の間、スピードは落とすように指示してあった。ゆっくりと雲が流れていく。/p>
「早く、戻れ」
もう一度彼ははっきりと告げた。
対する少女は曖昧に微笑するだけでまだ立ち去る気配を見せない。
とうとう苛立って彼はやや声を尖らせた。
「あそこに書いてある文字が読めないのか。ここは立入禁止区域だと何度言わせる。そもそもお前が決闘者だったら即刻失格になっているところで・・・」
咎める声が尻すぼみになったのは、気丈な彼女の顔が泣きそうに歪んだのがわかったからだった。
「な、なんだ」
泣いて済むと思ったら大間違いだぞ、と続けようとした彼の耳に入ったのはか細い声だった。
「・・・・・・めません」
「なに?」
「読めません・・・だって・・・」
彼女が読めない、と言っているのが、扉に大きく白抜きで書かれた「関係者以外侵入禁止」の文字のことだと分かって彼はなおいっそう声を荒らげた。
「何が読めないだと?! あんなに大きく書いてやっているではないか。貴様、言い訳にしてももう少しましな・・・」
「だって、わからないんです!!」
彼よりも早く怒鳴り返したのは少女の方だった。
「・・・なに?」
「わからないんです・・・なんて書いてあるのか・・・ここだけじゃなくて。注意事項とか書いた紙もらったけど・・・読めない字がいっぱいあって・・・なんとかお兄ちゃんや杏子さんに教えてもらったけど・・・漢字がいっぱいあって・・・」
「・・・・・・あ・・・」
そう言われて始めて、彼は思い出したのだった。
少女のこの瞳が、外の世界を映すようになったのが、ほんの数時間前だということに。
「あたしができることなんて、なんにもないんです」
文字、一つ、まともに読めなくて。
「舞さんの薬とか、お医者様に頂いたけど・・・ふくよう、とか読めない字が多くて・・・しちゃいけないこととかしなくちゃいけないこととか、わからなくて・・・」
口で説明されたことは覚えられても、詳しいことはこれを見て、なんて言われて渡された紙は読めない字だらけだった。杏子が遊戯の対戦が終わって帰ってくるまで彼女は途方に暮れていたのだ。
気まずい沈黙が落ちた。
少女の瞳からはとうとう涙が溢れて止まらなくなっている。
涙の原因は彼の与り知らぬところだが、最後のとどめを刺したのは確実に彼だ。
だがどうしてやることもできない。
どういう言葉も、かけられない。
「・・・・・・その、長かったのか、失明期間、というのは」
「8歳の頃からです。完全にではなくて、ものの形とか、そのくらいならぼんやりとは見えてたんですけど」
涙をぬぐって、彼女はぽつりぽつりと話し出した。
完全に失明しないためにずっと病院暮しだったこと。
次第に悪くなるからなるべく目を使わないようにと言われたこと。
目が見えるようになった今でも、学力が追い付かないためにまだ学校に復帰するめどが立っていないことも。
「ひらがなとかかたかなくらいならなんとか分かるんですけど、漢字が多いと何がなんだか・・・」
「・・・・そうか」
元来病気一つしたことのない彼には、そういったハンディを負った人間の気持ちはわからない。
だが、目が見えないということが日常生活にどれだけの負担をかけるか、それくらいのことは想像が付いた。
治ったからといって簡単に元に戻れるものではないのだ。
だからこそ己の無力に敏感になる彼女の気持ちが痛々しかった。
目が見えない、そんな病気にかかったのは、それこそ彼女のせいではない。
自分がまたしても致命的な失敗をしてしまったことに気付いて、彼は必至で対処策を探した。
脳内の言語中枢神経系をフル回転させると、知らずのうちに視線が空を彷徨う。上、下、左。
うう、とうめき声とも咳払いともつかぬ音をひとつ喉の奥で鳴らすと、未だまとまらぬ言葉を思い付くままに吐き出した。
「・・・・孔雀の件は医療チームのミスだ。専門の看護婦をつけるように言っておこう。それと眠れないと言うならオレの部屋を使え。オレは関係者のための部屋があるからな。それから・・・・それから何かわからないことがあったらモクバに言えばいい。オレの部屋の内線電話で0番を押せばモクバの携帯につながるようになっている。他に何か不自由を感じるなら必要な手を取るから何でも言え。オレからモクバに言っておいてやる。いいか、このデュエルシップの中では誰もが同じく、オレの下に平等なのだ。オレ以外の人間に権力はない。だからお前に力が無いのは当たり前だ。お前にできることがないのは当たり前なのだ。てゆうか何もするな。しなくていい。お前は黙ってオレの言う通りにして、あの凡骨な兄の応援にのみ心血を注いでいろ。たとえそれであの凡骨が負けたとしてもそれはお前のせいではない。お前はできることはやっている。それでいい。いいな? 納得したな?」
立板に水のようにまくしたてて、少女の手のひらに自分のデュエルカードを押し付ける。
自分の部屋を空け渡してまで、この娘に何をしてやりたいのか彼自身が今ひとつ意味不明だった。
案の定、きょとん、となった彼女に、では早く眠れ、と言いおいて逃げるように踵を返して立ち去った。
・・・といってもすぐ目の前のコンピュータルームに閉じこもっただけだったが。
それからしばらくして少女が立ち去ったのを、コンピュータルームの窓際に隠れるようにして確かめると、彼はようやく安堵のため息とともに、その狭い部屋の隅に据え付けられた簡易ベッドに潜り込んだのだった。
「なんだこりゃ」
翌日。朝食を取り終えて自室に戻ってきた城之内以下決闘者様ご一行は、愛想も素っ気もない鉄の扉に子供の落書きかと思うような黄色いペンキの跡を見て目を丸くした。
『 は い る な 』
「 関係者以外侵入禁止 」
「書き直されなくても分かってら」
厭味かよヘンなやつ、と兄は付け加えたが。
静香だけはその意味を理解して微笑んだ。
( やっぱり、海馬さんて優しい人だなぁ )
でも、兄にそれを言ってもやっぱり絶対認めてはくれないだろうと思ったので、夕べの晩、誰のベッドを借りたのかは内緒にすることにした。