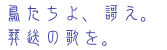
鳥葬といい、風葬という。
彼の育った村では死者は村から少し離れた荒れ野に運ばれ、そのままうち捨てられるのが決まりだった。
野晒しになった死体に鳥が群れる。
さして豊かでもない、北の荒れ地。
辺境にほど近いその村には鳥たちが住処にするべき木も餌にするべき実も種も草もなく、
打ち続く戦乱に、秋の収穫はおろか春に植える種の入手さえ、とうに絶望視されて久しかった。
そのわずかな収穫すら奪い去り、死者の肉をついばみ群れをなして飛ぶ鳥たちは、彼らにとって禍々しい死の使いだった。
彼を育ててくれた老母が死んだ時も、同じように鳥たちの野辺に捧げられた。
ぎゃあぎゃあと意味もなく中空で騒ぐ鳥たちの声が、羽が、空から降ってくる。
雪のように白い羽毛もあれば闇のような黒い矢羽もある。
不思議な光景だった。
羽と糞に覆い隠されて、今までうち捨てられたはずの死体は骨すら見あたらない。
やがては彼の祖母も骨ごと鳥に還ってしまうのだろうかとぼんやり思った。
鳥に。
還る。
その発想がなんとなく気に入って、彼は明日からの生きる糧の心配を、一瞬忘れた。

それからしばらくして、蛮族に襲われた村を捨て、彼は都に出た。
てっとり早く食っていくために軍人になった。
力を得て、物を知り、夢も見るようになって、人間らしい感情や思想を人間の言葉で語ることを覚えた。
大切な人を得て、失いもしたが、その痛みを埋める代価も得ていた。
言葉で語ることもできず、得ることも、捨てることも、取り替えることもできない何かを見たのは、ただ一度だけだった。
それと出会った日、彼は出入りの商人から鳥籠を一つ、買った。
彼の館を訪れるたびに、鳥たちの声が騒がしい。
やけに鳥の多い場所だと思っていたら、主が飼っているのだと後で知って驚いた。
長いつきあいだというのに、そんな話を今まで聞いたことがなかったからだ。
ただでさえ使用人の少ないその家で、おおかたの人間が鳥の世話に時間を費やしているらしい。
主自身が留守がちなので、いいきばらしになるんですけどと、侍女の一人が苦笑していた。
「でもねぇ。なにしろ数が多いですから」
独り身の人間が家族がわりに獣を飼うことは珍しくないが、この館の主と鳥という取り合わせはなんとなく奇異だった。
いつか理由を聞こうと思いながらも、日々の忙しさに取り紛れた。
ある日、訪ねてみると、彼が庭でなにやら熱心に小槌をふるっていた。
何を作っているのかと尋ねると、彼は振り返らずに答えた。
――― 鳥小屋だ。
――― 鳥小屋?
――― そうだ。数が増えてきたのでな。移すことにした。
――― そんなに飼ってどうするんだ?
――― 別に。 飼うために建てているわけではない。
――― じゃあなんのためだ?
――― 閉じこめておくためだ。
――― 鳥を?
――― そうだ。
閉じこめておく、というその言葉にはどちらかといえば嫌悪の情がある。
嫌いで、嫌いだから閉じこめておく。そんなふうに聞こえた。
―― でもよ。鳥ってのは・・・翼があるんだし。やっぱり空を飛んでいる方がいいんじゃないか?
遠慮がちにいうと、彼ははじめて手を止めて、振り返った。
―― できるだけ、鳥でいっぱいにしたいのだ。
その言葉に、黄飛虎はさらに混乱する。
そう言った時の彼の表情は、好悪がどうというよりなにかしらの決意と、熱心さに満ちていた。
堅実な政治家が一つの事業を仕上げようとする時のような、そんな。
“ ―― できるだけ、たくさんの鳥だ。
それから、いつかある日何か変わったことが起きたら、
扉を開け、空に飛び去る鳥を見る。”
―― 何か変わったことって、どんなことだ?
―― 何かだ。世界が全て変わるような、そんな。
そういって彼は作りかけの檻を見ていた。
珍しく受動的な彼の物言いに、この男でも抗えない何かはあるのだろうかと、黄飛虎はぼんやりと思った。
それ以降、二人の間でこの鳥小屋についての話が話題に上ったことはない。
完成したのかどうかすら、黄飛虎は聞かなかったし、彼も話さなかった。
それ以上のことを聞くのがなぜだか恐ろしかった。
ぎゃあぎゃあと鳥が鳴く。
大きさも色も違う数々の鳥たちは鳴き声もひとつひとつ違うのだと、確かにそう教わったはずなのに、彼の耳にはいつも同じにしか聞こえなかった。
ぎゃあぎゃあと、まるで赤子の泣き声のようだ。
不快さに眉をしかめる。
うるさい。
黙れ。
鳥小屋は幾たびか補修を繰り返し、今では庭のほとんど全てを占領するくらいの大きさにまで拡張されている。
その中で不自由に翼を羽ばたかせる鳥たちが不満を訴えて鳴いていた。
ぎゃああ。ぎゃああ。
喚き続けていたところで自由になどなれるはずもない。
彼の気が変わらぬ限り。
世界が変わらぬ限り。
黙れ。
『――あれは誰ですか?』
『彼女かい? 妖狐の精だよ。名前は・・・今はなんと言っていたかな。忘れたよ』
『まるで鳥のようですね』
『そうかね? ああ確かに。傾世元穣を広げたところは翼に見えなくもないがね』
金鰲島に仙としてあがったばかりの頃。まだ彼が未熟な地仙に過ぎなかった頃。
初めて彼女を見た。
きれいだとか、身のこなしが軽いとか、そんな言葉の変わりにしたわけではなく。
ただ鳥のようだと。
あの荒野の大地を埋め尽くした翼を思い出しながら、彼は彼女をそう呼んだ。
『聞仲。私はもう駄目だ』
『側に――――居てくれ』
『聞仲くん。殷を――この子を守ってね』
裏切ったのは自分。約束を違えたのも自分だ。
これが最後の決戦になる。
敗北など考えてはいなかった。考えていたのは次の戦いのことだ。
避けて通れない戦いを今まで避けてきたのは、養い子への愛情ではなく、あの女への憐れみ故だ。
そんなことは当の昔に気づいていた。
だがそれ以上の感情について彼は自分自身の中ですら言葉にしたことはなかった。
身代わりのように鳥たちが庭先で喚き続けている以外は。
鬨の声とともに訪れる黎明の時ではなく。
満ちた月が見事な円を描く夜ではなく。
雲一つ無く晴れ渡る快晴の霹靂が美しい昼でもなく。
春と夏の中間の季節風がやや強くなった、どちらかといえば薄曇りの、昼食の後のしばしの休みも終わりかけた時刻。
花火が上がったかのような、爆発的な音に人々が振り返ったのは、そんな劇的でもなんでもない、平凡な時間だった。
何事かと振り返った人々の目に映ったのは、虚空を染める色の乱舞。
鈍色の空を一瞬に埋め尽くした翼のはためきは、困窮と荒廃に疲れ果て路傍にうずくまる朝歌の人々の目すら、天を仰がせた。
そして彼女もやはりまた、人々より一段高い場所、城の楼閣から、それを見ていた。
” ―― 大地から打ち上げられたかのように群れ飛ぶ、何百羽という鳥たちを。
―― 呆然としてそれから狂気にかられ、歌いながら、叫びながら、
―― 四方を逃げまどうありとあらゆる鳥たちを。
―― 炸裂する翼の花火を、光の中に放たれた色彩の雲を、
―― フーガの調べと化し、空を舞う、怯えきった音の雲を。”
朝歌の上空に一瞬出現した無数のはばたきはやがて小さくなり、現れたと同じくらい呆気なく四散した。
常ならぬ怪異は天変地異の前触れかと臣民たちを不安がらせたが、どうせ今更災厄の種が増えたところで何ほどのこともないさと誰かが言い、鳥葬の風習のない都では死の使いなどと恐れられもせず、やがて忘れられた。
ただうち捨てられた館の庭先で、無数の色とりどりの羽が大地を埋め尽くしていた。
閉じこめられていた叫びは空に還り、意味をなさない言葉の破片のように羽は地に残された。
やがてはそれも風に消える。
供も連れず、義妹たちにも告げず訪れた彼の館は、無人の気配だった。
庭先に散らばる無数の羽だけが、あの鳥たちの狂乱の痕として残っていた。
しばらくの間ずっと、彼女はその羽が風に揺れるのを見ていた。</p >
“―― 誰にも伝えられることのなかった想いの残照、
空を翔けていった叫びの余韻、大地に描かれた意味をなさない言葉の破片。”
受取損ねた彼の真意。
それを見つめる彼女の心象もまた言葉にも形にもできない混沌の中にあった。
彼のように解き放ってしまえたらと思い、けれど彼女を構成する全てと融合し渦巻き、細部にまで行き渡るこの想いを、いかにして取り出せばいいだろう?
唯一思いつける方法は、人間の女にしかできないことだった。
何一つ産み出せない彼女の体には、ぬくもりの余韻一つ与えられてはいない。
彼が彼女に残したのは狂おしい包容でもいたわりに満ちた愛撫でもなく、つぶてのように天から投げ落とされた羽根たちだけだった。
ばらばらになったその全てを再構成しても、産声を上げるものはなにもない。
彼女がその命題を解決する方法を見つけだしたのは、ずっと後になってからのことだった。
今はただ、鳥たちよ。
謌え。
この葬送の歌を。
―――死せる彼の想いの証に。
※作中のイタリック体は全てアレッサンドロ・バリッコ著「絹」(白水社刊)からの引用です。