
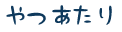
「まだ終わらないのか」
バカにしたような台詞だが、口調はいっかなのんびりした調子だった。
「……そんな簡単に終わらないわよ。てゆか、今日明日で終わるようなことじゃないし。一応ね、今あたしがやってることはいわゆるライフワークってやつなんですからさ」
普段の気品ある姿勢はどこへやら、机の上につっぷしかねない勢いでがりがりと羽根ペンを走らせていたパイロープは顔を挙げ、目の前のソファに優雅に身を横たえて長い髪を弄ぶ男を睨み付けた。
「今日明日で終わるようなことじゃないなら、明日にでもしてしまえばいいのではないかね? 分野は違えど同じ学術の徒として忠告するが、適度な散歩は発想の転換に役立つよ」
「それで絢爛の愚者を呼び出す方法も発明したわけ?」
強烈な嫌みだったが、相手はひるむ隙も見せず、長い髪をまたひとふさ梳いただけだった。
「ああ、あのやり方はもう先代達の間では確立されていた方法だったからね。ただ本気でやる人間がいなかっただけだ。根気と、緻密さ、正確さ、勤勉さ…まあそんなものさえあればできる程度のことだよ。確かにセンスは必要だったがね」
「世界を混乱に陥れるための勤勉さなど持ちたくもないわ」
「だったらそのへんで止めておいたらどうなんだね」
「少なくともあたしの研究はそんな目的でやってるんじゃないわよ」
「目的など、使う側の意志次第だよ。君が解答を見い出し、誰かがその結果を異なる意志で利用する。君の知らないところで、君のいない時代に、勝手に一人歩きを始めてしまう。魔術も同じさ」
「……」
違う、と言い切ることはできなかった。それは学問の永遠の課題だ。
そんなことはわかっているが、この男にだけは言われたくないと思う。
そしてそう言えば100になって反証が返ってくることは疑いなかった。 この男の言うことはいやになるほど正しくて合理的で隙がない。論争になれば負けることは目に見えているのだ。だから違う理由をまた挙げた。
「……きりのいいところで終わらせたいのよ。ただでさえ政情不安定でいつ図書館が出入り禁止になっちゃうかわかんないし」
その解答には男は肩を竦めただけだった。
確かに今のジールは揺れている。世継ぎの王子がト−ドリアに出陣した。 ところが一向に戦況の報告がこない。そのうちジークフロード師から進言があって、世界の律が狂い始めていると言う。それがなぜなのかパイロープはもう知っている。そして進軍した王子は多分もう帰ってこないつもりでいる。
やりきれなかった。
ジールにきて9年、軟禁状態とはいえ日常の生活は保証されていて、昼間でさえあれば自由に外にもいける。護衛という名の監視役でついてくる兵士はいるがおおむね親切で、侍女たちもいろんな話をしてくれる。気に入らないこともあったが、それなりに愛着もあった。
それなのに何もできないでいる。
あのときと同じように。
焦って苛つく感情がずっと根底にあって、それなのに原因を作った男はのうのうと目の前で自堕落に寝そべっている。
理不尽だ。
やつあたりしたい。
でもそんなことをしてもなんにもならないこともわかっている。
ああ。 やりきれない。
ぐるぐると渦を巻く感情はまた同じところに戻ってしまう。
ため息をついた時、ぞわりとするような感覚が走り抜けていった。
(………………!)
今の、なに? 慣れない感覚にとまどう。
第六感は鋭い方だ。だが、普段稀にくるそれとは違う。明らかな悪意を持った何かが心の中に触れていった。ざらりとしたイヤな感覚だった。
「ジールの王だな」
「え?」
彼女と同じものを感じ取ったのか、けれど不快感すら感じていない様子で男は言った。
「ジークフロード師から報告があっただろう。世界の律が狂っていると。」
「…だから?」
「ジールの王の狂気がこの城に充満しているのさ。魔法具だの、古い文献だの同様、象徴としての人は魔法の器になりやすい。この国は王権が強くて、王は老いていてしかも狂っている。器としては最悪だ。貪欲なくせに出口がない。だが破綻しているからこうやって漏れ出て悪意を捲き散らしている」
「……それって、かなり危険ってこと?」
「あれの影響にあるのはまだこの城の中だけだがな。他は他で……他のことでいろいろと影響が出ているだろう」
世界の行く末に関心のない男は、平坦な口調でまた寝そべった。
苛立ちがいっそう増す。 立ち上がって出て行こうとする背に向けて、男が言った。
「どこへ行く?」
「どこでも。少なくともこの部屋よりは……」
あんたといるよりはマシよ、と言いかけた言葉は男の言葉で阻まれた。
「少なくともこの部屋の方がいくらかマシだぞ」
「この城の、どこにいたって同じなんでしょ」
「私の傍の方がいくらかマシだと言っている」
それがいちばんイヤなんじゃないの!
怒鳴りかけて、くらり、ときた。
開け放った扉の向こうから腐臭にも似た嫌悪感が押し寄せてくる。 口を押さえて、身を竦ませる、その傍をすり抜けるようにして、男が扉を閉めた。
とたんに和らぐ不快感。
「わかったか?」
「ええ。これも魔術?」
「いや。世界の律は狂っている。従って私も魔術は使えない。だが私はヌホと会っていて、魔術には耐性がある。それに……ああいう悪意には慣れてもいる」
「……?」
「生まれてからずっと、ああいうものに囲まれて暮らしてきたからな。魔術だけでなく人の狂気にも耐性があるんだよ、私には」
声はやはり淡々としていて、それが不幸だとも思っていないようだった。
「世界は、これからどうなるの」
それを目の前の男に聞くのは心底違和感があった。
「さて?」
彼の反応は予想通りだった。わからないことはわからない。
「予測は6通りほど可能だが、不確定でそれ以上は絞れない。まあこのままいけば魔術の体系は破綻するだろうな。今まで蓄積された理論が全て無になるわけだ。それはそれで面白いが」
「おもしろい、ですって!?」
この後に及んでもそんな言葉を口にできる男の無神経さに腹が立つ。 男の目が始めて彼女を見た。深遠の瞳に映る暗い虚無。
「魔術など使えなくても、大差ない」
よりにもよってこの男の口からそんな言葉が出てきたので、彼女は一瞬怒りを忘れた。
「大差ない?」
「魔術など使えなくても、この世は存在するさ。多少、人死には出るだろうがそれで、人間世界が滅ぶとはね、私には思えないよ。魔術師の人口などしれたものだ。世界の大半は魔術など縁のない人間ばかりなのだし。まあ少しばかり大きな天災がきたと、そう思えばいいのではないかね」
「それでも海がひっくり返れば溺れる人はいるし、実っていた果実が実らなくなったら飢えて死ぬ人間もいるのよ。帰らない人を前にして、大差ないなんて、そんなことは絶対にないわ」
帰らない人を。 それが自分にとって誰なのか、何が自分を焦らせているのか。改めて思い知らされてパイロープは泣き出したくなった。
実際に泣いていたのかもしれない。
気がつくと、ソファに座り込んでいて、少し困ったような顔の男が白い布を差し出していた。
「ありがと」
受け取って目をぬぐい、鼻まで咬んでやったが、男は気にしたふうもなかった。 だが、返そうとしたハンカチは受け取らず、またソファに身を横たえて、目を閉じる。 彼女の取り乱した姿を見ても、何も言わない。
泣いたことで幾分すっきりした。顔をあげればやりかけのライフワークがほうり出されたままだ。 他にやることもなかった。
「……また、戻るのかね」
立ち上がって、机に戻った彼女を横目で見て、彼はつぶやく。 口調にはほんの少しの非難が含まれていた。
「しかたないわ。悔しくても、心配でも、今の私にもやっぱり他にできることないんだし」
「楓の種の旋回は」
男の言葉に、パイロープはえ、と目を丸くした。
「散歩に連れていけって、ひょっとしてそれを見に行こうってことだったの?」
クラスターの進軍後のどさくさ紛れに牢を抜け出してちゃっかり元の宝珠の部屋に居座った男が、連日押し掛けては散歩、散歩とせがむのは。
「以前見せてやると言っただろう」
「そりゃ言ったけど。でも楓の実がなるのって、秋よ?」
そんなことも知らないのか、と言わんばかりの彼女に、砂漠の国からきた男は取り澄ました顔を滑稽なまでに崩した。
「なんだって、それじゃあ」
失望感を隠しきれない様子で身を起こす。
「少なくとも後、半年は待たないと無理よ」
「………」
しばらく呆然としていた様子だったが、またため息をついてソファに沈み込む。
「まあいい。待つのは慣れているし」
「あら負け惜しみ? それまで世界の律が狂っていなければいいわね」
「そうかしまった」
そんなことを惜しがる男に、パイロープは初めて笑った。
不謹慎だとわかっていても、笑ってしまっていた。
「秋になったら、行きましょう」
その約束が守られることを信じて、彼女は世界と、それを守るために旅立った友の無事を祈っていた。
どうか、世界が。
また笑い声で満ちますように。
こんな狂気も、悪意もはね除けて、 どんな人の胸にも、希望が戻りますように。
なんの手出しもできないかやの外に置かれた人間が、多分みんな、今そう祈っている。
泣いたり笑ったり怒ったりやつあたりしたりしながら、祈っている。