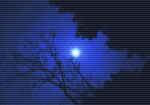ジャック・ローランドから手紙が届いた。
『お誕生日会のお知らせ』
3つ折になった便箋を開いて最初に目に飛び込んだ一文に、レイオットは「またか」とつぶやき天を仰いだ。
今度は誰だ、自分のじゃないだろうなと続きに目を通し、最初の一段落目でがっくりと肩を落とした。
日時と場所と対象人物。いずれも彼には鬼門だったから。
「お前なぁ……なんでよりによってこの日なんだよ……」
買い出しがてらカペルを連れてジャックの元に訪れたレイオットは、常より遅い昼食のテーブルで便箋を振りつつぼやいた。
「? なんで? 世間様にはいい日よりだよ?」
つか、お祭り日だしー、とサンドイッチをほおばりつつジャックが答える。
「ハロウィンの日なんてさ。おめでたいじゃん」
「ホントにその日が誕生日なのか?」
ううん、と彼は口いっぱいに食べ物を詰め込んだ顔を横に振った。
「ホントはその日より2週間前。でも休みが取れるのがハロウィンの前後だっていうし。ちょうどその日だったらフィリシスも都合いいって言ってたし」
「そうだろうともさ」
ジャックは単なる日常あるいは交友関係上の「都合」なのだと思っているようだが、一時期とはいえ同居していたレイオットは知っている。
彼女にとってハロウィンが「都合がいい」理由。
「新酒が届く日だからな……」
ワイン、バーボン、ラム酒にウォッカ。それが樽ごとごろごろトラック3台分も。よい酒とみれば節操なく収集する彼女にとって、ハロウィンは新年以上に待ち遠しい祝日なのだ。
「へえ。それは楽しみ」
「お前飲めるのか?」
「いんやあんまり」
嗜好品にうるさいジャックだが、まだ未成年を出てまもない歳のため、酒に関しては経験は浅い。飲み慣れている酒といえば、食卓に上るワインくらいのものだ。
「じゃあ意味ないだろ」
「いや楽しみなのは飲む方じゃなくて見る方」
「?」
「酔っぱらった人間っていろいろやらかしてくれるからさ」
「悪趣味っていうんだよそういうのを」
ため息をついてレイオットは傍らに座る少女を振り返る。
「お前は飲むなよ」
「飲みません」
即答だった。当たり前だ。未成年である。
一応念押ししたのはむしろジャックに聞かせるためである。
「おやつまんない」
「飲ませるなよ」
「飲みません」
からかい半分に言うジャックに釘をさすと、傍らの少女がかわりに再度答えた。
「まったく……」
最近妙に息が合い始めた二人にレイオットは若いもんは気楽でいいなどとじじむさいことを考える。
「それで何にするか決めた?」
ジャックがサンドイッチを食べ終わった手を、タオルでぬぐいながら聞いてきた。
「何を?」
作業再開と見て帰りかけるレイオットに、ジャックがレンチをふってみせる。
「決まってるじゃないか。誕生日だもの」
そこで効果的に間を置く。何の意味があるのかは知らないが。
「プ・レ・ゼ・ン・ト」
***
「プレゼントねぇ……」
そうは言っても具体的に思い当たるモノは何もない。
そもそも人に、まして女性に対するプレゼントなど今まで生きてきてただの一度たりとも送った経験はない。誰かを祝う、などという感情にも行為にも無縁の人生だったのだ。
とはいえレイオットもカペルも、3ヶ月前に祝ってもらう側として、彼女からしっかり贈り物をもらっていた。
「義理は返さなけりゃならんか……」
「はい」
通りを歩きつつショーウィンドーに飾ってある品物を横目で見ているが、どんなものを送ればいいのか見当はつきかねた。
「何がいいのかね。あんまり高価なもんだと性格上悩むだろうしな」
「本人に聞けばいいのでは?」
「それだとサプライズ・パーティの意味がないとさ」
そう。レイオットのときもそうだったが、こういうのは本人にないしょでやるのがいいんだ、というのがジャックの主張である。
そのために場所をフィリシス邸にしたのだ。
彼女くらいになれば「ハロウィンにパーティ」といっても違和感なく受け入れられるだろう。
女同士でもあるわけだし。
「ま、いいか。今すぐでなくても。そのうち何か思いつくだろ」
頭をかいてレイオットは問題を棚上げした。
カペルは何も言わなかったが、それが期限設定のない努力目標であることを誰よりもよく知っていた。
***
問題の人物がレイオット邸にやってきたのはその週末のことである。
この時点でハロウィンはあと1週間後にせまっているが、レイオットはもちろん未だに何の用意もしていない。
「スタインバーグさん、モールドの点検、すませました?」
「それならこないだ一仕事した時に……」
「それって2ヶ月も前じゃないですか! 戦術魔法士のモールド点検は月に1回って決まってるの知らないわけじゃないんでしょう?」
「いやまあ別に異常もないようだし」
「異常があるかどうか検査するのはエンジニアの仕事です! 専門家でないあなたの判断で万が一のことがあったらどうするんです! 専門のモールドエンジニアによる定期点検リストの提出は魔法士協会の定めるところの義務であって……」
「あーわかったわかった……」
館の中を歩き回るレイオットの後ろを追いかけつつ、こりもせずめげもせずネリンは「レイオット・スタインバーグ真人間化計画」を遂行している。
彼女にもらった本を読みながら、カペルはそんな二人のやりとりを何とはなしに横耳に入れていた。ちなみに今読んでいるのは『世界古典名作全集』。分厚いハードカバーの本を膝に乗せてページをめくる。
「まったくもう!」
夕食の支度と称して台所に逃げ込んだレイオットに、とりあえずの追求を諦めたネリンが戻ってきた。
居間に座り込んだカペルに気づいて、笑いかける。
「あら。本読んでるの?」
「はい」
「何の本?」
カペルの傍に座り込んでネリンはカペルがもう読んだ分として床に重ねていた山から一冊取り分けた。
「世界古典名作全集? ふーん、こんなのあったのね……おもしろかった?」
懐かしそうに目を細める。
「はい。だいたいは」
「そう」
本の背表紙を撫でるネリンの懐かしげな横顔に、カペルは聞こうと思っていた疑問を口に乗せた。
「読んだ中で、いくつかわからないことが」
「あら、何かしら」
実はレイオットにも聞いてみたのだが、彼はきょとんとした顔で「なんだそりゃ」とつぶやいただけだった。一応本の持ち主だったネリンなら分かるかと思ったのだ。
「この本の中で」
言って山の中から赤い背表紙の本を取りだした。薄めで絵本のようだ。
「月から来た女の人の話があります」
「ええ」
「求婚者に対していろんな贈り物をねだるのですが、品物の基準がよくわかりません」
「基準?」
「つばめの貝とか、ねずみの衣とか、石の食器とか」
「…………」
「なんでこんなものをほしがるのでしょう」
「ええとね……」
直訳すれば確かにそのとおりではあるのだが。
「つまりね……それは全て『この世にはありえないモノ』ばかりなの」
「?」
「『ありえないモノ』をねだることで、私のことは諦めてくださいって言ってるのと同じことなの」
「なぜそんな遠回しな断り方をするのですか?」
「そうね……」
正直言えばネリンもそう思う。いやならいやでそう言えばいいし、もし本当に手に入れてきたらどう言い訳するつもりだったのだろう?
「傷つけたくないから……ううん、違うわね……自分が傷つきたくない…方が正しいかな」
「?」
「断って相手ががっかりしたり悲しんだりすると、相手をそういう目に合わせてしまった自分が嫌になるのよ、だから……そうね。やっぱり卑怯よね、この話のお姫様は」
経験があるのだろうか? やけにしんみり語るネリンにカペルは本を見開きにしてネリンの方に向けた。
「どれがいちばんいいですか?」
そのページには問題の「贈り物」が図入りで載っている。
「え? この中で?」
郷愁に浸っていたネリンは急に現実に引き戻されて目をぱちくりさせる。
「はい」
言われてそれぞれの品を見てみる。
1.佛の御石の鉢
2.蓬莱の玉の枝
3.龍の首の玉
4.火鼠の裘
5.燕の子安貝
「・・・・・・」
どれといわれても。
「うーーん・・・どれもあんまり・・・」
「欲しくないですか」
「ええ」
なんでそんなことをといわんばかりのネリンにカペルは心のうちで用意したリストに×をつけている。
ちなみに彼女のリストでは、
1.佛の御石の鉢 = 食器・家庭用品
2.蓬莱の玉の枝 = インテリア雑貨系
3.龍の首の玉 = アクセサリ
4.火鼠の裘 = 衣類
5.燕の子安貝 = なんだかわけわかんないもの
・・・という分類になる。
その全てがダメだとすればさてどうしようか。
「?」
意外に真剣に絵本をにらんでいる(ようにもみえる)カペルにネリンは不思議そうな視線を向けている。
だが、レイオットが「できたぞ」とのんびりした声で夕食の始まりを告げたので、その話題はそれきりとなった。
さてと転んで行き着く先は結局限られている。
カペルにとって日常的な相談相手といえばお隣のシェリング夫人かジャックぐらいしかいない。
わけてもこういった問題をもっていくならばやはり、同性のシェリング夫人の方がよいだろう。
翌日掃除にやってきた夫人をつかまえて聞いてみることにした。
「へえ? もらってうれしかったプレゼント?」
無表情にこっくりとうなずくカペルに、シェリング夫人は目元をほころばせる。
いまだ感情の動きはわかりにくいながらも、どこか雰囲気の変わってきた少女について夫人は素直によいことだと思っている。
「そうだねぇ・・・まあああいうのは気持ちだからねぇ・・・」
「気持ち・・・」
「お金がかかっていなくても、自分のためにいろいろ考えてくれた気持ちがね、うれしいもんだよ」
そういいながらも、円満な家庭生活を営んでいる夫人は家族からもらった中でうれしかったもの、を思いつくままに上げてくれた。
「相手がいちばん欲しいものがわかってればいいんだけどね。なにがほしい、とか言ってるの聞いたことないのかい?」
最後にそう言われてカペルは考え込んだ。
ネリン・シモンズ女史のほしいもの。いつも欲しいといってるもの。
思いつくものは一つしかなかった。
***
「さあじゃんじゃん飲もうねーー![]()
![]() シモンズさん」
シモンズさん」
扉をくぐるなり「ハッピーバースデー!」の声とともに迎えられ、うれしいやら恥ずかしいやらでなにやら面映い感じのネリンに、本人よりも楽しんでいる風のフィリシスが酒瓶を撫であげる。
答えるまもなくネリンのグラスにはどばどばと高そうなワインが注がれた。
「これはねー、××っていう地方の数件でしか作ってない葡萄で取れるもんでさー。寝かせるより新酒のうちに飲んだ方がおいしいのよーー♡♡♡」
他にもね、これはねーとうれしげにテーブルの上に山と並んだボトルを指差しては説明してくれるが、そんな高価な酒など口にしたことのないネリンにはどこの酒造メーカーがどうでなどといわれても何がなんだか。
この酒ぜーーんぶあげるから持って帰ってねー♡と最後に付け足されたが、つまるところこれが彼女のプレゼントというわけらしい。
「たんに飲んで騒ぎたかっただけなんじゃないかあれは」
飲めない(飲まない)レイオットと未成年のジャックが、あきれた風に女二人の酒豪ぶりを見ている。
「かもねー。フィリシスにとってはいい飲み友達ができてめでたい限りだしさ。ところでレイは何持ってきたの」
「いいだろ別に」
興味津々といったふうにこちらを覗き込むジャックを適当にあしらいつつまわりを見渡せば、集まっているメンツは先日のレイオットの誕生日とほとんど変わっていない。シェリング夫人がいないことと、そのかわりに・・・
「やあ元気そうだねレイオット・スタインバーグ」
彼にとってはネリンよりも鬼門のこの男が加わっていることだけだ。
「あんたもなカート・ラベル魔法監督官」
いまだ魔法士になりたての頃、この男にいいように使われた経験があるレイオットは露骨に顔をしかめた。
「あいかわらずで結構なことだ」
「うむ。お互い健康で日々を無事に迎えられるのはめでたいことだな」
レイオットの皮肉をものともせず満足げにうなずいている。どうもこの男とレイオットでは人生観に決定的な差異があるせいか、お互い意思の疎通が今ひとつ。
「あんたこんなとこによばれてていいのか。家族は?」
「妻と娘は二人して旅行に出かけてしまったのだよ。最近流行りのスパとかいうのに凝っていてね。バーデン・バーデンで1週間強制ダイエットコースとやらに挑戦するのだそうだ」
「・・・・・・おいていかれたのか」
「子供はいつか親を追い越していくものだよ」
本来ならしんみり響くはずの言葉がこの男がいうと全然真実味がないのはなぜだろう。
「そんなところへムーグ魔法士から誘いがあったのだ。シモンズ監督官は私の部下。部下といえば家族同様。いわば彼女は私にとっては第2の娘とよんでもさしつかえない。その彼女の誕生日というのならば本来担当のロラン監督官を差し置いてムーグ魔法士主催のパーティに出席してなんの不都合があろうか」
「もってまわった言い方はよせ」
「私もどんちゃん騒ぎがしたかったのだ」
「ストレートに言うのもやめろ」
仮にも魔法管理局の部長にまで出世した男に涙目で駄々をこねられてもな、とレイオットは内心で盛大なため息をつく。
この調子で「予算が無いのだ」を何度やられたことか。
「ところであんたがたはちゃんと持ってきたの?」
主賓席のソファに陣取ってネリンを独占していたフィリシスがようやく男性陣に水を向けた。
何をとはいうまでもない。クラッカーを鳴らし、ローソクを吹いて、ケーキを切り分けた以上、お誕生パーティに必要なアイテムはあとはたった一つだけだ。
「ほいほい」
ジャックとラベルがレイオットの両脇でリボンと包装紙に包まれた箱を上げてみせる。あきれた風に少し離れた場所でそれを見ていたブライアンとシェリルも。
「うむ。くるしゅうない。献上を許すぞ」
本人を無視して話を進めるフィリシス。ネリンはと見れば苦笑しながらも楽しそうだ。
「んじゃまず俺からね」
いってジャックがテーブルに置いた箱の中身ははたして・・・
「これ・・・時計・・ですよね?」
真中に文字盤と針があるそれは時計と呼ぶにはえらく斬新な形をしていた。形も色もまちまちな巨大なベルが5つついている。
「ん。超強力目覚し時計。セットした30分前からベルが一つずつ鳴り出すの。5分前には全部のベルが鳴り出すから表3軒両隣まで響き渡るよ」
「・・ありがとうございます」
確かに寝不足で朝が遅いネリンにはいいプレゼントだ。ただちょっと・・・ジャックが作ったらしいというところに不安を覚えるが。
「なんか他にヤバげな機能とかついてそうだね」
フィリシスがネリンの気持ち・・というよりその場にいた全員の気持ちを代弁した。
「失礼な。一度動き出したら絶対に狂わない、止まらない、賢者石の魔導回路仕様だよ」
そういうところがヤバいんだ、と誰もが思ったが、当のネリンがひきつりながらも、
「ありがとうございます。使わせていただきます」
と、いったのでよしということになった。
「んじゃ次はラベル監督官ね」
「うむ。私はこれだ」
やけにずっしりした包装紙の中身は『試験によく出る魔法六法全書―直前対策過去問200選・爬虫類でも分かる模範解答付きー私はこうして1級監督官になった-』。
「・・・・・・」
「がんばって出世してくれたまえ」
「・・・・・・はい。ありがとうございます」
なんと答えていいものやらわからず、ネリンは頭を下げる。しかし一挙両得どころか一石で四鳥くらい狙ったこのタイトルははたして効果を代弁しているものなのかどうか。
「教育パパだねぇ」
ジャックが先ほどの発言を受けてか、笑いながら言った。
それ以外にもブライアンとシェリルからは射撃の訓練用にエアガンと手袋とイヤーマスクが一式。
こうやって並べてみると・・・・。
「なんか実用本意だねぇ・・・」
ネリン自身のキャラクターがそうさせるのか集まったメンツの好みに左右されるのか、どうも女の子のプレゼントらしくない。
「華がないっていうか・・・」
フィリシスとジャックが苦笑しつつつぶやいた。
「あ、でも役に立つものばかりですし・・・ありがとうございます。みなさん」
とはいえネリンももうちょっと・・・夢のあるものをもらいたかったと思わなくもない。今さら花だのドレスだのをねだろうとは思わないがしかし。
「あ、そういえばレイオットとカペルちゃんがまだだね」
「そうそう。いちばん世話になってるはずの人間がまさかなんにも用意してないなんてことはないよねぇ」
***
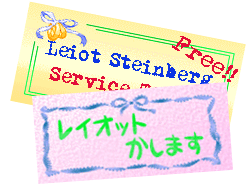
「・・・・・・してないわけじゃないが」
全員の注視を浴びてレイオットは頭をかく。
「じゃどこに?」
「それ」
ジャックの言葉にレイオットが指差したのは先ほどネリンが吹き消したローソクがたっている豪華な22cmホールのバースデーケーキ。
「え、これ?」
すごい、とシェリルが目を丸くした。
生クリームと季節のフルーツをふんだんに使った飾り付けはプロもかくやの腕前だ。
「昨日の晩からスポンジやいて作った」
そしてここに来る前にフィリシス邸の旧知のメイドに頼んで出して貰ったというわけだ。
集まった面子の中でもっともものぐさそうに見えるレイオットの意外な努力(?)に全員が驚嘆した。
「へええー料理する趣味なんてあったんだ」
以前いっしょに住んでいたはずのフィリシスの言葉に、レイオット邸訪問の初日から手料理をごちそうになっているネリンが微笑んだ。
「ええとってもおいしいですよ」
「あら。じゃ初めてじゃないんだ」
「え?」
「レイオットの手料理食べるの」
さすがに鋭い。
「ええ、まあ用事で伺ったときに時々・・・」
「いかんっ! いかんぞシモンズくん!!」
突然ラベルがネリンの肩をわしっと掴んで大声をあげる。
「あ、すみません・・そうですよね。やはりそういった饗応を受けるのは何かと問題が・・」
「こんなヤクザな男の手料理になどだまされてはいかん!! 気が付いたら一服盛られて売りとばされているかもしれんのだぞ!」
「・・・・・・おい」
レイオットは以前彼の家にやってきてはシチューの味に難癖つけておかわりをしていった旧知の男の背中を蹴った。
無認可の魔法士としてヤクザよばわりされるのは慣れているがこの男の口から出るとなぜか腹が立つ。
「ああっ、何をするのだ! みたかねシモンズくん。この男はこーゆー男なのだよ。こんな乱暴者の家に押しかけるなど今後一切やめたまえ」
「いや今のはあんたの方が悪いと思うがな」
同世代の人間として見るに耐えかねたのか、これまであまりしゃべらず傍観者に徹していたブライアンがあきれたようにつぶやいた。
「まあまあ。レイオットにしてはかなりマトモなプレゼントだったじゃないか。てっきり魔法がらみのご禁制品かなんかと思ってたけど」
「やれるかそんなもん」
入手するつてがないわけではないが、この監督官にそんなものを送ろうものなら、やったが最後後ろに手が回ることは疑いない。
「それじゃ、最後はカペちゃんね。何にしたの?」
ジャックに話し掛けられて、ずっと手にしていたアップルジュースのグラスを置いてカペルがポケットから取り出したのは、何かのチケットの束らしきものだった。
色とりどりの厚紙を切って作られたとおぼしきそれは確かに子供らしいプレゼントといえる。
「あら。何かしら」
肩たたき券とかかな? とネリンは思い、ほほえましい気持ちで受け取って・・・硬直した。
タイプライターで大きく打ち込まれたその文句を、フィリシスが横から覗き込んで読み上げる。
「『レイオット・スタインバーグ無料貸し出し券』?」
「おいっ!!?」
レイオットが慌てているところを見ると本人には一切無断であったらしい。
「『チケット1枚で1日無料ご奉仕。ただし魔法士としての仕事は除外。期間:本人が死亡しない限り有効』・・・」
続きをジャックが読み上げた。
「カ、カペルちゃん・・・?」
表情の読めないCSAの少女は笑うでもなく、真面目に答えてくる。
「シェリング夫人が今まででいちばんうれしかったのは息子さんから頂いた手作りの『お手伝い券』だったそうです」
「・・・・・・ええ」
「それと本人がいちばん欲しいと思っているものがあればそれがいいのではないかと」
「ほ、ほしいもの??」
レイオット・スタインバーグの無料ご奉仕が?
全員がつられてレイオットを見る。
プレゼントされてしまった当のご本人はいまだ唖然とした表情のまま、ぶんぶんと勢いよく首をふる。
「いつももっと自由にできる時間がほしいと」
「・・・・・・ああ!」
そういえば仕事が立て込んで忙しいときにそんなことを愚痴っていたような。
たまの休みもなんのかんのとたまっている雑事に追われてゆっくりできる時間がもっとほしいと――そんなことを言ったような――気もする。
「ヒマといえばレイオットほどヒマをもてあましている人間はいませんから」
「あのな」
確かにそのとおり。これには本人以外の全員が納得する。
「代わりにできることがあればと」
「・・・・・・・・・・・・」
筋が通っているといえばそうだが。
「だったらなんで自分でやらないんだよお前は」
断りもなくそういうことをするなと言外に含めてレイオットが当然のつっこみを入れる。
「CSAである私ができることには限りがありますから」
いたって冷静に言い返すカペルに彼が反論する前に、ラベルが笑い出した。
「こりゃあいい! シモンズく ん。せいぜいこきつかってやりたまえ」
「そうだな。普段ごろごろしているだけの人間にはいい薬だ」
「意外に器用だしね。料理とか代わりにやってもらったら?」
「以前部屋の模様替えしたいっていってたじゃない。男手あると便利よー」
「1日無料って単価的にどのくらいの時給分になるのかな」
めいめいが好き勝手にレイオットの身売りを歓迎している。
「勝手に決めるなよ・・・・・・」
とほほな気分でレイオットはつぶやいたが誰も聞いていないことは明らかだった。
傍らの少女をにらんでもその甲斐は全く無い。
ネリン自身はといえば困ったような顔でそれでも必死で笑いをかみ殺している。
実際のところ本気で使う気はなかったが、いざというときの切り札に使えなくもないかなーなどと考えていた。結構非道である。
***
帰り道、レイオットが彼女を送っていくことになったのは、フィリシスの「早速1枚使ってみたら」の一言による。
「すみません。送って頂いて」
ネリン自身は遠慮がちだったが、ちゃっかり1枚無料ご奉仕券をカペルに渡しているのをレイオットは目撃している。
返すなら俺に返せよとか思ったりもするが、大人気ない気もしてそれも言えなかった。
「いや、ま、帰り道だしな」
実際はやや遠回りなのをカペルは知っていたが黙っていた。 無料ご奉仕無料ご奉仕。
山ほどとはいえないまでも両手にはあまるくらいのプレゼントを、ネリンの手から取り上げて車を降りる。
「すみません」
「無料ご奉仕だそうだからな」
あまり部屋の中に入るのも気がひけて、入り口近くの床にプレゼントの山を置く。
「ありがとうございました」
玄関口で姿勢よく礼をするネリンに、レイオットは帰りかけた足をとめた。
ジャケットのポケットから何か取り出す。
「どうしようかとも思ったけどな」
「?」
手のひらサイズにおさまる小箱は上品な深い青のリボンでラッピングされている。
「いろんな意味で世話になってることだし」
レイオットとその箱を交互に見比べて、ネリンはそっとそれを受け取った。
「い、いいんですか」
「他に使い道ないし」
開けてみると出てきたのはプラチナの鎖のペンダント。トップのデザインも派手ではないが上品な造りだ。
真ん中の白い石がほのかに光を浴びて柔らかく輝いている。
「これって、ムーンストーンですか?」
「そういうらしいな。店員の受け売りだと」
「ありがとうございます。大切にしますね」
普段ならこんな高そうなものを、と遠慮するところだが、今日は誕生日のお祝いなのだ。
このくらいいいのかも。
自分を甘やかすのは慣れない体験だった。
目を細めてネリンは笑う。以前病院で見たあのあどけない笑顔だった。
「いや・・・じゃあ」
うれしそうにペンダントを胸元にかけるネリンを見て、きびすを返す寸前に、レイオットが言った。
「本物じゃなくて悪いけどな」
「え?」
ネリンが何か言いかける前に階段を下りていった。
「レイオット。何をあげたのですか」
ハロウィンの夜は満月の晩でもある。
月に照らされた森の道はほの明るく、急ぐ用もないとあって帰り道はのどかな気分だった。
「んー」
レイオットの返事は曖昧だ。ネリンが来た翌日カペルを残して街まで出て行ったレイオットが何かを買ってきたのは知っていたが結局それが何なのかは教えてくれなかった。
「ケーキだけではなかったのでしょう?」
「まあな」
別に秘密にすることでもないが、まあ洒落みたいなもんかな、とレイオットは独りごちる。
「カペル。月を手に入れる方法を知ってるか」
「月を?」
言われてカペルはフロントガラス越しに空を見上げる。
「わかりません」
そもそも月に所有権などないし、もらってもどうしようもない。
およそ非現実的な話がよりにもよってレイオットの口から出たので、カペルはこれはなんの謎かけだろうと考え込んだ。
「どうするのですか」
それでも重ねて聞いてみたのは、月にまつわる別の話が頭をよぎったからだった。
欲しくもないものを男にねだって、ひとりで月に帰っていった臆病な女の話。
「あの月をな。男が女に「やる」と言って、女が「はい」と答える」
「はい」
「それだけで月は女のものになる」
「・・・・・・そうなのですか?」
「ほんとかどうかは知らんがね」
「なぜそんな話を?」
その言葉に、レイオットはしばらく考え込んだ。
「さてね」
昔、彼も今のカペルと同じように、あの人の真意がわからずに聞き返した。だが帰ってきたのは少しつらそうな微笑だけ。
「昔、ある人に教わったのさ」
多分――彼も誰かに月をあげようとしたことがあるのかもしれないと、その時ぼんやり思った。
「ま、過ぎた望みだよな。高みの月ってな」
「高嶺の花の間違いでは?」
「月の方が手に入りにくそうでいいだろ」
「・・・・・・全く手に入らないと思っているよりいいと思います」
ふと虚をつかれて、レイオットはカペルを見直す。
「・・・・・・なるほど。そうだな」
月だって変わらずにあるのだし。花だって手を伸ばせば届くのだし。
失ったものもあるけれど、欠けていくものは多いけれど、変わらずにあるものも、新しく得たものもちゃんとあるでしょうと満ちた月が笑っている。
いつかと願うことは無駄ではなくて、いつの間にか気づかないうちに願いは叶っていたり、希望は戻ってきていたりするから、思い続けることが大事。
ただ信じることで月だって手に入る、それだけの話。
ただ願うことで誰かが幸せに笑ってくれて、それだけの話。
積み上げたささやかなものたちが月に届くまで。
「ま、今はあれでかんべんしてもらうしかないけどな」
「今は?」
レイオットの独り言にカペルは律儀に反応する。
返答に困ったレイオットは、
「そのうちな」
期限設定のない努力目標を口にした。
お月様まで、まず一歩。