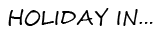
・・・というわけでバカンスである。(6巻参照)
「で、お前さんならどうする?」
内心、相談をかける相手を間違ったと思わなくもなかった。
案の定、問われた相手は自作と思しきいびつな銅製のティーポットを片手に目をきょとん、とさせている。
黙っていれば天使のようなジャック・ローランドは今日も今日とて油汚れたツナギ姿だ。
「家で飯食って寝てる」
数秒の沈黙の後に返ってきた答えはかなり参考にならない一般論だった。
「それのどこがバカンスなんだよ…」
やはりこいつに聞くんじゃなかったとレイオットはやや投げやりに返した。
「だって普段やれないことをやるのがバカンスだろ」
「お前が普段どんな生活をしているのかはだいたい想像がついた」
「だって別に行きたいとこなんかないし」
確かに、鉄筋コンクリート剥き出しの、わけのわからない機械に埋もれたこの工場に万年引き蘢っている機械オタクに健全なアウトドア式バカンスは似合わない。
だからといってジャック・ローランドはレイオットの知る限りではまだ20歳、いわゆる「お年頃」のはず・・・である。成績優秀なくせに実務に携わっている方が楽しいと進学を蹴った彼はたまの休みでもうれしそうに金にならない(つまり依頼人のいない)機械いじりで時間をつぶしている。確かに本人はそれで楽しいのだろうが、果たして本当にそれでいいのか青少年。
自身の重苦しい青春時代は棚に上げて、レイオットはため息をついた。
「あー、でもレイの場合はだめだよね。だって普段がそういう生活だもん」
「・・・余計なお世話だ」
そんなレイオットの心配はどこ吹く風とジャックはさりげなく暴言を吐いた。
「やっぱさ、こういう場合は山とか海とか、そういうんじゃない?」
瞬時に脳裏をよぎったのは「パラダイス=南の島」という俗っぽい想像だった。
いかんいかん、だいぶ毒されてきてるなと軽く頭を振る。
誰に、とは言うまい。だがあの監督官の言うことはどうも本人不在のときにふいに思い出されることが多く、しかも一度思い出すとなかなか頭から離れないのだ。
バカンスの計画などというものに本腰を入れてしまったのもそもそも彼女との会話のはずみからだったような気もする。
「カペちゃんはどっちがいい? 海派? 山派?」
答えないレイオットにどこで見切りをつけたのか、ジャックはティーカップの準備をしていた傍らの少女に声をかけた。
問われた少女はしばしの沈黙の後に、
「・・・・・・どちらでも」
という世界一参考にならない答えを返した。
「つーか、それでいちばん困ってるんだよ」
苦笑しつつレイオットが口をさした。
「?」
「カペルを連れていけるところとなるとな・・・」
「あ」
レイオットの苦笑の意味をようやく理解したジャックが間抜けな声を上げる。
どうやら本気でそのことに思い至ってなかったらしい。それはそれでありがたいことではあった。
世界中の人間がジャック・ローランドのようであったならカペルが生きて行くのになんの支障もないのだろう。
だがやんぬるかな、世界は異端を弾く。
ここに来るまでの道中でさえ、初夏の日差しを遮るには分厚すぎるフード付きマントを深く被ってきている彼女である。
その彼女が、海だの、山だの、いかにも露出度の高そうな場所に行けば・・・・
青い海。照りつける太陽。白い砂浜。水着ではしゃぐ人たちの中に混じるーーー迷彩柄フード付きマントの少女。
「・・・・・・・・・」
あやしすぎる。
もしくは。
青い空。涼しげな初夏の風。なびく夏草の高原。その中で裾はためかせたたずむーーー迷彩柄フード付きマントの少女。
「・・・・・・・・・」
いずれにせよ、あやしい。
「お気遣いなく」
顔を合わせて黙り込んでしまった男2人の間に立ってCSAの少女は短くコメントしたが、そう言われてはいそうしますと言えるほど無神経になれるはずもない。
第一、この場合問題なのは彼女の心情だけでなく、己の視覚に残る心象である。
たとえ他人も本人も気にしなかったとしても、バカンスの思い出としては情緒を削ぐこと疑いない。
「やっぱり無難なとこで無人島とかかね・・・」
仕事柄そういう場所にあてがないでもなかった。
人目を避ける無人島で、テントでもはって自炊してまあ軽いキャンプ? そんな感じで。
「うーん。それもいいだろうけどさ。それって普段の生活とどう違う訳?」
場所が変わっただけで、やってること変わりない気がするけど。
ジャックのコメントは容赦がない。
バカンス=息抜き。楽しい想い出作り。
という世間一般的な慣習に乗っ取って考える限り、レイオットとカペルが2人して無人島に行って誰もいない海辺でキャンプなどやってみたところで、何かわくわくどきどきするよーな思い出に繋がる要素は・・・あっても困るが、一切、ない。
図星を指されて沈黙してしまったレイオットに、ジャックは
「まあ、無理なことはやめときなよ」
と、これまた水を差すような無情な一言をくれた。
「どうしたもんかね・・・」
自宅のソファに寝転がりつつ、レイオットはひとりごちた。
やはり慣れないことはしない方がいいのだろうか。
柄にもなくバカンス、と軽く考えていたのだが、予想以上に(自分たちには)困難なことだったようだ。
どだいレイオットにもカペルにもバカンスなどということに対する期待感とか昂揚感とかが欠けているのだから、何をしたら楽しいのか、そもそも楽しいというのがどういうことなのか、それが分からない。
自分はともかくカペルにはそれではいけない、と思ったからこその今回の計画だったのだが。
「お気遣いなく」
床の上で転がるシャロンを観察していたカペルは、そんなレイオットの気遣いを否定するかのようにこの計画になんの関心も示していなかった。
「こんにちは、スタインバーグさん、カペルちゃん」
ふ、とため息をついた瞬間に、背後から響いた挨拶は、いつものように分厚い書類を抱えたネリン・シモンズ監督官のものだった。
「ああ・・・あんたか。気がつかなかったよ」
「・・・だろうと思いました」
もはや主が扉を開けるまでもなく、チャイムを鳴らして鍵がかかってなければ勝手に上がり込んでくるほど、この監督官の訪問はなじみになっている。
何しろ、スタインバーグ邸は在宅であったとしても、チャイムから10分は待たなければ扉が開かないという配達員泣かせの家である。
いるのかしらいないのかしらなどと扉の前で悩む時間をネリンはとっくに無駄だと割り切っていた。
「それで? 今回はなんの書類だ?」
ここのところ仕事の依頼はかかっていなかったはずだがなとレイオットは首を傾げた。
「いえ、違うんです。これはたまたま家に持ち帰る分というだけで。今回伺ったのはカペルちゃんの方で」
「カペル?」
呼ばれた彼女が猫から顔を上げて少しきょとんとした目でネリンを見た。
「そうなんです。あのね、カペルちゃん。よかったら夏の間、うちに来ない?」
ネリンの意外な申し出に、カペルとレイオットは思わず顔を見合わせた。
「あんたの・・・家?」
「ええ。あ、家って、実家の方ですよ? 実はナレアから手紙が来て・・・」
不本意ながら世話になったし、命の恩人だし、いろいろと知りたいこともあるしで、夏の間遊びに来ないか、というお誘いだった。
「何もない田舎ですけど。その分静かだし、自然も豊かでいいところですよ?」
「いいのかね? そのー・・・ご両親とかは」
「母がいますけど・・・多分ナレアが説得したんだと思います」
戦術魔法士にCSAという世間一般には受け入れがたい取り合わせをどうやって説得したのかは知らないが、あのナレア嬢がそうと決めたのなら多分誰も誰も逆らえないのだろうな、と漠然とながらレイオットは事情を推察した。
「・・・どうする?」
レイオットとしてはおそらく「どちらでも」というかわり映えのない返答だろうと踏んでいたのだが。
「・・・ぜひ、行きたいと思います」
予想に反して返ってきたのは、熱のない口調の、積極的な返答だった。
「意外だったな・・・」
カペルが眠たげなシャロンを連れて自室に戻った後、レイオットがつぶやいた言葉にネリンが笑みを返した。
「カペルちゃんですか? そうですね。私もちょっとそう思いました」
「少しは前向きになった、と喜ぶべきなのかね、あれは」
単純に祝福してやるにはなんとなく複雑な心境だ。
「・・・淋しいですか?」
そんなレイオットを見透かすように、ネリンの言葉には揶揄するような響きがある。
「あのな」
思わず言い返したが、そんなこと全くない、と言えるほど平気な訳でないことも確かだった。
「楽しいバカンス、のはずだったんだがなぁ・・・」
話を反らすようにぼやいてみせる。
「あら。私といっしょでは楽しくないとでも?」
「やけにつっかかるなアンタ」
「何故だと思います?」
「?」
心無しか崩れない笑みがどことなくぎこちなく見えた。
「いいですよね。楽しいバカンス」
「・・・・・・?」
ソファから身を起こして彼女を見返せば、はっきりと、眼鏡の奥の目は笑っていない。
「どうしたんだ? シモンズ監督官」
「楽しいバカンス! 本来ならゆぅうっくり骨休みして、のびのびと遊んで、また次の仕事に備えるべく 鋭気を養うよい機会なんでしょうねええええ」
「・・・・・・とれなかったのか、休み」
「誰のせいだと、思います?」
目の前に置かれた厚さ2cmの書類の束。
「・・・・・・」
「とりあえず、1週間は有給もぎ取りました。『休み明けには』全部提出するって公約で」
書類の束と、顔面の筋肉を無理矢理ねじ曲げて作ったような笑みを見比べて、レイオットは背筋を逆立てる。
「・・・・・・まさか」
「『休み明けまでには』サイン、くださいね?」
夏休みの宿題を押し付けられた生徒のように、レイオットは沈黙した。
バカンスは、楽しいばかりとは限らない。
RAZZLE DAZZLE(鮎川考鳥さま)初出