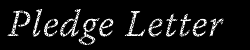
二次拘束術式図版はモールドとともに、魔法士の命綱ともいえる「装備」のひとつである。
しかしながら、その実効性についてはといえば、未だはっきりした検証がとれているわけではなく、モールドに組み込まれた一次拘束術式図版に比べるとその信頼性は著しく劣る。
そもそも肝心のモールドの設計理論にしてからが、経験主導の推論を試行錯誤の末にようやく体系化したものであり、根本的な原理については未だにはっきりしていないのが実情なのだ。
それでもどうにか理論化された基礎設計に基づいて、専門家の手によって製造された「機械」と比べ、いくら賢者石を使用した特殊な塗料を使用するとはいえ、皮膚の表面に、人間の手によって書き込まれただけの「模様」にどれほどの効果があるのか――ほとんどの魔法士が、モールドの損壊後すぐに魔族化していることを考えれば、ただの気休めだと言いきられても苦笑で答えるしかない。
せめても反論を試みるとするならば、「魔法」そのものが「使用者の意思の具現化」であるとする以上、その「気休め」こそが魔法士の精神的な安定という意味で重要な因子だからだ、ということになるだろう。
魔族という絶対的な脅威に対し、制限された魔法行使回数と、通常の使用方法では恒常魔族圏に阻まれてまず役に立たない銃火器を手に、自らの機転だけで戦いを挑まなければならない戦術魔法士にはかなりの精神的強度が必要とされる。
知らずのうちに蓄積されたストレスはぎりぎりの状況下でわずかな判断ミスを招く。そして戦術魔法士にとって現場での判断ミスは即、死、そして魔族化につながる。
故に魔法士は常日頃から精神的なストレスは感じないような生活を送るよう心がけているし、その一方でノイローゼに陥って身を滅ぼす者も少なくなかった。他人がどう思えど、現場に身を置く魔法士であれば、どのようなささいなこともたかが気休めと笑うことはできないのだ。
だが、レイオット・スタインバーグの場合―――
無資格の魔法士でありながら超一流と言われる腕を持ち、対魔族戦闘に関してはおそらく正規の魔法士よりも遥かに豊富かつ変則的な経験値を積んだレイオット・スタインバーグの場合、そんな「気休め」自体を必要としていない。有効性がどうのというより先に、その効果がもたらす「身の安全」そのものを求めてすらいない、というのが本音である。
従って、これまでは二次拘束術式図版を省略して戦いの現場に臨むことも少なくなかった。
だが、最近、トリスタン市における魔族化事件が大幅に増加し、魔法士以外の――本来ならば魔族化とは無縁のはずの一般市民ですら安易に魔族化するという深刻な事態を受けて、市政府および労務省魔法管理局といった公的機関からの依頼(正式な依頼、という形は取れないものの)を受ける回数が増え、今までは省略していたその図版を身につけることも多くなっていた。
正規筋の依頼の場合、その図版を記入した上で、モールド装着前の状態を撮影・提出する義務が生じる。無資格の彼には本来必要のない行為であるが――それをしないと、半ば暗黙のうちに彼の「担当」になっているネリン・シモンズ監督官の事後処理にまたひとつ面倒が増えることになる。ただでさえ彼を起用する為に余計な処理を抱え込まなければならない彼女の労力を、少しでも軽減するために、彼はそれを受け入れている。
どれだけ請求・懇願されても正規の資格申請書類にサインしない彼の、いわば、ささやかな贖罪のつもりであった。
だが、その日。
やはりケースSA発生の連絡を受けて、現場に急行し、モールドを装着しようとしたその時。
レイオットは、常のように助手であるカペルテータの方を振り返り、いつもの処理を頼もうとした時点で―――お互い同じものに視線を合わせたまま黙り込んでいた。
彼女の右腕に巻かれた包帯。右肩から釣り下がり、その腕を固定した大きな三角布。
彼女のその怪我は、ジャック・ローランドの研究所を訪ねた際に起こった不幸な事故のせいだった。
ジャックが例によっていいかげんに積み上げていたガラクタがふとしたはずみで落ちて彼女を巻き込んだのだ。幸い負傷したのは腕だけで命に別状はないものの、完全に動かせるまでは全治2週間、という診断がくだされた。(CSAである彼女を見てくれる医者といえば当然モグリになるが、たかが腕の骨折程度で診断ミスをすることはないだろう。)
しばらく無言で見つめ合った後、レイオットが一応、といった風に聞いてみる。
「・・・動かせそうか?」
「おそらく無理だと」
それはそうだろう。怪我がどうこういう前にギプスでしっかりと固定されているのだ。器用な彼女は食事などは左手で行っているのだが、さすがに文字を書くような複雑なこととなると利き手でなければ無理だろう。
「どうしたもんかね。省略するか?」
「代わりに書ける人がいなければ、それでもいいかと」
「代わり?」
二次拘束術式図版は基礎的な魔法工学理論を習得した者であれば書ける。逆に言えば魔法知識のない人間には書けないものである。魔法に関する詳細な知識は一般社会に対しては厳密に秘匿されているため、魔法関連の職種に従事する者でなければそう簡単に知ることはできない。最近では黒本などのような怪しげな魔法本が出回ってはいるが――レイオットの見たところその本に記載されていた二次拘束術式図版は甚だ簡略化されたいい加減なものだったように記憶している。
故に、今この場において、カペルの代わりに正確な二次拘束術式図版を書ける人間となると思い当たる人物は一人しかいなかった。
「どうしたんですか? 何か問題でも?」
支度の遅いレイオットに業を煮やしたのか、モールドキャリアの扉が開き、その当の一人が顔をのぞかせた。
トランクス1枚のレイオットと向かい合うカペルを見て、ふと眉をひそめて訊いてくる。
「? 何やってるんです?」
労務省魔法管理局二級監督官ネリン・シモンズ。
若くして公務員の中でも最大の難関、魔法監督官の試験に合格したエリートである。
この場に及んで申し分のない「代役」ではあったが・・・レイオットはなぜか短く嘆息した。
「はあ。二次拘束術式図版が」
「カペルがこの腕でね。すまんが頼む」
事情を説明されてネリンはすぐ納得した。
「わからないところがあったら、カペルが補助するから」
レイオットが言い添えるが、既にネリンは躊躇う様子もなく、レイオットの右腕に筆を滑らせ始めている。
さすがというべきだろうか。少し小首をかしげただけで澱みなく正確な術式図版を描いていく彼女は紛れもなく、魔法監督官試験においてその年の受験者中、最年少の合格者、全体でも上位10位内に入っていたという才媛ぶりを思わせる余裕に満ちていた。
さらにいうなれば、まがりなりにも「若い男」であるレイオットの裸体に近い姿を前にしてもいささかも取り乱した様子がない。そのあたりにも彼女の高い職業意識の片鱗が伺えた。
( さすがだな )
口には出さないまでもレイオットは秘かに感嘆していた。
ネリンの監督官としての仕事ぶりを間近にすることはこれまでにも何度かあったものの、今回ほど信頼できるパートナーとして意識したことはなかったかもしれない。
監督官としての彼女の経歴は浅く、まだまだ新米の危うさがある。一方レイオットはといえば十代の頃から魔法士として幾多の経験を積み、業界内ではベテランといって差し支えない人間だ。
従ってこれまでともに仕事をしてきた中で、主導権を握っていたのはどちらかといえばレイオットの方だった。
( これは――ちょっと考えを改めるべきかもな )
考えてみればネリンもレイオットともに多くの場数を踏んできているのだ。自己を律するところが強く、向上心もある彼女はおそらくひとつの事件から、彼以上のことを学び取っているのだろう。
足下に跪いて、膝から下の図版を書いていた彼女が、つと、立ち上がる。
「ああ、書き終わっ……」
レイオットが言いかけたとき、ネリンが顔を上げないまま、制した。
「あ、動かないでください」
まだ書いてないところがあったかな、と思う間もなく、胸元にそれは書き込まれていた。
心臓の真上。いつもは空白のまま残される場所。
I pledge my heart to be back to you as a human―――。
間違えることなく、流麗な筆記体で完璧なスペル。
目にした瞬間、レイオットは身を震わせた。
「・・・・・・」
無言のままその呪文を見下ろす彼の目には、ある種の嫌悪感とすら言ってよいものがあった。
「・・・シモンズ監督官」
強ばった声が、漏れる。
「消してくれ」
ぎりぎりのところで押さえた感情。
対するネリンは静かに彼を見返す。
返答は短く、一言。
「いやです」
「シモンズ監督官」
わずかに非難と哀願の響きが混ざった声を、ネリンは真正面から受け止めてもう一度だめ押しのように言った。
「消しません」
いうまでもなく、彼女は普段彼が”それ”を書かないことを、否、書かせないことを知っている。
何度も何度も、事件処理後に見てきた写真。そのどれにも見当たらなかった、”誓いの言葉”。
「御願いします」
聞く耳持たない、とばかりに彼女は背を向け、モールドのそばで彼を待つ。
そう。事態は一刻を争うのだ。
ここで言い争っている暇などなかった。
苦い表情で彼はモールドの中に身を横たえた。
固定の為にレバーに手をかけて待つネリンを非難の眼差しで見つめて、彼は言った。
「やっぱりあんたに頼むんじゃなかったよ」
まだそこまで自分を許せているわけではない。
なのに敢えて踏み込んできた彼女の行為は明らかに不快だった。
あんたは知っているはずなのに。
『おせっかいにも度が過ぎる』
そう、言ってやりたかった。
彼女の瞳に泣きそうな光が浮かんでいなければ。
分かっている。それが単なる逃避に過ぎないということは。
贖罪のために死ではなく、生を選ぶべきだと、頭ではわかっている。
死によって償えるものなど何一つなく、けれど本当に許しを請いたい相手はもういない。否、そもそも許されるべきではない、生きるに値しないとそう思いながらも死ぬことすらしなかった自分は、ただ逃げていただけだと、それはそう、はっきりとわかっている。
だが、何故に。なんのために。この罪を抱えてどうやって。
俺がここにいる意味は何だ。
傍らに贖罪の代替にした少女を置きながら、その少女自身からは復讐も断罪も否定されて。
生きている、その意味さえ見つからないというのに。
生きて戻ると、その誓いを躊躇いなく口にするにはまだ。
( もう少し、時間をくれよ )
いつかは見つけたいと思う。
いつかは、この罪を抱いても生きていく意味を持ちたいと思う。
いつかは、この手にその証を抱くのかもしれないとは思う。
だが、そのいつかは今ではない。
この誓いの言葉を捧げるに値する存在はどこにもいない。
( まだ、もう少し )
絶望の意味すら知らずにいた自分を見つめる覚悟を、時間を、逃げ場所を。
( 奪わないでくれ )
まだ、忘れさせないでほしい。
闇の隙間に差し込んだ光のまばゆさに脅える自分を、まだ許していてほしい。
( 俺は、そこまで強くない―――まだ。 )
魔族に相対し、高揚していくからだとは裏腹に、心は現実とは乖離していた。
命取りになると分かっていても、落ち着かない、この心地の悪さ。
胸にあるのは誓いの言葉。
そんな言葉に意味など無いとわかっているのに―――、鼓動の上に刻まれたその言葉はまるで呪詛のようにレイオットを責め立てる。
生きて、在れと。
