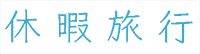
前置きがわりの最終回・改竄編
リナ 「えー、ごほん。『まぁよかったじゃない、ヴァルガーヴ。無事生き残れて!』」
ヴァルガーヴ「ほほぉ……神魔融合魔法の上に、重砕斬まで直撃させといて、言うセリフがそれか……」
ゼロス 「いやー、見事にぼろぼろですねぇ、ヴァルガーヴさん」
アメリア 「でも、不思議ですよね。ホントになんで助かったんでしょう」
ゼルガディス「リナが初めて重砕斬使った時も助かったんだ。何が起ころうと俺は驚かん」
ガウリィ 「案外話せば分かるやつなんじゃないか? あの金色のリナ」
ゼロス 「ちょっ、ガウリィさん。やつ、だなんてオソロシイ。本来なら名前を口に出すのもはばかられるような方なんですよっ」
リナ 「金色のリナってなんなのよっ!! ピンクのリナより恥ずかしいっ!」
ガウリィ 「だって俺名前しらねーもん」
ゼルガディス「知らないんじゃなくて覚えてないだけだろう」
ヴァルガーヴ「……お前ら、人を無視してわけのわからん話をすんな!」
リナ 「あーーっ、ごめんごめん。とにかく助かったんだからいーじゃない。浄化がどうとかいったってあんただって生き残れて嬉し
くないわけじゃないでしょ?」
ヴァルガーヴ「…………」
リナ 「ともかくせっかく生き残った命、ガーヴの意志を継いで、今後の余生も立派に生き抜いてってことで!」
ゼロス 「そうです。よければごいっしょに世界を滅ぼしてみませんか?
今なら三食昼寝に、おやつのチョコレートまでついて、獣将軍待遇でお迎えしますよ~」
ヴァルガーヴ「誰が行くか! この生ゴミ魔族!」
アメリア 「あ、同じ悪口」
リナ 「案外気が合うのかもね、フィリア……ちょっとフィリア? 何呆けてんのよ!」
フィリア 「えっ……あ、私……」
リナ 「だーめだわ、こりゃ。ショックで使いものになりそーもないわね、ヴァルガーヴ、そーいうわけだからちゃんと面倒みてやんのよ。じゃあね~」
ヴァルガーヴ「じゃあね~じゃないっ! なんで俺がこんな女の面倒みなけりゃならんのだ!」
リナ 「あ、カタートに竜の峯っていうとこに行くといいわよ。ミルガズィアっていうちょっと変わったおっさんがいるから。あたし紹介状書いといてあげるわ。礼にはおよばないわよ、わー、あたしってふとっぱら--!」
ヴァルガーヴ「だから人の話をきけ、お前ら!!」
ガウリィ 「腹へったなーリナ」
アメリア 「ゼルガディスさん、一緒にセイルーンにいく約束は……」
ゼル 「…………しばらくならな」
リナ 「あーいいことした後は気持ちがいいわねーーほら、ドジラス!! あんたはとーぶん、あたしがこきつかってあげるわ。一緒に来なさい」
ジラス 「へっ?、オ、オレ、ヴァルガーヴ様といっしょに」
ご、がきぃっっ!!
リナ 「なんかいった!? あーらどうしたのジラス?」
ガウリィ 「白目むいてんじゃないかな」
ゼロス 「じゃそーいうことで。ごきげんよう、ヴァルガーヴさん」
ヴァルガーヴ「だから人の話をきけといっとるだろーが、お前ら!!」
そんなわけで、前置きが長くなりましたが、ここから後が本編です。
最終回、L様とヴォルフィード様のご加護で無事生き残っちまった(……ということにした)ヴァルガーヴとフィリアのお話です。ご都合主義万歳!!
****
「よく参られた。リナ=インバースから事情は聞いている」
カタート山脈に住む黄金竜の長、ミルガズィアは彼にしては珍しく親しみのある笑みを浮かべて、彼らを迎え入れた。
内心どう思っているかはともかく社交辞令だけは完璧に、フィリアの一族の末期については触れぬまま、いつまでも逗留されるがよい、と言い置いて挨拶の言葉を締めくくった。
「ありがとうございます。お言葉に甘えさせて頂きます」
フィリアが短く答えて優雅な礼をした。
「ところで、彼が……その?」
多分リナ=インバースから話がいっているのだろう。
「ええ。ヴァルガーヴです」
たいしてフィリアはまたしても簡素な言葉を返す。
「そうか。この者が……」
ミルガズィアがまじまじと彼をみた。
彼らの過去のいきさつを知っているらしく、奇妙な顔をしてはいるが、同じ黄金竜とはいえフィリアたちとは仕える神も住む場所も違いすぎるとあって、自分が古代竜であるということに対してもあまり関心がないらしい。何となく複雑な気持ちでヴァルガーヴはうなずいた。本人、頭を下げたつもりである。
「なるほど、この者が……黄金竜にこづき回されてグレて半魔族になったあげく、主をなくしてヤケに走り、闇を撒く者(デュラグディグドゥ)に身を任せようとした古代竜の生き残りか」
「………………………………」
ひゅるりとカタートを吹き抜ける風が寒かった。
「……それはそうなんですけど、その、もうちょっと、言いようが…………」
フィリアがフォローにもなってないことを口走る。
「しかし、リナ=インバースの話では……」
あの女……どんな説明しやがった…………。
心中、密かにもう一度復讐を誓うヴァルガーヴ。
とどこおりなく(?)会見は終わったように見えたが、ふいにミルガズィアが思いついたように首を傾げた。
「失礼だが、フィリア殿とお会いするのは初めてであったかな? 御名をどこかで聞いたことがある」
「一度無理なお願いを聞いていただいたことがございます……父の名を通じて」
「ああ、そうだった。手紙を頂いたことがあったのだな。そうか。ハザード殿の娘御か」
「はい」
そこでミルガズィアはきまずげに沈黙した。その父ももはやこの世の人ではないということを思い出したためだろう。
「御一族のことは……気の毒だった…………」
「いいえ。自らが信じた正義に殉じたのですから本望でしたでしょう」
固い声でフィリアが返した。
ヴァルガーヴはふいにあることに気がついて眉をしかめた。
ここにきてからこの巫女は一度も笑っていない。
「あの時の者たちは……今でもここにおる。お会いになられるか?」
「いいえ」
やはり固い声でフィリアは返した。会いたくない相手なのだろうか? この巫女にしては珍しいことだ。
「そうか」
気の毒に、どうやらミルガズィアは墓穴ばかり掘っているようだった。
どこか気まずい雰囲気のまま、会見は終わった。
とうとう最後まで彼に詳しい事情の説明はなかった。リナ=インバースがミルガズィアにどんな説明をしているのかも分からぬままであった。
「なあ、おい」
会見が終わって、二人にはミルガズィアの屋敷にそれぞれの部屋が与えられた。
ここの一族はヒトガタでいるより竜形態のままで暮らしているのが普通らしく、ヒトガタの住むところといったら彼の屋敷くらいしかなかったのだ。
フィリアも昔は竜形態で暮らしていたようだがリナ=インバースとの道中で、すっかりヒトガタの方に慣れてしまったらしい。
水竜王の配下の館らしく水の庭園の上に浮かんでいる。部屋と部屋とを結ぶ回廊から、水面にうつった見事な満月を見下ろしながらヴァルガーヴは背後の小卓でティーカップを傾けるフィリアに問いかけた。
「なんでしょう」
「俺までひっぱってきてどうするんだ」
「どうするって貴方、どこか行くアテあるんですか」
「いや……ないけどよ」
「だったらいいじゃないですか。とりあえずリナさんの好意に甘えるということで」
「けどな」
あの女の好意に甘えて、いいことのあった試しがあるか。
そう言いかけたのをフィリアは故意に遮った。
「とりあえずここに身を寄せて、身の振り方はそれから考えましょう。あなたも私もしばらく心と体を休める時間が必要だと思います。……それなら一人より二人の方がいいわ。そう思いません?」
「…………あんた前からここの長と知り合いなのか」
フィリアの問いを敢えて無視してヴァルガーヴは逆に問いかけた。
「父の知り合いです」
フィリアの答えは簡素だった。
「手紙って?」
これは詮索しすぎかもしれない。たださっきの会話とここにきてからのフィリアの態度がどうもひっかかっていた。
「以前、故あって人を預かって頂いたことがあるのです」
「ふうん」
もっと続けるかと思ったがフィリアはそれきり口を閉じた。どうも話したくない話題であるらしい。
ティーカップを置いたフィリアはほとんど出し抜けにおやすみなさいと一言告げて部屋に戻っていった。
先ほどのヴァルガーヴへの問いの答えについても、それ以上の追求はなかった。
翌朝、朝食を取っている時にミルガズィアが会いに来た。
簡単に居心地はどうだったかという話の後、本題が切り出される。
「フィリア殿、例の者が会いたいといっておるがどうなさる? とりあえず今日の歓迎の宴には出席するとのことであったが」
「では宴の席でとお伝え下さい。……ここで会う気にはなれません」
「そうだな……わかった」
それでもヴァルガーヴに詳しい説明はない。もはやここまでくれば意地でも自分からは聞くもんかと彼は心中つまらない意地をはった。
歓迎の宴といってもヒトガタになれる者のみの集まりとあって人数はそれほど多くなかった。せいぜい30人程度で、贅は尽くしているものの親睦を深めるといった雰囲気はあまりしなかった。
原因は分かっている。
歓迎されるべき当の本人に熱が欠けているせいだ。彼自身は勿論の事。そうそうに柱の蔭に入って目立たないように酒杯を傾けていた。彼はフィリアの『おまけ』みたいなものでどちらかといえば招かれざる客だ。
だいたい黄金竜というのはどうにももったいぶった一族だ。
親愛の情を表すにも型通りやらないと、気が済まないし、型から外れたことは絶対にしない。
それでも酒が入ればそれなりに盛り上がるもので、彼はいつのまにか肝心の主役が姿を消していることに気がつかなかった。
慌てて周囲を見渡すがやはりどこにも姿が見えない。
いったいどこへ行ったんだ?
別に心配するわけではないが、それにしてもなんの断りもなく姿を消すような真似は彼女らしくなかった。
もう一度よく周囲を見渡しているうちに、ミルガズィアと目があった。
そういえば彼はフィリアの隣に席っていたはずで、いくらなんでも彼女が姿を消せば気がつかない筈はないだろう。
問いかけるように凝視する彼に、意味ありげに頷いて、手招きしてきた。
いささか酔いのまわった足取りで少し前までフィリアが坐っていた席に腰を下ろす。咎める者は誰もいなかった。てんで勝手に飲んでいる。
「フィリア殿は少し席を外されている」
酒杯を手にしたまま出し抜けにミルガズィアが告げた。
「ふぅん」
それ以上返す言葉が見つからなかったので、ヴァルガーヴは同じように酒杯を傾けた。空いた杯がすかさず満たされる。
空になった酒瓶を脇にどけて、隣のミルガズィアが視線を合わせぬまま言葉を継いだ。
「そなたはどこまで知っている?」
「何を」
「フィリア殿のことについてだ」
「おせっかいな巫女さん」
他に言いようがなかったので彼は即答した。
「その程度か」
苦笑したようにミルガズィアが言った。
「彼女の過去については?」
「全く」
これも即答する。過去というのはあまりおもしろいものではない。特に彼にとっては。
「フィリア殿がここにきたときは正直驚いた。思わず本人かどうか確認したくらいだ」
では最初の会見での会話はカマかけであったらしい。
「ここには彼女の一族の者がいる……知っているか」
「故あって人を預かってもらったとかなんとか」
「故あって……か。その人というのが誰なのかは聞いたか」
「聞いた。が、答えなかった」
「知りたいか」
ミルガズィアはどうやら彼に話したがっているようだ。
他人の秘密をべらべらしゃべくるようには見えないのだが、人は見かけによらないものだ。
……後日になって彼はミルガズィアが酔うとおしゃべりになるという話を知る。
「実はな」
彼の返事を待たずにミルガズィアは切り出した。
「預かっているというのは、彼女の元婚約者とその妻女だ」
「はん?」
咄嗟に言われた意味が分からなかったのでヴァルガーヴはまじまじと隣に坐る男の顔を見直した。視線の先にいる男の表情は最初にあった時の鉄面皮そのままでとてもゴシップに興じるようなところは見えない。
その彼から聞いた話によると、こうである。
フィリアには幼い頃から、親同士が決めた婚約者がいた。
ところがフィリアが100歳くらいのときのこと、その婚約者が別に恋人を作って婚約解消を申し入れてきた。当然ながらこのできごとは双方の親を怒らせた。結果、その婚約者は両親からは勘当され、神官位は剥奪され、恋人と二人して追放ということになったのだが、追放された彼らを保護してくれるようにミルガズィアに頼んだのが他ならぬフィリア自身であった、というのだ。
「……じゃあ、あの巫女さんは自分を裏切った男と恋敵の落ち着き先の世話をしてやったわけか?」
「そういうことになるな。私はハザード殿とは懇意にしていたがフィリア殿については名前くらいしかしらなかった。……が、彼女自身の署名とウィルコプト家の紋章入りの手紙をもった者がやってきたので受け入れた。そのときは詳しい事情も知らなんだし、断る理由もなかったのでな」
「物好きな」
「後になって事情を知ったが一旦受け入れたものを今更放り出す訳にも行かぬ。それで結局うやむやになった」
「…………なるほどな。でもなんでそんなこと、オレに話す?」
「知りたいのではなかったのか?」
思わず相手の顔を見直したが、別に嫌みを言われているわけではなさそうだった。ただ相変わらず鉄面皮なだけで。
満月はまだ欠けてはいなかった。
昨日見た見事な円の形そのままに、水面に映って揺れている。
回廊の欄干に手をかけて、彼は月を見ていた。
「……久しぶりだね」
「そうね」
しばらくの沈黙。
当然だ。話すことなどなにもない。
「奥様はお元気?」
嫌みのつもりはなかった。社交辞令としては適当だと思ったから口にしたまでだ。
彼は振り返って笑った。
「元気だよ……君も元気そうだね」
「ええ」
また沈黙があった。彼は何か言いたがっている。
なのに糸口がつかめなくて困っているようだった。
「みんなのことは……」
そこで口ごもり、先を続けられなくなる。
いつも迷ってばかり。
フィリアはため息をついた。
それを彼は誤解したようだった。
「ミルガズィア殿から聞いたよ……たいへんだったんだね……」
いたわりの言葉はどこか他人事に響いた。
「君にばかり重責を押しつけて、すまないと思う。……あのとき僕が逃げなければこんなことにはならなくてすんだかもしれないのに……」
そうだろうか? 一族が滅びることは避けられないことだった。彼がいようがいまいがそれは関係ない。
黙ったままのフィリアに、彼は余計に弁解のような言葉を繰り返す。
「自分の幸せのために君を裏切った……僕のことを恨んでくれてかまわないよ。なのに君は僕と彼女のことを最後まで気にかけてくれた。本当に感謝しているよ」
フィリアはやはり答えない。その表情からも何も窺えない。
彼は罪悪感に満ちた顔でこう締めくくった。
「ときにはたまらなくなるよ……どうして君を愛せなかったんだろうと」
月を見つめる彼をそこに残したまま、フィリアは立ち去りかけ、そこに立つ人影に気がついた。
どうやら立ち聞きされていたらしい。
そして立ち聞きと言えばもう一人。
相変わらず月を見つめている男を振り返る。その向こう側に立ち尽くす小さな人影。回廊の柱に隠れるようにして様子をうかがっていた。彼は気づいていただろうか? おそらく気づいてはいないだろう。
「偽善的だな」
傍らに立つ男が一言感想を漏らした。
「自分を捨てた男を恋敵ともども世話してやる方もやる方だがよ」
「別に……捨てられたとは思っていません」
背中を向けたまま、冷ややかな声が答えた。
「へえ?」
揶揄するような返答に、フィリアがはじめて振り返り、彼を見た。
「親同士が決めた婚約でした。私と彼との間に特別な感情があったわけではありません。彼が自分の恋人を自分で決めた時にはむしろ祝福さえしてあげたかったくらいです。なんにしろ自分では決められない人でしたから」
辛辣な物言いは彼の知るフィリアにそぐわなかった。
「そして今更あんな愚痴をこともあろうにあんたに漏らしている」
それは事実だったのでフィリアは訂正しなかった。
「あの人は……ああいう人です。今の言葉にしたって本気ではありません。ただ言ってみただけ……ほんのちょっと思いついた程度のことでしかないんです」
月に背を向けて歩き出す。背後の男はしばらくためらったようだが、後をついてきた。歩みを止めぬままで彼女は続ける。
「ただ言ってみただけ……思ったことを口に出して見ただけ。自分の言葉が他人の心にどんな反応を及ぼすかなんて、考えもしないんです」
そこで立ち止まり、もう一度振り返った。
彼女を裏切った男もこちらを見ていた。そしてその彼を見ている娘。
もはや何をいったところで聞こえはしないところまで離れた。
「性根がでたらめなんです」
瞬間、傍らの男が軽く目を見張った。
嫌いだったわけではない。けれど愛せないのも事実だった。その点では幸いなことに、彼と彼女の思いは一致していた。
けれど彼女とは違い、彼の口は考えなく動く。
「かわいそうに。彼女は怯えています。彼が云った言葉は彼女の耳に入っていたでしょう」
自分と彼が連れだって回廊に出た時からずっと、彼女の刺すような視線を感じていた。捨てられるかもしれないという不安。彼女はフィリアの実家の使用人の娘で、フィリアにとっては後輩にあたる。初々しい、子供のように無邪気な少女だった。恋を知った彼女は、猜疑と嫉妬に苛まれ、百も年老いたような印象だ。
「……お願いがあります」
自分を見つめる遥か向こうの視線を感じたまま、ヴァルガーヴに一歩近づく。
視線を合わさぬまま一言告げた。
「もしよろしければ、キスしてくださいませんか」
ヴァルガーヴの目が軽く見開かれた。けれどその驚いたような顔を見ていた者は誰もいない。一瞬で彼は自分を取り戻した。
「いいのかよ。仮にも……巫女だろ」
「それはもうとっくの昔に捨てました」
「けどな」
「あなたさえいやでなければお願いします。できれば彼らに見えるように」
なるほど。
自分は当て馬がわりというわけだ。
「いいんだな?」
「お願いします」
ためらいのない声。
ヴァルガーヴはフィリアの前に立ち、彼女を抱き寄せた。
彼女の背中越しにこちらを見ている男を見る。
その不幸ぶった顔を見ているのはなんだか腹が立った。
腕の中の彼女は身じろぎ一つせず黙って彼に体を預けている。
顎に指をかけ上向かせた。
背後の男とは対照的に、その表情は意外な程落ち着いており、口許には穏やかな笑みさえ浮かんでいる。
なんで笑ってるんだ?
意味を考える間もなく勝手に体が動いていた。
彼女の瞳が閉じられて、静かに唇が重ねられた。
ゆっくり三秒ほど数えてフィリアは唇を離した。
抱き寄せられている腕をほどこうとしたが、もう一度強い力で引き戻された。
さらにもう一度唇を塞がれる。今度は深く、舌が入ってきた。
抵抗するのも変に思われる……。
それで逆わなかった。
これがキス。
ぼんやりとフィリアはその感覚に酔いしれてみる。
たぶん、これでよかった。
相手が彼なら、きっと後悔しなくて済む。その予感は正しかった。
彼の手が彼女の髪を梳くように頭に回される。
その瞬間、フィリアは背後にいるはずの男の存在を忘れた。
己を取り戻すのは、ヴァルガーヴの方が早かった。
自分があて馬がわりだと、どこかでさめた感覚があったせいかもしれない。
実際にはダシにされたのは、ヴァルガーヴではなかったのだが。
ヴァルガーヴは口づけたまま視線を上げて、彼女の左肩越しに立ち尽くす男を見た。
その男はやや呆然とした表情で彼らを見つめていた。
ざまあみやがれ。
すっとした気持ちで彼は唇を離す。
フィリアの肩に手を回して抱き寄せると、二人並んで歩き始めた。
もう一度軽く振り返って、男に笑って見せた。嘲るように。
翌朝、ヴァルガーヴがまだ半分寝とぼけたまま顔を洗っている時に、もう一度ミルガズィアがやってきた。
「おはよう。心地よい朝だ」
曇天の天気でも同じ挨拶を繰り返しそうな彼に曖昧に頷いて、ヴァルガーヴは真っ白なタオルで顔をぬぐう。
「巫女さんならまだ寝てるぜ」
彼に用があるとも思えなかったのでヴァルガーヴは親切のつもりで教えてやった。
「そなたは元気そうだな」
「ああ。夕べはいい酒だった。ごちそうさん」
「夕べ……? なんだったかな」
大まじめな顔で首を傾げている。
ヴァルガーヴは思わず一歩下がって疑い深そうに彼を見た。
「冗談だ」
…………疲れるおっさんである。
「いや、半分は冗談でもないのだが」
なんなんだ、一体。
「昨日私はそなたに何か言わなかったか」
どうやらフィリアの事情をぺらぺら喋ったことを覚えていないらしい。
「いいやぁ、別に」
ちょっとそらぞらしくなってしまったが彼はしらばっくれることにした。
知らなくてもいいことは知らなかったことにしてしまうに限る。そうでなくても夕べは悪い夢にあてられたような気がしていた。
「そうか」
ミルガズィアは素っ気なく言った。
「どうやらそなたは酔うと記憶がなくなる質らしいな。いやよかった、よかった」
殴っちゃろうか、この男。
密かに背中で拳を固めるヴァルガーヴの前で、カマかけに成功したミルガズィアはどこから取り出したか扇子など仰いでいる。
と、ふいに思い出したようにぱちりと扇子を閉じた。
「それでは、昨日のことはまるで覚えとらんのか?」
「あーー、覚えてねぇ、覚えてねぇ。気がついたら寝台の上だよ」
「そうか。しかし、男として、してしまったことには責任を取らんとな」
「あ?」
夕べの記憶はしっかり残っているが、ミルガズィアが何を言おうとしているのか、ヴァルガーヴは一瞬図りかねた。
「考えて見ればよい縁組みかも知れぬな。そなたもフィリア殿ももはや同族は一人も……残ってないことはないが、おらぬも同然の身であるし。これも何かの縁。仲人は私が仕切らせてもらうぞ。式の準備もこちらでするから、案ずることはない。ああそうそうそなたが半魔族だということは隠しておいた方がよかろうな。なるべくささやかなものにするつもりだが、式に呼びたい者がいるのであれば今のうちに使いをだして、そうそう、リナ=インバースとあの連れを呼ぶのなら、人数は少なめにしておいてくれ、あれ一人で十人分は食うからな。あぁ、あと、いかに世話をかけたとはいえ魔族を呼ぶのもちょっと…………」
ほっておくといつまでも「式」とやらの段取りを果てしなく続けそうなミルガズィアを遮って、絶句していたヴァルガーヴは叫んだ。
「ちょっ、ちょっと待てっ!! なんなんだ、それは!!」
「何といって……そなたとフィリア殿との縁組みの話だが」
「あほうなことを言うな! 誰と誰が結婚だ!!」
「なに」
ミルガズィアはそこで始めて鉄面皮を崩し、眉根を寄せた。
「ではそなた…………」
「ああ。なんの誤解をしてんだか知らねぇが、オレは……」
なにもしちゃいない、という言葉を遮って、ミルガズィアが彼にびしっと指を突きつけてきた。
「フィリア殿を弄んだというのか!!」
「なっ、人聞きの悪いこというな!! オレはなにも……」
「甘い、甘いぞ、ヴァルガーヴ。古代竜の習わしがどうかはしらぬが、酔ったはずみとはいえ、かよわき婦女子に一夜の伽を強いておいて知らぬ存ぜぬでは、我らの正義が成り立たぬ! ましてやフィリア殿は神に仕えるべき聖位一位の巫女! 本来ならそんじょそこらの野良ドラゴンには姿を見ることすら許されぬ貴き身! さあ悔い改めるならば今のうちだ。さもなくばそなたには未来永劫『スケベ男』との烙印が押されるであろう!!」
イヤだ……そんな烙印……。
まくしたてるミルガズィアにヴァルガーヴはかつてない恐怖を感じてパニックを起こした。
「いっいち、一夜の伽ってなぁなんだ!! だれが、だれを弄んだっつーーんだ!! 妙な誤解するんじゃねぇっ!」
「弁解とは男らしくない。古代竜とはそんな卑劣な一族であったのか! フィリア殿もこのような男に身も心も捧げてしまうとはなんと憐れな……」
「だから、オレはまだ何もしとらーーーんっ!!!」
朝靄のはれた快晴の中、カタートの山々に、ヴァルガーヴの叫びがこだました。
お互い言うべき事も言いたいことも言い尽くして、肩でぜいぜいと息をするヴァルガーヴとミルガズィア。本気で勝負すれば体格と能力差でヴァルガーヴの勝ちであろうが、そんなことで竜形態になってまで決着をつけるのはなんとなく馬鹿馬鹿しかった。にらみ合う二人の空気がぎりぎりまで張りつめた時、さわやかな声が頭上から振ってきた。
「おはようございます……あら、お二人ともどうされたんです? ものすごい汗」
彼らの争いの元凶は、何も知らぬ気に回廊の上からきょとんとした顔で彼らを見下ろしていた。
「はあ? わたしとヴァルガーヴが……ですか」
ミルガズィアから事情を聞き知ったフィリアは、事情を知った後でもやっぱりきょとんとした顔をした。
「まさか、そんな。根も葉もない話です。いったいどこからそんな……」
「いや、私もそんな筈はないと思ったのだが」
先ほどの勢いはどこへやら、しれっとした顔で言ってのけるミルガズィアに、ヴァルガーヴの顎がかくん、と落ちる。
カタートのミルガズィア……あなどれない男であった。
「ゆうべフィリア殿とヴァルガーヴ殿が接吻を交わしていたのを見たという者がいてな」
それは根も葉もあることだったのでヴァルガーヴは思わず、真顔に戻って、ついた肘から顔をあげた。フィリアも緊張した面もちでミルガズィアを見返す。
「それは……いったい誰から……?」
「うむ……それが……」
ミルガズィアは一瞬口ごもった。
「フィリア殿の元婚約者殿からだ。彼の話によれば、それはもう濃厚な口づけであったから、絶対に一線は越えていて、夜毎愛欲の日々を過ごしているに違いないと……」
わざわざ「元婚約者」といったのは明らかにヴァルガーヴに教えるためであろう。
がたん、と音を立てて椅子が倒れた。
「ちょっと、どこへ行くんですか」
「ブッ殺す」
ぼそ、とつぶやくヴァルガーヴ。目が完全に本気であった。
「待って、今更、彼を殺してもどうにもならないわ。どうせ話はそこら中に広まっちゃってます」
「そのとおりだ。既に我が一族の中で知らぬ者はおらん」
フィリアのとりなしにミルガズィアが根拠なくきっぱりと頷いた。
が、それは結局ヴァルガーヴの損ねた機嫌に火をつけただけだった。
「じゃあ、どうすりゃいいってんだ!」
「放っておけばいいでしょう」
フィリアはあっさりと言った。
「あ?」
「ミルガズィアさんの誤解は解けたことだし。実害があるわけじゃないんですから」
「それは……」
確かに言われて見ればその通りではある。
あるのだが、しかし…………。
なんとなく釈然としない。
彼が困惑しているうちに、ミルガズィアはそそくさと帰っていった。
逃げやがったな、あのヤロウ……。
後で気づいて、ヴァルガーヴは憮然とした。
「性根がでたらめなんだっていったでしょう」
フィリアが溜息をついて立ち上がる。
「私も迂闊でした。あの人、あれで見栄っ張りだから、人に漏らすはずないと思ってたんですけど」
「それどころか、尾ひれに鱗までつけてしゃべくりたおしてくれたようじゃねぇか。誰と誰が愛欲の日々だぁ?」
「私と貴方がですね」
「落ち着いて、しれっというな!」
「ごめんなさい。でも、もう笑うしかなくって。私、うぬぼれてたんですね」
「あ?」
窓辺に立ってフィリアはかすかに笑った。初春の陽光がきらきらと水面に反射している。
「あの人のことだから、元、とはいえ婚約者を盗られたなんて認める筈ないって思ってたんです。でも、結局あの人にはつまらないゴシップにできる程度のことでしかなかったんでしょう」
それは違う、と彼は思った。
この噂は明らかに、フィリアを傷つけるために広められたものだ。
だいたいこの手の噂で傷つくのは女の方で、それもこともあろうに相手がかつての敵、半魔族である自分だというところに明らかな悪意が感じられた。
どこまでも腐ってやがる。
あの男のことだから、したり顔でミルガズィアにご注進に及んだに違いない。それもあくまでも自分はただ心配で、なんて言い訳をしながら。
そういう意味でいえばミルガズィアはだまされなかったわけだ。
ノリは妙だがなかなかあなどれないおっさんである。
「あんた、あの男に未練はないわけか?」
「あると思います?」
振り返ったフィリアに逆に問い返されて、ヴァルガーヴは返答につまる。
「昨日のアレは…………なんだったんだ?」
「アレってなんでしたっけ?」
「……………………」
「冗談ですよ」
ここの空気は人のユーモア感覚を狂わせるのだろうか?
それともミルガズィアのアレは伝染するとか。
ヴァルガーヴは密かに、自分だけは気をつけようと心に誓った。
「未練はありません。後悔もしてません。あの二人にはうまくいってほしいと心の底から思ってます。これでいいですか?」
「もし、あの男が駆け落ちしなかったら、結婚してたかもしれないんだろ?」
「やけにつっかかるんですね」
フィリアが肩にかけていたマントをとって椅子の背にかけた。
確かにそんなものを纏うにはうららかすぎる天気だ。
風が、卓上に活けられた花を揺らしていく。花弁が舞って、床に落ちた。
フィリアはまた湖面に視線をうつした。
「あの人が私に結婚しようといった時、なんと言ったかご存じですか? 『ぼくと君はきっと幸せになれると思う。みんなも喜んでくれるだろう』。……どう思います?」
「………………」
「私は……そんな言葉を望んでいたんじゃない……少なくとも、彼の言葉に同意することはできませんでした。私は……待っていました。けれど彼は一言も言わなかった。最後まで言わなかった。一度も言ってはくれなかった」
空の高いところでヒバリが鳴いている。緑の木々を揺らして湖面を抜けていく、さわやかな、涼やかな、風。
「それは、愛という言葉でした」
愛。
それは、この世でもっとも怖ろしい言葉の一つだ。
少なくともこんな天気の日にする話ではないような気がした。
彼女は振り返らない。泣いているのかもしれない。
彼は彼女の傍らに立った。
彼女は湖面を見ている。泣いてはいなかった。それで彼はほっとした。
「ヤツに愛されたかったのか?」
フィリアは笑って首をふった。
「…………昔は、ちょっとだけ、そう思ってましたけど」
「……ならいいか」
軽く息を吐いて、ヴァルガーヴは空を見上げた。
何も知らぬ気に晴れ渡った青空。
ひとりでむきになって馬鹿みたいだ。
ふいに何もかもどうでもよくなった。多分彼女もそうだったのだろう。
こんな天気の中で過ごすうちに、いつか。
少なくとも、彼女は彼よりは多く見てきたはずだ。こんな空を。
幸せの中で育った、こんな空の下で生きてきた、祝福の子供。
自分とはなんと違うことか。
しかし、かつて感じた妬心や羨望は、以前とは違ったものに姿を変えている。
憧れ? 希望? なんと呼べばいいのかは分からないが、それはとてもきれいな感情のように思えた。
ただ、こんな空の下を彼女と一緒に旅して、寄り添って、見上げている。それだけのことで。
「いい天気だな」
「そーですね」
「今日もいい月だろうな」
「きっとそーですね」
「いつまで、ここにいる?」
「それはあなた次第ということで」
「ついてくる気か?」
「いけません?」
しばらく考えて、彼は言った。
「ま、いいか」
時間は飽きるほどある。答えを出すのはまだ先でもいい。そのうちきっとわかるだろう。この穏やかな気持ちの意味が。
月を追って、空を見上げて、風にのって、雲を連れて。
明け方の海に着く、見えない船に乗って。星の降る夜に、月の軌跡を辿って。
そうして、彼らの長い休暇旅行がはじまる。
参考文献
◇「幽蘭露」 藤田あつ子 秋田書店(コミックス)
◇CD「天空歌集」より「休暇旅行」 谷山浩子