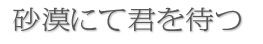
夢を見るのだ、とアイリスは言った。
それはなんということもない朝の、いつもの食卓で思い出したように呟かれた一言で、しかもその上彼女にそぐわないこと夥しかったので、オシアンはどうしたらいいか分からず、ただ困惑して紅茶を注ぐ彼女を見つめた。
「へえ、どんな?」
代わりに答えたのは、オシアンの向かいに座って一部の隙もなく身支度を整えたジャレッドだ。
その問いに特別な感情は籠もっていない。少しばかりの興味と会話の糸口に対する簡素な反応。ジャレッド・ソーンダイクはどんな異常な事態にあっても常に平静さを失わない男だ。
オシアンにとっては、アイリスがそんな私的な、自身の内面に立ち入るような話題を口にしたこと自体が驚愕に値するというのに。
「砂漠の夢だ。何もない、砂しかない、そんな場所の」
何もない、という言葉通り、彼女はそこで言葉を切って後は何も口にしない。それで話題は終わったと言わんばかりに。
唐突に始まって、唐突に終わる彼女の会話の癖にオシアンは未だ慣れずこっそりとため息をついた。
アイリスの外殻は牡蠣よりも硬く、そして同時に臆病だ。およそ感情と呼べるものは完璧に抑制され、相手の反応を伺いながら自身はそれを映す鏡としてのみ存在している。夢も欲望も、アイリスにとっては自身のものではない、相手に見せてやるものだ。
「ふうん。暗示的だな。お前の中身そのままのようだ」
辛辣な言葉から上手に棘を抜けるのはジャレッドの特技の一つだと思う。
だからアイリスは怒らなかった。仮に怒ったとしてもそれを素直に表すような人でもないが。
「そうかもしれないな」
ティーボットを置いて椅子に座ると、わずかに手を組む。朝食前の祈りは短く、おきまりの文句を唱えもせず終わる。二人とも神を信じていない人間だからそもそも行為に意味もないのだろう。それでも欠かさないのは、二人が妙なところで形にこだわる人間だからと、
「ジャレッド。テーブルに肘をつくな。オシアンが真似をする」
自分に対する教育の一環、なのだと思っている。
人の世界で生きる以上、最低限のマナーと常識は必要だ。形だけでも真似ておけとアイリスからは言われていた。アイリスは孤児の自分をまっとうな人間として育て上げることを自身の指命としている。愛情でもなく、同情でもなく、彼女自身が役割がなければ生きていけない人間だから、という理由で。
だからありがたがる必要などない。自分の手など必要ないと思う時がきたら、気にせず勝手に生きろとオシアンは言われていた。
「砂漠か。行ったことは?」
「ない」
気づけば会話はまだ続いていた。
「だろうな。だとしたら夢になど見るはずがない」
先ほどよりも何でもない言葉だろうに、なぜか今度の一言は棘が利いていた。ふと緊張が走った気がしてオシアンはカップを持ったまま硬直する。
「お前はあるのか、ジャレッド」
最後に相手の名前を呼ぶのはアイリスが回答を期待しているときの癖だ。通常、彼女の言葉は独白にーー否、芝居の台詞に似て、直接会話している相手よりも第三者の反応を伺うようなところがある。呼びかけは相手の役者に次の台詞をせかすための合図のようだった。
「軍にいたとき、駐屯したことがある」
「戦地か」
「エジプトだ。アレクサンドリアの占領の際に出征した」
「侵略戦争だな」
「反乱鎮圧の名目でな」
アイリスの辛辣な言葉をジャレッドは否定しない。
揶揄するように笑ってカップを傾ける。気づけば彼の仕草も役者めいていて、オシアンは観客であることを義務づけられているように口を出せないままだ。
「あそこはおまえが思うほどいい場所じゃない。暑くて、砂っぽい風と腐りかけで蠅まみれの食料しかない最悪の場所だ。うっかり気を抜くと熱病で倒れてそのままあの世行き。最近じゃ考古学ブームとかで観光も盛んらしいが、俺はごめんだな。あんな崩れかけの遺跡と汚物まみれのナイル下りの何が楽しいんだか」
「誰も行きたいなどとは言ってない。単に夢に見ただけだ」
「夢は願望の顕れというだろう。本当に行きたくなる前に釘をさしておいてやったのさ。お前の白い肌なんか半日袖をまくってただけであっという間に火ぶくれだ」
「だから行きたいとは言っていない」
今度こそ機嫌を損ねたようで、アイリスはぶっきらぼうに会話を打ち切った。
幕間の一幕がようやく終わったようで、オシアンはほっと息をつく。この二人にとっては——ことにジャレッドにとっては軽い会話遊びなのだろうが、正直なところオシアンは心臓に悪いので止めてほしいと思っている。
食事を終えたジャレッドは、じゃあ行ってくる、と立ち上がりいつものように出かけていった。
次にいつ帰ってくるのかは言わぬまま。
ジャレッドとアイリスがどんな関係なのか、オシアンには正直わからない。自分を拾ったのはジャレッドだが、一緒に暮らし、世話しているのはアイリスだ。
生活費は彼から出ているらしい、と朧気に察しているが、アイリスはアイリスで時折、芝居の端役などこなしてある程度の収入は得ているようだった。
ジャレッドはロンドンで事務所をかまえている。貴族や政府筋の私的なエージェントとして働くことが多いが、それ以外にも、自身の興味だけで勝手に動くこともあるらしい。それなのに最終的にはそこからも収入をひねりだしてしまうのだから有能と言っていいのだろう。何でも屋だよ、とかつてオシアンに笑って教えてくれたが、そのわりには卑屈なところがなく自身の仕事に誇りを——というより満足を得ているようだった。
あれは誇りなどで仕事をしていない、とはアイリスの言だ。あれは万事やりたいようにやるだけだ。自身の興味が最優先でそのためにどんな汚れ仕事をやることも、どんな罵倒を浴びることも気にしない。望んだ結果が得られればそれで満足な男だ、と。
オシアンの見るところアイリスはそのことに少し腹を立てている。
彼が賞賛よりも自身を満足させることに重きを置いていることについて。そしてそんな彼に利用されることについて。
決して喝采を浴びない舞台裏の演出家に、操られて踊るだけの人形が抱くような苛立ちと無力感をもって。
* * *
『何もない場所だ。ただ砂だけがある。風は吹いているが何も運んでこない。髪を揺らして私は立っている。建物はある。私が立っている家が。そう。砂漠の中の一軒の家だ。南欧の港町によくある家だ。壁は白く、扉も、柱も白く塗られている。生き物は他にいない。私は誰かを待っている。誰かは分からない。この家に私の他に人はいない。誰かを待って——しかし来ないことも同時に期待している。待ち続けている今がいちばん満ち足りているように感じるんだ。空っぽの家に空っぽの私がいる。そして気づくんだ。もう何も望むものはないことに。悲しみも喜びもない。ただ期待だけがある。胸がはちきれそうになりながら待っている。もしかしたら、万が一にも。地平線の向こうまで目を凝らしながら。来ないことが分かっていてもいつまでも待っている』
——舞台裏で出番を待っている時の気持ちに似ている。あれよりも空虚だが、その分期待は大きい。
アイリスは一息に語って、言葉を閉じる。
暗闇の中で、ジャレッドはその言葉を聞いていた。
窓から差す月明かりの中でアイリスは生き物の気配を感じさせずにそこにいる。語る言葉は彼女自身のことだが、全くの他人のことのように聞こえる。
アイリスは自分の中にそうした人格を何人も持っている。
時々それが堪えきれなくなったように発露する。抱えきれないほどの人生を生きてきた彼女は、あふれ続ける自己を自身の中に納めたままでいることができない。生来の女優なのだ。
そんなとき、ジャレッドは彼女の好きにさせてやる。唐突に始まる独白も、思い詰めたように収縮する視線も、周囲を全く無視して動く手足も咎めず、ただ眺めている。
そうして彼のためだけの一人芝居に耽溺する。
「お前の望みはなんだ、アイリス?」
芝居の終わりに、彼は口にする。
「何も。私には何もない。ただ周囲が求める私がいるだけだ」
「与えられた役割を演じ続けることが望みか」
「受動的だと笑うか? 私は、私の愛したものの望みを叶えることができればそれでよかった。かつては母の、リコの望みが私のすべてだった。なぜなら二人の望みは果てがなかったから。次から次へと何かを望んでは厭きて、また次を望む。望むものが大きい者ほど、私を充足させてくれた」
「なるほど、お前は人の望みを映す鏡だアイリス。望んだものが果てしないほど、お前の世界も広くなるというわけか」
闇の中で彼女の双眸は輝く。昼の光の下では深海のようにすべての光を吸い込んでしまうというのに。
「あの夢は、きっとお前のせいだ」
芝居の終わった彼女はどこか寂しそうに見えた。
待っているのにやって来ない。来ないことはわかっているのに待ち焦がれている。
「お前は、私に何も望まない。だから私は何にもなれない」
「役柄なら与えてやったろう。オシアンの母親役を。それだけでは不満か?」
それが一種の逃げであることを承知の上で、ジャレッドは口にした。
「……いや。感謝している。あの子がいるおかげで昼間はどうにか過ごしていられるからな」
だが、とアイリスは言葉を継いだ。
「時折、物足りなくはなる。あの子は私に望むより、私の望むとおりに生きようとしているから」
だから、もっと帰ってきてやれ。お前があの子に生きる望みをやってくれ、とアイリスはそう言葉を継いでジャレッドと同じように、逃げた。
* * *
砂漠の中に一人でいる。
白いテーブルの上に白いティーセットがある。二人分のカップに注がれた紅茶の片方に彼女は口を付ける。
相対する椅子にはもちろん誰もいない。
孤独には慣れた。待ち続けることも苦痛ではない。
彼女はもう、このままでもいい気がしている。
閉じこめられているわけではないことを彼女は知っている。たとえばそう、この足を一歩踏み出してしまえば、どこにでも行けることも。
待ち続ける必要などないのだ、と心のどこかで声がする。自由に生きろ、好きな場所に行って、好きなように生きろと。
分かっている、と彼女は思う。
だからそうしているじゃないか、と。
私は私の好きなように生きている。
来ぬ人も待つのも、私の勝手じゃないかと。
いつか彼がここに来たら、そう言ってやりたい気がしている。
そうして少し困惑する顔でも見れたらきっと満足だろうと、そう思っている。