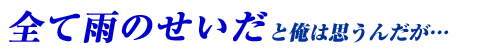
written by ミサモンタ様
木々の葉が黄色や、赤に色づき始めたこの季節。辺りは小春日和に包まれている。
しかし、秋雨前線が張り巡らされるこの秋は、突然天候が変わるという事もしばしば。
特に田舎と呼ばれるレイオットの住むトリスタン郊外は、その落差が都会に比べて大きかった。
カペルは、誰もいないリビングで、一人静かに窓の外を眺めていた。
外は先ほどまでの良い天気とは打って変わって、バケツをひっくり返したような雨が降っている。
雨は、風景を溶かさんばかりに滴を撒き散らし、空には黒い雲が占拠していた。
サーという音が、カペルを包み込む。他には何も聞こえない。
何をするでもなく、カペルはソファの上に座りながらその音に耳を傾けていた。
微動だにせず、姿勢正しく座るカペルの姿は、さながら人形のようであった。
しかし、そんな静寂に意義をとなえるかのように、カラコロと玄関のベルが鳴った。
どうやら来客のようだ。
今まで微動だにしなかったカペルが静かに上体をおこして、席を立つ。
そのままカペルは、玄関へと向っていった。
扉を開けた先には、いまではもう見慣れた顔のネリンが、びしょ濡れになって立っていた。
「こんにちは、シモンズ監督官。」
「こんにちは、カペルちゃん。突然ごめんなさいね。仕事で近くまで来たものだから、少し顔をだそうと思ったら、急に降ってきちゃって。」
心底参ったという表情で、ネリンが言う。
カペルは一通り上から下までネリンを観察すると、体を半歩引いてこう言った。
「中へ、どうぞ。」
無表情でネリンを招き入れる。
ネリンは少々戸惑った。始めは、顔をだすだけのつもりだったので、一瞬ネリンは、カペルの親切を受けるべきか否か思案したが、これだけ濡れていてはどうしようもないと判断した。
「お邪魔します。」
ネリンは、カペルの言葉に素直に従った。
いつものように居間に通されたネリンは、いつもいるはずの人間がいないことに気付く。
「カペルちゃん。スタインバーグさんは?」
「シェリングさんのお家へ、洗濯機を直しに行っています。」
ソーサリストなんて仕事をしていると、いやがおうにも機械にはくわしくなる。それに付け加え、ソーサリストは頭脳を要求される仕事でもある。
そのため、レイオットにとっては洗濯機を直すことなど朝飯前だ。
日ごろからお世話になっているシェリング夫人の頼みとあらば、むげに断ることもできない。
これらの事情により、レイオットは不在なのである。
「洗濯機を?直しに?」
「はい。」
あのスタインバーグさんが?という言葉は飲み込む。
胡散臭いという言葉が、服を着て歩いているレイオットほど、近所づきあいと言った言葉が似合わない人間もいないだろう。
しかし、今ここで、レイオットの意外な一面に驚いていてもしょうがない。カペルを困らせるだけだ。
「じゃあ、カペルちゃんはお留守番なんだ。」
「はい。」
「そっか、じゃあタイミング悪かったかしら。」
濡れた前髪を払いながら、ネリンが申し訳なさそうに言う。
「いえ、特にやることもなかったので実質的には問題ありません。」
これまた、本当に思っているのか判断できない表情で、カペルが言った。
しかし、意に介した様子もなく、
「そう言ってくれると助かります。」
とネリンが微笑む。
カペルは、そんなネリンの姿を一見すると、「少々ここでお待ちください。」
と言って居間を出て行った。
数秒後、戻ってきたカペルの手には、タオルがあった。
そのタオルを、ネリンの目の前に差し出す。
「この季節になると、雨が冷たいので、そのままだと風邪をひくかもしれません。
シャワーを浴びてきたらどうでしょうか。」
「え、でもそこまで迷惑かける訳には…」
確かに濡れた服を着替えたいし、熱いシャワーを浴びて、暖まりたい。
先ほどから背筋がゾクゾクして、寒気ばかりが襲ってくるのだ。
しかし、よくスタインバーグ邸を訪れるネリンも、さすがにそれには躊躇する。
「風邪を引いて同僚に迷惑をかけるよりは、ましだと思いますけれど。」
「ぐっっっ!」
カペルのその言葉に、ネリンは思わず変な声を上げる。そのあまりにも的を得たカペルの言葉に、ネリンは少々ダメージを食らってしまった。
「それを言われるとつらいものが。」
「ならば、ここでシャワーを浴びるのが妥当ではないでしょうか。」
素っ気無いカペルの言葉に、しばしの沈黙のあと、ネリンは喜んでと言うより、とほほな感じで、大人しくカペルからタオルを受け取った。
そのまま、風呂場へ行くと、ネリンは、濡れた服を一枚一枚脱いでいく。
水を含んだ衣類は、体のあちこちに張り付き、その不快感にネリンは思わず顔をしかめる。
「はぁ、まさかこんなことになるとは…」
これから特に用事がないときにこの家にくるのはやめようと、堅く心に誓い、シャワールームへと足を向けた。
(やはり、柄にも無いことはするもんじゃないな。)
雨の中をはや歩きで歩きながら、レイオットは一人胸の中で呟く。
シェリング夫人に頼まれて、洗濯機を修理するまではいいとして、シェリング家まで歩いていったのがまずかった。
シェリング夫人の家まで歩いて約10分かかる。確かにレイオットの足だと、急いだら5分位でつくが、それでもちょっとそこまで、という距離ではない。
いつもなら絶対に車で行っていただろう。
しかし、何故だか今日は柄にもなく歩きたくなったのだ。
もしかすると、先日ネリンに「もっと健康的な生活を送ったらどうですか!」などと言われたせいかもしれない。
そして、案の定、シェリング夫人に別れを告げてから数分後。突然雨が降り出してしまった。髪も服もしとどに濡れ、まさに「水も滴るいい男」状態である。
残念ながらいまこの場には、レイオットのその姿を喜ぶような人間はいないが。
雨は、先程より一層強さを増しているようだった。その証拠に雨音が大きくなっている。
そんな中を歩きながら、レイオットの頭の中に浮かんでいるのはたった一つ。
この体中に服が張り付く不快感と、寒さから逃れる事だった。
先程までの寒気はどこへやら。今、ネリンの体を包み込むのは、温かい湯気である。
その温かな抱擁とも言うべき快楽に、ネリンの体は桜色に染まり、頬は上気している。
家主であるレイオットの留守中に、勝手にシャワールームを使わせてもらっている事に多少の罪悪感は感じるが、やはり、この温かな誘惑には勝てず、ネリンの心はひじょうに幸福に満ちていた。
(さて、体も十分温まったし、そろそろ出ようかな。)
ネリンは給湯のノブに手をかけると、蛇口をキュイという音をならして閉める。
お湯が止まった事を確かめると、体中の水滴を拭うべく、脱衣所への扉を開いたのだった。
ガチャガチャ
誰かが慌てて鍵を開けるような音がする。
カペルは一人の人物を頭に浮かべ、玄関へと出向いた。
カペルが、玄関に到着するのを見計らっていたかのように、扉が開かれる。
扉の外から入って来たのは、カペルの予想通り、レイオットだった。
「おかえりなさい、レイオット。」
レイオットは、少々手荒に前髪をかきあげて、扉を閉める。
「ああ。ただいま、カペル。全く、えらい目にあったよ。」
そういいながら、レイオットは足早に居間へとはいる。
「やはり、雨に降られてしまいましたか。」
「これは、もう降られるなんてレベルじゃないがな。」
後ろから声をかけてくるカペルに、うんざりといった風体で答える。
レイオットは、来ていたコートを脱ぐと、そそくさと部屋を出て行こうとする。
「あ、レイオット。シモンズ監…」
「悪いなカペル。俺は風呂に入るから話しは後にしてくれ。」
カペルの言葉に覆い被さるようにレイオットが言う。そうとう、服が張り付くのが不快なようで、眉をしかめている。もう、レイオットの頭の中には、風呂に入る事しかないのだろう。
「でも、今シモンズ監督官が…」
最後の静止の言葉、いや、忠告もレイオットの扉を閉める音にかき消され、レイオットには届かなかった。
スタインバーグ邸の寝室や、トイレ、風呂場には鍵がついていない。
それは、主人がズボラなのと、住人が二人しかいないからである。この家には当然ながら、レイオットのほかには、カペルしかいない。
例え風呂に入る際に、カペルがいないのなら、警戒し、中に誰かいるか位気配でわかっただろう。
しかし、カペルは今、居間にいる。だからレイオットは油断していたのだ。
目的の場所に着いたレイオットは、何の躊躇も疑いもなく、扉を開ける。
そして、自らの目の前に展開されている出来事に、思わず凍り付いてしまった。
レイオットの目線の先には、裸体のネリンの姿があった。
反射的にというか、何と言うか、思わず上から下まで観察してしまう。
柔らかそうな足、細い腰、思っていたより大きい胸、少し赤く染まった白い肌、そして驚きに見開かれた瞳。
そこまで観察してやっと我に返る。
「あ…いや、その…」
しかし、動揺は増す一方のようだ。
その言葉で、ネリンも我に返り、とっさにタオルで体を包む。
「あ~シモンズ監督官…その、すまん。」
おろおろと言うレイオット。きっと本人も何を言っているのか分かっていないのだろう。
「そう思うのなら、早く出て行ってくださいよ!!」
ネリンの怒声にはじかれたように、レイオットは、慌てて後ろ手に扉を閉める。
「な、なんで!?」
レイオットは口元に手を当てながら、今さらながらに疑問を口にする。
当然だ。今日は週末でもなければ、何か約束していたわけでもない。
レイオットは、扉に背中をもたれさせると、ズルズルとへたり込む。
頭の中では、先程の光景が浮かぶ。本当に一瞬という短い時間だったが、状況判断の早いレイオットは、はっきりと記憶してしまった。
「マジかよ。」
思わず赤面してしまう。どうして、俺はここまで動揺しているのだろうか。
自分の頭の中にある、もう一人の冷静な自分が、自分自身に問い掛ける。別に、女の裸に免疫がないわけではない。
数年前までは、フィリシスという恋人がいたわけだし、レイオットも男だ。
一夜限りの女だって数人経験している。だから、余計に自分の行動が不可解でならない。
ここにジャックがいたら「女の裸くらいで赤くなるな!」とか言われそうだ。
すると、レイオットの背中から、ネリンの声が聞こえてきた。
「スタインバーグさん!見ましたね!」
「み、見てない!」
ネリンの怒気をはらんだ声に、思わず否定の言葉を口にする。
「絶対嘘です!見たでしょ!」
「いや、み、見てない…」
心なしか声が小さくなる。
「じゃあ、どうしてドモっているんですか。」
「いや、まぁそれはだな…」
扉越しの会話だと言うのに、相手の表情が見えない分、余計に怖くなる。普段から飄々としているレイオットの姿からは、想像もできないほどの慌てぶりだ。
「責任とってくださいよ!」
「責任って…」
とここまで言って、レイオットの頭の中に一つの言葉が点滅する。
「責任」=「結婚」
思わず、そんな自分を想像する。
~
朝の光が差し込む部屋で、自らが寝ていたベッドが、誰かが座ったことを告げるように、左に傾く。
「スタインバーグさん。朝ですよ、起きてください。」
瞳を開いた先にいるのは、朗らかに笑うネリンだった。レイオットは、ネリンの姿を再度確認するかのように、ネリンの腰に手を回す。
「ネリン。いつまで俺を「スタインバーグさん」ってよぶつもりだ?そういうネリンも、もうシモンズじゃなくて、スタインバーグだろ。」
少し意地悪気なレイオットの言葉。
「そうでした。何だか昔の癖が治らなくて。」
照れた笑いを浮かべながら、ネリンが恥ずかしそうに言う。
「じゃあ、レイオット。」
「ん?」
「朝ご飯にしますか?それとも私………」
~
ぶんぶんぶんぶん!
レイオットはそこまで考えて頭を振る。
自らの想像の恥ずかしさに、思わず卒倒しそうになってしまった。
気を取り直すために、一つ咳払いをしてから、レイオットは口を開いた。
「あ~シモンズ監督官。俺にどう責任を取れと?」
少しの間の後、ネリンとレイオットを隔てていた扉が、カチャリと開く。
そこには、レイオットの白いYシャツに、黒いズボンをはいたネリンが立っていた。やはり、レイオットの服は体に合わないらしく、袖や、すそを折っている。
顔は、風呂上りのせいか、怒りのせいか、羞恥のせいかわからないが、赤くなっていて、レイオットにはネリンの胸中がいまいち良く分からない。
やや上目遣いにレイオットを睨むと、ネリンはおもむろに腰に手を当てた。
「スタインバーグさんには、資格を取ってもらいます。それで、今回の事には目をつぶります。」
自信満々に言うネリンの態度に、思わずレイオットの肩の力が抜ける。
「それと、これとは話しが違うだろう。」
「いいえ、今日の出来事に関しての責任はきちんととって頂きます。当然じゃないですか。
私は、は…裸を見られたのですから。しかも無料で。それ位のつぐないは当然です。」
自分で言っていて興奮してきたのか、なぜか言葉に必要以上熱が入っている。
「じゃあ、金を払えばいいのか?」
思わずレイオットが突っ込む。
「そういう事を言っているわけではありません!」
ネリンは、自分の言っている矛盾に気づいていないようだ。
さすがのレイオットもこれには参ってしまった。不可抗力とはいえ、自分がやったことの罪(?)は変わらない。しかし、資格は取りたくない。かといって、ここで資格を取りたくないとごねても、頭に血が上っているネリンには逆効果だろう。
思わず思案顔になる。
ほとほと困り果てたレイオットを助けに来たかのようなタイミングで、カペルが静かに扉を開けてやってきた。どうやら、この騒ぎが気になったようだ。
「どうしたのですか?」
感情のこもらない声。
今までの口論は、冷や水をかけられたように鎮まる。
「いや、話せば長くなるんだが…」
レイオットは、頭を掻きながら答える。しかし、ここではたっとある事に気づく。
「なあ、カペル。俺が帰ってきたとき、シモンズ監督官がいた事は、もちろん知っていたよな?」
「当然です。シモンズ監督官に入浴をおすすめしたのは、私ですから。」
しごく当然という風にカペルが答える。
「あのなぁカペル。そういう事はもっと早く言ってくれれば、こんな事にはならなかったんだぞ。」
それはそれはダルそうに、レイオットがうなだれる。カペルの言葉に、心底脱力したようだ。
「しかし、私の記憶が正しければレイオットに伝えようと思い、話をしましたが、レイオットは全く聞かずに部屋を出て行きました。」
カペルに悪意はない。むしろ、カペルはこの事態を収めるべく、真実を正確に話そうとしている。
しかし、レイオットにとってカペルの心使いは、裏目に出てしまった。
カペルの、その言葉を聞き、ネリンの攻撃が再び始まった。
「ほら!やっぱり、スタインバーグさんのせいじゃないですか!」
「いや、まあ、おおむね俺が悪い事は認めるが、せめて情状酌量の余地は求めるぞ。」
「いいえ、認めません。今すぐに資格を取ってください。」
どうやら、ネリンは意地になってしまったようだ。レイオットは困りはて、カペルに助けをこう。
「おい、カペル。このお嬢さんをどうにかしてくれ。」
「私が何か言って、シモンズ監督官が大人しくなるとは思えませんが。」
「カペルちゃんに助けを求めるなんて、卑怯ですよ。」
とまあ、全く収集のつかない事態に発展しつつある。
なお、言い合い(というか、ネリンの一方的な責めというか)を続ける二人は、カペルの目から見てじゃれ合っているようにしか見えない。
それなりに緊迫した事態なのだろうが、どうも緊張感がない。かといって、いつまでもこの状態のまま、いるわけにもいかない。
「では、こうしてはいかがでしょうか。」
あの状況下において、唯一冷静に判断ができる人物であるカペルの提案。
それは、これから三ヶ月間ネリンがスタインバーグ邸に訪れた時は、毎回夕食無料、そして毎回家まで送迎するという条件が提案された。
ネリンも自分より年下のカペルの意見に、頭ごなしに反対する事もできずに、結局、この条件で手を打つ事になった。
ようやくネリンの服が乾き、レイオットはネリンを自宅まで送る。
時刻はすでに八時過ぎ。カペルの提案は今日から実行され、夕食をご馳走され、家まで送ってもらったネリンは、夕刻の怒りはどこへやら上機嫌だ。
「今日は送って頂いて、どうもありがとうございました。」
運転席に座っているレイオットに、窓越しに、律儀に挨拶をするネリン。
「シモンズ監督官。これは俺の償いなんだから、気にしていたらきりがないぞ。」
「でも、やっぱり何か悪い気がして。」
ネリンの真面目さは、どうやっても治す事はできないのだろう。送ってもらって当然なのに、思わずお礼の言葉を口にしてしまう。
これがネリンのいい所であり、欠点でもある。
そんなネリンが可笑しくて、思わずレイオットの口元がゆるむ。
「なら、俺もお礼を言わないとな。」
「お礼?」
ネリンが訝しげに問い返す。
いつもとは違う、少しいたずら小僧のような表情するレイオットに何故かドキッとする。
しかし、レイオットの言葉の意味は理解できない。
「ああ。ミス・シモンズのおかげで、いいものを見せてもらったからな。いい目の保養をさせてもらった。」
一瞬何のことか分からずに、考えを逡巡させるネリン。
そして、「いい目の保養」となった対象が、自分であるという事に気づき、顔を真っ赤にさせる。
「ス、スタインバーグさん!」
レイオットは、あまりにも予想通りのネリンの反応に、思わず吹き出してしまう。
「もう!スタインバーグさん、からかうのは止めてください!」
ネリンが、羞恥に顔を染めながら憤慨する。
「冗談だよ、冗談。」
レイオットは、手をパタパタ振りながら可笑しそうに言う。ネリンは「もう!」と何回も呟いていた。
「じゃあな、シモンズ監督官。俺はこれで帰るよ。
「あっ、はい、スタインバーグさん。お気をつけて。」
ネリンの言葉を聞き届けてから、レイオットは車にエンジンをかける。
「お休みシモンズ監督官。風邪を引かないようにな。」
「ええ。スタインバーグさんこそ。では、おやすみなさい。」
ネリンが朗らかに笑う。
そして、モールドキャリアが発進した。
帰りの車の中で、一人思いをはせる。どうしてあんなに自分は動揺してしまったのか。
そして、一つの事柄にたどりつく。
なるほど。ネリンの女という部分を目の当たりさせられたからだろう。
そうレイオットは一人で納得する。そして、今までネリンを女性としてはっきり認識していなかった事に気がつく。
ネリンが女性だという事は、わかっている。しかし、頭でわかっている事と、心が認識する事は違う。特にネリンは童顔のため、幼く思いがちだ。
しかし、ネリンの体つきは、顔に似合わずしっかり大人で、スタイルもいい方だと言えた。
自分の予想と違うものを目の当たりにすると、人間は動揺してしまうものだ。
今日の出来事は、レイオットの意識を大きく変化させる出来事となってしまった。
近いからこそ気づかない事。良くありがちな人間の過ち。それを、レイオットは冒してしまう所だったのかもしれない。
まだまだ、自分の気持をつかみ切れないようだが。
(思っていたより発育してたな。)
風呂場で目撃した時の事を思い出し、ふとそんなことを考えてしまう。そして、思わず自分につっこむ。
「欲求不満か、俺は…」
苦悩に満ちたその言葉を聞く者は誰もいない。
再びしとしとと降り始めた雨以外は。
background-sozai:
Prism
■■■■Post Script■■■■
初のゲスト様小説がストジャでございますよ! ひゃっほう!!
ミサモンタさんありがとうございます。
作中の新婚ネタなど勝手に続きを捏造しそうになる有様でした。
ベッドサイドに腰掛ける若奥様ネリンと、きっと上半身は裸で寝てるレイオット・・・。
いかん! 未だ18禁には手を出しておらんのに!! (誰か殴って正気に返せこの女・・・)