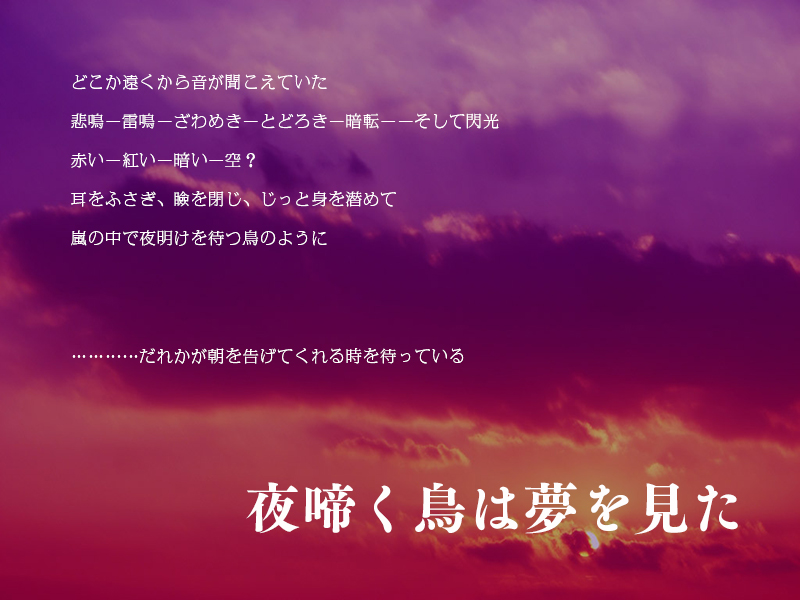
第1章 目的のない旅は彼を堕落させた
黄金に輝く砂の畝には、風が描いた風紋だけが延々と広がっていた。
ここ三日ばかり同じ景色ばかり見続けて、いい加減ヴァルガーヴは飽きが来ている。
(いつになったら終わるのかね)
長い逃亡生活の時には周囲を見渡す余裕などなかったので気にもならなかったが、こうも変化のない世界を旅していると頭の中がボケてきそうだ。
ひまつぶしらしいひまつぶしもないから、『こんなこと』をしている。
「次、貴方の番ですよ」
声を掛けられて彼は、真正面の彼女に向き直った。
掌にかかる赤い糸。
「あっ、ああ……」
しばし黙考した後、その間に指を潜り込ませて今度は彼の掌に、その赤い糸が納まる。
「んーと……」
彼女が小首を傾げて、またその赤い糸の間に指を絡ませるのを見て、また彼は砂丘の方に目をやった。
「しっかし、あれだな……」
「えっと……ここがこうで……、なんですか?」
まだてこずっているらしい彼女は上の空で返事を返してきた。
「なーーーんにもないところだよな、ここは。次の街までどのくらいだって言ってたかな、あのばーさん」
5日前まで滞在していた砂漠の中の小さな村の老婆から貰った地図はいい加減なもので、だいたいの方向と相対的な距離くらいしか分からない。
「さあ……一週間くらいって言ってませんでした?……あ、ここはこうね」
「けど出立前には4日もあれば着くとか言ってなかったか? だいぶボケてたんだな、あのばーさん」
「かもしれませんねぇ……、あ、できました」
言われて振り返った彼女の指には彼が見たこともないような型が出来上がっていた。
「おい、ちょっとそれ、なんだ?」
「は?『パイナップル』……のつもりなんですけど、そう見えません?」
「俺にゃ足が六本ある牛かなんかに見えるけどよ……まぁいいか。そろそろ行こうぜ。こんなとこでいつまでもあやとりしててもしょーがねーし」
「そーですね……でも……自信作だったんですけど……牛ですか……」
ちょっと悲しそうな彼女を横目にシートだの空になった弁当箱だのを片づける。
空を見上げて方向を確認するとまた歩き出す。
赤い糸をもつれないように縛ってポケットに入れると彼女もすぐ後ろをついてきた。
急ぐ旅ではないが、せめて今日中には人家のある場所に着きたい。退屈もここに極まってしまった感のする、見た目は十代後半のナイスガイ、実は当年とって200といくつのあやとり上手な古代竜であった。
ミルガズィアに別れを告げ、カタートを後にしてはや3カ月。
落ち着き先らしい落ち着き先も見つからぬまま、彼らは気まぐれに任せた旅を続けていた。
元の大陸に戻る気もしなかったので、とりあえず逆の方向に進んでみようということで、偶然にもリナ達が以前旅していたのと逆のルートを辿っている。
幸いなことに不毛の砂漠はそれから2日後に抜けられた。
砂漠越えが終われば難所らしい難所もなく、むしろそこから先は彼らが住んでいた大陸よりも温暖で緑も多く、暮らし易そうだった。
もっとも彼ら竜族は体温の調節やら栄養物の摂取やらの大抵の生命活動は魔力でできてしまうので、寒いも暑いも関係ないのだが。
彼らがいちばん苦労したのは、『いかに人間らしく見せるか』というその一点につきた。リナ達と旅してきたフィリアがいちばん人間の生活に慣れてはいたが、それでも時折人間のものの考え方にはとまどうことがあったし、風土ごとにかわる習慣、社会常識といった範疇になるとボロがでそうになることがしばしばだった。
ヴァルガーヴにいたっては……言うまでもない。古代竜自体が種族としてはあまり群れを作らない種族で、協調性だの、団体意識だのといったもの自体が希薄なのだから、人付き合いがいいとはお世辞にも言えなかった。
「おいおい、ちょおっと待ちな!」
「かわいいねーちゃん、連れてんじゃねーか。オレ達も混ぜてくれよ」
森の中でわらわらと湧いて出た一団に、ヴァルガーヴは面白くもなさそうな顔でちらりと視線を送り、背後のフィリアを振り返った。
こちらも顔をしかめてはいるものの、怯えている様子は微塵もない。
「一つ訊きたいんだがな」
リーダー格におぼしきスキンヘッドにヴァルガーヴがうんざりしたような声を掛けた。
「お、おう。なんでぇ」
いつもと勝手の違う態度に戸惑い気味の返事が返ってくる。
「お前らってのは、アレか? 森だの関所だのごとに必ず一群れは棲息すべしって決まりでもあんのか? 人間ってぇのは商売ごとに『くみあい』とかいうのを作ってなぁなぁの折り合いつけてるらしいが、お前らみたいな暴力と品性のなさだけがウリの商売でもそーいうのがあるわけか?」
彼が半ば本気で訊いているらしいということを察してスキンヘッドはちょっと眉をしかめて気味悪そうな視線を向けてきた。
「な、なんなんだ……ミョーなヤツだな……」
「おい、お前、生意気だぞ! オレ達をなんだと思ってやがる!」
傍らのナンバーツーとおぼしき男が乱されたペースを取り戻そうと大声を上げてくる。
「お前ら自分の立場ってもんがわかってんのか? オレたちゃ盗賊だぞ。とーぞく! しかも泣く子も黙る盗賊団「峠の狼」とは、オレ達のことだ!」
「とーげのおーかみ、ねぇ…」
「あら、少しはましなセンスだと思いますわ。この間なんて「ウェディング・テキスト」なんてヘンな盗賊団もいたじゃないですか。全員がウェディング・ドレス着てて、奪ったお宝は性転換の手術代に回すっていってた女装趣味の盗賊さんたち」
「あんな変態が世にいるとは思いもよらなかったな」
「やかましいっ! そんな外道どもといっしょにすんじゃねぇっ! オレ達は先祖代々由緒正しく続いてきた立派な正当派の盗賊だっ!」
「へぇ、こういう仕事にも正当とか邪道とかあるんだな」
本気で感心するヴァルガーヴ。けれどなにせ態度は完全に馬鹿にしきっているので相手には伝わらなかったようだ。
「お前ら、襲われてるって自覚があんのか?! 普通ならもうちょっと怯えるとか命乞いするとかそーいうことしてみようとか思うんじゃねーのか? オレは思うぞ、ふつう!」
それはあんまり威張れたことじゃないような気がするとヴァルガーヴは思ったが、地団駄をふんで主張するスキンヘッドがあんまり気の毒なので言わずにおいた。
「わかった、わかった。なるほど普通なら怯えたり、命乞いしたりするんだな?」
「ちょっとヴァルガーヴ」
「いいじゃねーか。ヒマなんだしよ。つきあってやっても」
そう。実際ヒマなのだ。このあたり一帯はろくな観光名所もないし、名物料理とか効力のある温泉とかナゾの幽霊屋敷とかいう呼び物があるわけでもない。小さな街が点在するだけでそれもあんまり裕福ではないらしく、街から街へ向かう間だけで必ずといっていいほど野党だの盗賊団だのといった連中が現れる。ひまつぶしといったら彼らを相手に遊ぶことくらい。それもまともな戦闘となると力の差がありすぎて、軽い運動くらいにしかならないし。
たまには遊び方を変えてみるのもいいだろう。
「それで? ふつうは……どうするんだって?」
「お、おう。つまり普通はだな」
「ふんふん」
「えーとまず、こう……怯えたように後じさってだな」
思わず身振りでしめすスキンヘッドに、ヴァルガーヴはふんふんともう一度うなずいてみせる。
「それで……こう……『助けてくれぇ!』とか言うんだよ!」
「なるほど。なかなか上手いもんだ」
本気で感心するヴァルガーヴに、呆れたフィリアは既に離れた場所でどこから取り出したやらティーセットを広げている。
「いや、たいしたもんだ。今の怯えっぷりといい情けない声といい、あんた役者やったほうが向いてるぜ」
「いゃあ、それほどでも」
ひとしきり「正しい盗賊からの襲われ方」の実践講義は続き、もはや本来の目的はすっかり忘れられ、ほがらかに笑い合うヴァルガーヴと盗賊達。
「それじゃ、頑張ってな」
「いやいや、あんたらも道中気をつけてな」
あんまり仲良くなってもらいたくない連中ではあるが、まあ暴力による解決というのも問題があるし、よしとしよう。
いつまでも手を振っている盗賊達に陽気に手を振り返すヴァルガーヴを横目に、フィリアは軽い溜息をついた。
「おいおい、ちょおっと待ちな!」
「かわいいねーちゃん、連れてんじゃねーか。オレ達も混ぜてくれよ」
またしても道の真ん中に立ちはだかる盗賊団たちに、ヴァルガーヴとフィリアは目をぱちくりさせる。もしかしてとよくよく見てみたが、あのときの盗賊の首領はスキンヘッドだったのに比べこちらは熊とも見まがうヒゲ面である。
「なんか前にも似たようなことがなかったか?」
「前にあった人たちと登場の仕方がおんなじですわね」
「ひょっとしてマニュアルでもあんのかね?」
「……なんの話をしてやがる?」
一瞬とまどう盗賊達。しかし、こちらは前ほどのせられやすくはなかったようで、すぐに気を取り直したように大声を張り上げた。
「まぁいい! おい、命がおしけりゃそのねーちゃんと有り金全部を置いていって貰おうか!」
「…………」
「おぅどうしたい兄ちゃん。怖くて声も出ないのかい?」
「…………いや、考えたんだがな」
「おう」
「一つ相談だが、こいつ置いてくから金はナシってことで手を打たねぇか?」
「ヴァルガぁーヴっ!!!」
モーニングスターの直撃をぎりぎりのところでヴァルガーヴは避けた。かわりに耳を近づけていたヒゲ面の方がどつき倒され、地面に転がる。
華奢な美人が物騒なものを軽々と振り回すのをみて、おもわず盗賊達が後ずさる。
「どーいう意味です、今のはっっ!!」
「いや待て、落ち着け、フィリア」
ヴァルガーヴはちゃっかりといつの間にか巨木の枝の上に非難している。
「ごまかさないでください!! ちゃんと聞こえましたからね! おりてらっしゃい、さもないと……」
ぶん、と音速を超える速さでモーニングスターが翻る。
めきめきと音を立てて、ヴァルガーヴの腰掛けていた巨木が倒された。
そのとばっちりで盗賊たちのうちの何人かが打ち倒されたが、とうのフィリアはそんなことおかまいなしである。
「待ちなさぁいっ! 逃がしませんからね!」
怒り狂ったフィリアの攻撃の余波で、いつの間にやら盗賊団たちは壊滅していた。気の毒としかいいようがないが、世の中にはこんな天災のような人間(?)は確実に存在しているのである。
「うう……まさか、あんたたちは……あの……」
「どらまたリナ……」
倒れ伏す盗賊達は世にとどろく最も悪質な天災の名を口にした。
なんとかフィリアの機嫌が直った後(どうやって直したかは、ないしょ)知った名が耳に入って、ヴァルガーヴとフィリアは立ち去りかけた足を止めた。
「どらまた……?」
ヴァルガーヴの不思議そうな問いに、別の盗賊が息絶え絶えに答える。
「ど……」
「ど……?」
「ドラゴンもまたいで通る……」
「オレはあんなもの、またがん」
即座に、きっぱりとヴァルガーヴは宣言した。ああいうのはまたぐよりも、かかとで二、三度ぐりぐりと踏みにじった後、尻尾で叩いておくに限る。
「わたし、ひょっとしたらまたいじゃったかも……」
フィリアが過去の旅を思い出しながらなぜか不安そうに言った。
「ヴァルガーヴ、お金がありません」
唐突に口にされた一言に、ヴァルガーヴは目をぱちくりさせて(この男にしては珍しいことだ)背後で口を一文字に結んだフィリアを振り返った。
「ない、って言われたって……」
日も暮れかけた一本道。ようやく森を抜けたその先にわりと大きな街を見つけて、ほっと一息ついたところだった。
今さらそんなことを言われても、またしても野宿、というのではあんまり寂しすぎる。竜体をとっている時ならまだしも、今は目立たないようにヒトガタで行動しているの身だ。
「しょーがねぇなぁ……ならまたアレ、作ろうか?」
「アレはダメです。前にどんな騒動になったか覚えているでしょう?」
そうだった。
彼自身、知らなかったとは言え、まさかあんなものにあんな値がつこうとは想像すらしていなかったのだ。
持ち込んだ宝石商を皮切りにたまたま買い付けにきていたどこやらの王族の使いだの、ひょっこり窓から覗いていた盗賊の下見役だのに追いかけ回されて、さんざ逃げ回ったあげく、キレかかった彼は街一つあやうく壊滅させるところだったのだ。
そのアレ、とはすなわち、『ドラゴン・ブラッド』のことである。
『竜の血』という意味の、鮮やかな真紅の宝石は、文字通り、竜の血から作られる貴石である。ただその作り方そのものが竜族自身から失われてしまっているため、今となっては知っている者(竜)はほとんどいない。たまに古い遺跡から掘り出されたりすることがあるが、小粒の一つで三代先まで遊んで暮らせるくらいの金が手に入る希少価値の一品である。
たまたまヴァルガーヴがその作り方を知っていたため、自分の血でちょっとした親指大のものを作ったところ、持ち込んだ宝石商が手にしたまま泡を吹いたのを皮切りに、横からぜひとも譲ってくれと土下座する貴族まで現れて、あれよあれよという間に高値がつき、どこで手に入れたとつめよる人間達に追いかけ回されて、結局さっさと逃げ出すしかなかったのだ。
ここより小さな田舎町ですらあのありさまなのだから、こんな人間の多い街で、しかも長く人里離れていた身で、あんな騒動に巻き込まれたくはない。
「でもなぁ……金がなけりゃ宿屋にも泊まれないだろ?」
ミルガズィアからもらった路銀も底をつき、最近では襲ってきた盗賊どもを逆にカモネギにしていたのだが、そのカモすら出てこないような田舎を旅してきたせいで、手持ちの金は全くない。
「だから、働きましょう」
「働くぅ!?」
思わず声が裏返るヴァルガーヴ。彼女の意見は至極まっとうであるが、彼は生まれてこのかた職業らしきものを持ったことは全くない。
履歴書の欄に「職業:魔族」と書いて雇ってくれるところがあるだろうか。
一瞬真面目にそんなことを考えて、ヴァルガーヴはあまりのばかばかしさに絶句してしまった。
「んな面倒な……」
「しかたないでしょう。いつまでもぶらぶらしているのもよくありません。たまには定職について地道に、真面目に、お金を稼ぐ、という経験も貴方には必要です。さぁ!そうと決まれば、行きますよ!」
結局、それが言いたかったのか。
ヴァルガーヴはいささかげんなりした思いで急にはりきりだしたフィリアの後を肩を落とし気味に歩き出した。
どうやらこの巫女は、自分を真人間(真竜?)にするのが己の使命だと本気で考えているらしい。
(どうりで最近口うるせーと思った)
地道。真面目。定職。
これほど自分に似合わない言葉があるだろうか。
まっとうな人生を歩いてきたフィリアの感覚にはときおりついていけないものを感じるヴァルガーヴ。
のんびりのどかにのびた一本道をフィリアは元気に歩いていく。
いやなら離れてしまえばいいのだが、何故か彼女から逃げることができない。
肩を落として、彼は彼女の後ろをついていく。
日向の世界はまだ……ちょっとだけ遠い。
第2章 彼女はことさらに彼が悪だと考えているわけではない
ヴェゼンディ・シティ。
石造りの堅固な門の入り口にはそうかかれてあった。
「なかなか大きな街だよな」
これまで彼らが訪れてきた人の住む街の中ではもしかしたらいちばんかもしれなかった。だが聞いた話によればセイルーンとかサイラーグなどはもっと大きいらしく、ここヴェゼンディは人間の街の中ではまぁ中堅程度、ということになるらしい。
街に入った時には夜になっていたので、まず料金後払いの宿を見つけて腰を落ち着けようということになった。幸い食事代くらいの残りはある。仕事は明日から見つければいい。
ということで彼らはすっかり人通りの絶えた夜の街を歩いて宿屋の看板を捜していた。
だがどうにも見当を間違えたらしい。久方ぶりに人里に出てきたせいか、はたまた彼らがこういった「都市」の作りに馴染みがないせいか、気付いたときには宿屋どころか人の住んでいる気配すらなさそうな路地に迷い込んでしまっていた。
「これは引き返すよりないな」
「そうですね……」
フィリアの声にはさすがに疲労の色が見える。一日歩きづめなのだから無理もない。
叫び声らしきものが聞こえたのはその直後だった。
「なんだ?」
そして、闇に溶ける灰色の影。
人間の肉眼では見いだせない、その失踪する人影をヴァルガーヴの目ははっきりと捕らえていた。瞬間、その人影もこちらに気付いたようだった。
「…………?」
「ヴァルガーヴ!」
フィリアの叫び声で、ヴァルガーヴは一瞬で我に返り、飛んできたナイフを素手でたたき落とした。
(ちっ……このオレとしたことが……)
背後でほっと息をつくフィリアにちらりと見遣り、ヴァルガーヴは己の迂闊さを反省する。
(平和ボケして、なまったのか?)
以前なら、たとえ一瞬でも油断するようなことはなかった。
しかし一旦、己を取り戻してしまえば、二撃目の蹴りは目を閉じていてもかわせた。
それで少し安堵する。まだ勘は鈍っていない。
三撃目、相手の拳が飛んでくる前に、ヴァルガーヴは己の力を解放した。
「はあぁっ!!」
呪文一つ必要ない、緑の光弾が正体の知れぬ襲撃者の足下を襲う。
狙い違わず、はじき飛ばした--いや。
(今のは自分から飛んだのか)
ただの人間にしてはやる。
だが、体勢は大きく崩れている。
(誉めてやるよ、だがな!)
躊躇なく、二弾目を打ち放した。先ほどよりも早く。
(殺しはしねぇよ……めんどくせぇからな)
手加減してはいても、魔族は魔族。勝負はあっけなくついた。
今度こそ立ち上がれなくなった相手に、それでもヴァルガーヴは油断せず近づきはしなかった。
「キサマ……ナニモノダ……」
くぐもった声が顔を覆うマスクから漏れた。
「それはこっちの台詞だ」
「…………」
「なんでオレを襲う?」
「…………ミラレタカラダ……ダガ…………オモシロイ……」
「なに?」
それに返答はなかった。ふらつきながらもたちあがった襲撃者は、現れた時と同じように闇に溶けた。
今度こそ肉眼では見えない闇……それが魔術によって作り出された闇だと気付くのに、少しかかった。そして反省する。
(やはり、なまってるな)
「ヴァルガーヴ……」
溜息をついたとき、ためらいがちな声が背後からかかる。
(そういや、忘れてた)
「大丈夫か? お嬢さん」
「ええ……何だったんですが? あの人」
「オレに聞くなよ。こっちが知りてぇくらいだ」
「でも、どうみても貴方の知り合いっぽいですよ?」
「どうみたらオレの知り合いなんだよ」
「うさんくさそう」
喧嘩売ってんのか、このアマ……。
わずかに肩が震えたが必死で堪えた。
「で、誰なんですか?」
「知らねぇっつってんだろ!」
「でも貴方の知り合いなんでしょう?」
「違うというとろーが!」
「昔、部下にした後で捨てちゃった人とか」
「人間の部下を持った覚えはねぇ!」
「人間っぽくなかったですよ? ちょっと目がアブなそうだったし」
「目がアブないとオレの知り合いかよ」
「で、ホントは誰なんですか?」
「…………」
フィリアの誰なんですか攻撃はその後宿屋に着くまで続いた。
一夜あけた粗末な宿屋。
朝食だけはまともでヴァルガーヴは少し安心した。
後は路銀を稼ぐアテを見つけるだけだ。
とはいえ、まともに働いたことのない彼にできる仕事といえば、傭兵かボディガード。
(やっぱりそのへんか)
一応、フィリアと職業斡旋所なるものに顔を出してみることにした。
「ヴァルガーヴさんね……どんな仕事がいいのかね?」
初老の太った血色のよさそうなおっさんが、眼鏡を上げつつでっかい大福帳をめくった。
「どんなって言われてもな……これまで働いたことなんかねぇし」
「働いたことがない? いいとこの坊ちゃんだったのかい?」
オレのどこ見てそんな台詞が出て来るんだとヴァルガーヴは思ったが口には出さずにおいた。
「あの、でもこの人強いんです。ボディガードとか、力仕事とか向いてると思うんですけど」
フィリアが横から売り込みをかける。
「ふぅむ。なら石切場の仕事とかどうかね。100kgくらいの石を一日300個も運べば結構いい金になるよ」
具体的な数字を上げられてヴァルガーヴはちょっと顔をしかめた。
「いやかね? じゃあ魚市場で5kgのマグロを上げる仕事なんかどうだね? 一度に3匹ぐらい運ばなきゃならないが、こっちは30匹程度で済むよ」
「…………」
「あと、牧童はどうだい? 1500kgの牛の群れを20匹ほど追い立てる仕事なんだが、こっちは50kg程度の犬が2匹ほどサポートにつくし」
「…………」
だからなぜ必ず重量と数量がついてくる……?
このおっさん、目方(カウント)フリークか?
それともこの街では全て目方で給金が決まるのか。
呆れたヴァルガーヴが声も出さずにいると、斡旋係のおっさんはしぶしぶといった風に切り出した。
「いやなのかね? しょうがないなぁ……じゃあ……あんまり気がすすまないんだが、ボディガードの口があるよ」
あるんなら最初っから言え。
と、思ったがやはり言わずにおいた。
最近人間が出来てきたなぁ、オレって。
これも口には出さなかった。
(大人になる度に言えない言葉が増えていく)
くだらない会話から深遠な真実を導き出しそうになって、ヴァルガーヴは少し人生を見直す気になった。
第3章 夜中に執事をたたき起こすとろくな扱いをしてもらえない
この街でも有数の金持ちだというその男はどうみても金持ちらしく見えなかった。
若すぎる。
それが二人の感じた第一印象だった。
お人好しそうだ。
それがヴァルガーヴの感じた第二印象で、実際その男は拍子抜けするほど簡単にこちらを信用した。
「命を狙われている」
と、その男は言った。
だから、護ってほしい、と。
いつまで、とは言わなかった。狙っている相手をしとめてほしい、とも言わなかった。
提示された金額はかなりの額で、けれど後払いという条件がついた。
一文無しなのだと言うと、住み込みでやってもらえれば生活費はもつと言う。
私的な物を買ったときはツケにしておけば後から報酬から引いておく、とも。
後払いであることを除けば、有利すぎるほど有利な条件に二人は多少の胡散臭さを感じながらもおとなしく雇われてみることにした。
「……それで、いつまで護衛をすれば宜しいんですか?」
フィリアの至極当然な質問に、男は困ったような笑みを浮かべて答えた。
「そちらが辞めたいとおっしゃる時まで、です」
「……? 辞めたい?」
「実はこれまでにも9人ほど護衛を雇っているんです」
「9人?」
ヴァルガーヴの眉があがる。
「……けれど全員、もういません」
「辞めたんですか?」
「いえ……」
一瞬口ごもった後、男は続けた。
「斡旋所で聞きませんでしたか? ……聞いていないのでしょうね、やっぱり」
「…………?」
まだ納得のいかなそうな顔の二人に、苦笑して答える。
「全員、死にました」
「!」
「辞めたいとおっしゃる時まで、という意味が分かっていただけましたか?」
こちらに有利すぎる条件の意味もわかった。
あの目方フリークのおっさんが「気が進まない」と言った理由もわかった。
それと同時に後払いにしておけば結局支払いをせずに済むのだという計算が働いているらしいことも理解して、ヴァルガーヴは少し目の前の男を見直す気になった。
フィリアは明らかに不快気である。何か言いかけるのをヴァルガーヴは目で制して、目の前の男にうなずいてみせた。
「わかった。オレはそれで構わない。ただ一つだけ聞いておきたいことがある」
「何ですか?」
「命を狙われる理由だ」
「それは分かりません」
返事は即答だったので、少し嘘臭く感じた。
「ただ僕も聖人君子ではありませんから。金持ちというのはそれだけで狙われる対象になります。現に僕の父親もそれで亡くなりましたし」
「……狙ってるヤツに心当たりは?」
「それも分かりません。しかしその手のプロであることは分かっています。今までの護衛役を全てしとめたことから考えてかなりの腕であることも」
「……」
「どうされます?」
こちらを少し馬鹿にしたような言い方が癪にさわった。
「こっちが辞めたい時に辞めて構わないんだな?」
「はい」
「……わかった」
どうとでもとれる返答をしてヴァルガーヴはフィリアを振り返った。
「お前はどうする?」
「え? 私は……」
どう、と言われてフィリアは目をぱちぱちさせた。
今まで別行動を取ったことなどなかったので離れるのも躊躇がある。
返答に窮するフィリアに雇い主の方が救いの声をかけた。
「ああ、もちろん、お二人一緒に住み込んで頂いてかまいませんよ」
「いいのかい?」
「ええ、今、部屋を用意させます」
「そうしてもらえると助かる」
フィリアもほっとして頭を下げた。
「すぐに部屋に案内させましょうか?」
「オレは後でいい。館の周りをまわってくる。一通り確認しておきたいんでな」
「慣れてるんですね」
感心したように言われて、ヴァルガーヴは苦笑する。自分の落ち着く場所をよく点検しておくことは竜族に限らず野性に生きるものの習性のようなものだ。
他人の作った囲いの中で平気で生きていけるのは人間くらいだろう。
それがよいことなのか悪いことなのかは別として。
「それでは……そちらの方だけ先に執事に案内させます」
一瞬のとまどいに、ヴァルガーヴはまだ、自分たちが名乗っていないことに気がついた。彼らが迂闊に素性を知られたくなかったせいもあるが、「護衛の仕事があると聞いてきた」と言っただけで話しがとんとん拍子に進んだのでお互い名乗り合ってもいなかった。
「オレはヴァルガーヴだ」
「わたくしはフィリアと申します」
優雅な礼に、初めて目の前の男がフィリアをまともに見、少し赤くなったのをヴァルガーヴは見逃さなかった。
「よろしく……僕は、アべル。アベル・ランザードです」
(気に入らねぇ)
庭に出て壁づたいに進入路と退路を確認しながら、ヴァルガーヴは少し苛立っていた。
何が気に入らない、という明確な理由があるわけではない。
素性を確かめもせずに、こちらを雇ったこと。
報酬が後払いであること。
護衛が全員死んでいる事実。
狙われている理由も狙っている相手もわからないと言い張る雇い主。
どこか釈然としなかった。
アベル・ランザードは若すぎて、やり手の商人には到底見えない。ということは恨みを買うほど儲けているわけがない。偏見かもしれなかったが、彼がいわゆる「ごうつくばり」でないことには確信があった。護衛一人雇うのに金を惜しんでいないのがその証拠だ。
(だが、命を狙われているにしては緊張感がかけている)
ようやくヴァルガーヴはもやもやとした不信感の理由を見つけた。
そう、アベル・ランザードは怖がってなどいない。
真剣ではある。命を狙われているという自覚もある。事態を深刻に受け止めてもいる。少なくとも護衛を頼みたいと言ったときの彼の顔には明らかな苦悩があった。
それでも、ヴァルガーヴは確信していた。
アベル・ランザードは護衛を9人殺されても、怖がってなどいない。
それどころかフィリアを見て顔を赤らめる余裕さえあるらしい。
(気に、入らねぇ)
先ほどの彼の年相応の顔を思い出してヴァルガーヴは足下の小石を思い切り蹴飛ばした。
広い邸内をあちこち調べ回っているうちに、夕闇が迫る時刻になっていた。
今は日が短い時期なので余計に夜が早い。
夜目が聞くので調べ物にたいして支障はなかったが、ヴァルガーヴは一段落つけることにした。
(腹、減ったかな)
邸内に戻って執事とかいうのに食事の在処を尋ねると、台所に通された。
(要は、使用人と同じ扱いってワケか)
別にひがむ気はなかった。客でもなんでもない単なる護衛なのだからその程度の扱いで当然だろう。
(そういや……)
「フィリア……オレの連れの方の食事はどうなってる? もう済ませてたか?」
手近で食器を洗っているメイドに訊ねると、意外な返事が返ってきた。
「ええ、もう済ませてらっしゃいますよ。アベル様とご一緒に」
「なに?」
「久方ぶりのお客様でコックも腕を振るえたって喜んでましたよ」
「…………」
やっぱり気に入らない、とヴァルガーヴは目の前の使用人と同じ献立を睨み付けた。
どうにも腹の虫が治まらないのでそうそうに寝ることにした。
護衛役としては失格だろうが、あの呑気な男を護ってやる気は一気に失せてしまった。あんな毒にも薬にもならなそうな男、死んだところで誰に実害が出るわけじゃないだろう。
どんなに気配を絶とうと、人間ごときの襲撃を察知できないわけがないという自信もあった。
案内された部屋はそこそこに広く、ベッドも天蓋付でかなり大きい。
灯りもつけずに、ヴァルガーヴは服を脱ぎ捨ててむしゃくしゃしたまま布団にもぐりこんだ。
と、同時になにか柔らかいものにぶつかって、顔をしかめる。
「きゃあっ!」
その何かが悲鳴を上げた。すかさず上にかけていたシーツが引かれる。
「……?」
まさか。
ヴァルガーヴは飛び起きてベッドサイドのランプに火をつける。
ゆらゆらと揺れる灯りの向こうに、怯えたようにシーツにくるまったフィリアの姿があった。
「------!!!!」
今、自分がどんな顔をしているのか、なぜこんな状況になっているのか。
なんであんたがここにいるんだ。
当然の質問すらでてこない。ヴァルガーヴの頭の中は巨大な空白で埋め尽くされていた。
茫然自失の一瞬の後、ヴァルガーヴは上着もかけずに半裸のまま部屋から転がり出て、人を呼んだ。
まだ起きていた使用人との一悶着の後、ようやく眠りばなを起こされたばかりらしい執事がやってきた。
「はあ? 部屋が違う?」
「だから、オレの部屋にあいつがいるんだよ! ってことはオレかあいつかどっちかの部屋が間違ってるってことだろうが!」
「はあ、それは当然でしょうな」
「そうだよ! だからオレの部屋……」
パニック状態のヴァルガーヴの言葉を適当に聞き流した執事は至極当然、といった顔でいってのけた。
「はあ。ですから同じ部屋です」
「だからそれはあいつがいるって……は?」
「はあ。同じ部屋ですから」
お星さまが一つヴァルガーヴの頭の上に落ちてきた。
「なんだって?」
「ツイン・ルームですから」
ツイン……ツインってことは……。
「スィート・ルームと申し上げた方がおわかりになりますか?」
即ち新婚さん用である。
新婚さん用。
ヴァルガーヴの頭の上に、今度は隕石が落下した。
「だっ……、誰と誰がスィートだ! 別にしろ! いまっすぐっっっ、別にしろっ!!!」
「はあ……するとまだ?」
執事が意外そうな顔で聞きようによってはとんでもない台詞を吐いた。
「何が『まだ』だ! 妙な誤解するんじゃねぇっ!」
「なるほど」
ヴァルガーヴが逆上すればするほど執事は冷静だった。冷静どころか、面白がってさえいるらしく、二人の会話は果てしなくずれていく。
「オレとあいつとはなんでもねぇ! ただの連れだ! わかったら今すぐ部屋、用意しろ!」
「まぁまぁ、よい機会だと思えば」
「なんの機会だ、なんの!!」
「意外に奥手ですな」
「人の話聞いてんのか! てめぇは……!」
「照れ屋さん」
初老の紳士然とした男のとんでもない評価に、ヴァルガーヴの顎がかくん、と落ちた。
「若いというのは宜しいですなぁ。ほっほっほっ」
余裕の笑いをかまして執事は去っていく。
これまであったこともない人種であった。未知との遭遇であった。
世間の荒波は決して真正面から、迫害とか貧困とか戦争とかのわかりやすい形でやってくるものばかりではない。それは、初老の、酸いも甘いも噛み分けた50歳前後の人間の、善意の解釈という形でもって足下をすくいにきたりするのだ。
笑い声が廊下の曲がり角に消えて行くまで、ヴァルガーヴは激しいカウンターショックから立ち直れずにいた。
「……ヴァルガーヴ……」
背後から躊躇いがちな声がかけられる。
置かれた状況から言えば本当に困ってしかるべきは彼女の方なのだが、その声には困惑よりも、気の毒そうな響きが強かった。
「何も……何も言うな……」
肩を落とし、ようやくそれだけ口にした。
まだベッドの上でシーツをかぷっているフィリアを気まずそうにちらりと振り返って、ヴァルガーヴは激しい疲労の溜息をつく。
「と、とりあえず今日のところは我慢するしかねぇだろう……明日アベルに言って替えてもらうから心配すんな。オレはこっちのソファを使うから」
「……すみません」
「あんたのせいじゃねぇよ」
できるだけぶっきらぼうに言って、ヴァルガーヴは野宿で使っていた毛布を取り出し、ソファに横になった。
「おやすみなさい」
「ああ」
フィリアとのこういった挨拶に彼はまだ慣れないでいる。
朝も夜も、魔族として生活していたときには関係なかったからだ。
(オレは人間じゃねぇ)
人間に合わせて生きる意味があるとは思えなかった。
わけのわからん執事とのやりとりで気分がいささかささくれ立っている。
(馬鹿馬鹿しい……なんでオレはこんなとこにいるんだ……)
いっそただの魔族か、竜に戻ってしまえばいい。
別に一人でも困らない。どうせ彼の血は魔族としても竜族としても一代限りだ。
「…………あの……ヴァルガーヴ」
鬱々と眠れずにいる彼に躊躇いがちな声がかかった。
どうやらフィリアも眠れずにいるらしい。
まあ、若い男がすぐそばにいて安心して眠れというのも無理な話かもしれない。
野宿をしていた時は、仕方なしだという感覚が強かったし、ちゃんとした宿を取るときは必ず別の部屋にしていたから、一つ屋根の下の同じ部屋で眠るとなるとかなり調子が狂う。
「なんだ?」
フィリアには背を向けたまま、ヴァルガーヴは答えた。
「あの……よければ半分、開けますからここに来ませんか?」
「ここにって……同じベッドにってことか?」
意外な言葉にヴァルガーヴは振り返って彼女を見た。
「はい。あの……信じてますから」
何を、とは言わなかったが、意味は十分に通じた。
「いいのかよ」
「はい」
彼女の返事に嘘や躊躇いはなかった。
ヴァルガーヴは彼女の申し出を受けるべきかどうかしばし考えた。
「……いい。やっぱやめとくわ」
「どうして?」
「雄だからな」
からかうような口調で言った言葉に、フィリアが真っ赤になったのが分かった。
(ま、しかたないな……)
どうせ今夜一晩の辛抱だ。少なくともこの部屋は居心地はよい。
(金持ってるヤツの家だけはあるよな)
たとえソファでとる睡眠でも。
安らかな溜息と共に、ヴァルガーヴは眠りに落ちていった。
その夜、襲撃はなかった。
第4章 噂話は3割の誇張と7割近くの願望と1割以下の真実で成り立っている
次の朝、朝食の席でアベルに昨晩の事情を話すと、彼は目をぱちくりさせ、ついで破顔した。
「それは申し訳ありませんでした。てっきりご夫婦だと思ったものですから」
すぐに部屋を別にさせます、という彼の笑顔に悪意はない。
ないのだが、しかし。
(今こいつ、安心しやがったな)
つまらない邪推かもしれないがアベル・ランザードという男の何もかもが、ヴァルガーヴには気に障る。
「お願いします……それと、今まで泊まっていた宿から荷物を取ってきたいのですけど、かまいませんか?」
黙っているヴァルガーヴに変わってフィリアが礼を述べる。
「かまいませんよ……なんならうちの者を手伝いに行かせましょうか?」
「いえ、結構です。そんなに大した荷物じゃありませんから。ね?ヴァルガーヴ」
唐突に相槌を求められて、ヴァルガーヴは一瞬反応が遅れる。
「あっ? あぁ……って、オレも行くのか?」
「当たり前でしょう。あなたの荷物もあるんですから」
「護衛が留守してもいいのかよ」
これはアベルに向けた言葉である。
「かまいません……どうせ襲撃はいつも夜ですから」
なるほど。
では、昼間怯えていないのは、そのせいか?
いや。
そうは思えなかった。たとえ夜しかこないと分かっていても命を狙われている人間がこれほど緊張感のない笑い方ができるとは思えなかった。
荷物をまとめて降りてきたとき、フィリアは宿屋の女主人と世間話に花を咲かせていた。
支払をすませるだけのことに、なんでこんなに話が弾んでいくのかヴァルガーヴには一向に理解できない女の世界である。巻き込まれてはたまらないので彼は「先に出てるぞ」と一言だけ言い置いて外で待つことにした。
そして20分後。ようやく出てきたフィリアをじと目で見やると同時に背後からでっかい声がした。
「がんばるんだよっ! お二人さん!!」
「……?」
陽気に手をふる女主人に、苦笑いしつつ手を振るフィリア。
「がんばるって、何をだ?」
「どうも、勘違いされてたみたいで」
「勘違い?」
「駆け落ちだと思われてたらしいです」
思わず前につんのめった。
「かっ……」
「私がどこかのいいとこのお嬢様で、貴方が流れ者の傭兵かなんかで、身分違いの恋に落ちたとかいう設定らしいですよ」
設定……。
自分がB級ラブロマンスのヒーローに仕立て上げられていたらしいことをその時ヴァルガーヴは初めて知った。
(人間ってのはこれだから……)
「それでランザードさんのことなんですけど」
ふいに話題が切り替わって、ヴァルガーヴは眉をひそめた。
「アベルさんのお父さんが殺されたっていうのは本当らしいです」
「昨日、言ってたことか」
「そうです。とってもいい人だったって宿屋の女主人さんも言ってました。商売の方は……あんまりうまくなかったみたいですけど。先先代……つまりアベルさんのおじいさんですけど、この人はとってもやり手な分、とっても評判は悪かったんです。でもアベルさんのお父さんは逆だったみたいで。ランザード家は一時はこの街一、二のお金持ちだったそうですけど、今では……」
「落ち目なわけか」
こっくりとフィリアはうなづいた。
なるほどさっきの女主人との世間話は、彼女なりの情報収集だったらしい。
「先代はなんで殺されたんだ?」
「それが……よく分からないみたいで」
「分からない?」
「ええ。商用でこの街を出てた時に殺されたとか。アベルさんも一緒してたみたいですけど」
「護衛役は?」
「それなんですけど……」
フィリアがそこで初めて困ったような笑顔を見せた。
「その時の護衛って誰だと思います?」
「??」
「リナさんたち」
「なに?」
「だから、リナさんたちが護衛だったそうなんです。あとあの生ゴミも一緒にいたらしいんですけど」
フィリアが口に出すのも嫌そうに最後の一言を付け足した。
「リナ・インバースに、ゼロスまでついていて、殺された?」
苦笑いするフィリアに対し、ヴァルガーヴは深刻だった。
ゼロスを戦力に数えることはすまい。あの魔族が人間ごときを護衛することはないだろう。と同時に人間一人の命をつけ狙うようなこともしないはずだ。
それでもリナ・インバースは人間ながらそのゼロスとタメをはれるかもしれない魔力を有している。それが護りきれなかった相手というのは……。
「同じ相手なのか?」
「え?」
「殺そうとしているヤツだよ」
「さぁ……でもアベルさんが狙われているってことは街中の誰もが知ってるみたいですね。護衛役が9人も殺されたっていうので、噂の種らしいです。親子二代でつけ狙われるなんて気の毒だって、女主人さんも言ってました」
「…………」
「プロの暗殺者だっていうことは確からしいんですけど、雇った人間が誰かってことについては謎のまんまだそうです」
「プロ……ねぇ……」
あの、リナ・インバースを出し抜ける、暗殺者。
「ズーマっていうんですって」
「なに?」
「その暗殺者」
「正体わかってんのか!? だって今殺そうとしてるヤツは分からないって……!」
「雇った人間は分かってないって意味です……だって暗殺者の名前だけ分かってもしょうがないでしょう?」
「そりゃ、そうだけどよ……」
ズーマ。
暗殺者ズーマ。
もう一度心の中で反芻した時、ヴァルガーヴはその名前になにかのひっかかりを感じて眉をひそめた。
ズーマ。
確かにどこかで。
暗殺者ズーマ。
その名前には覚えがある……。
襲撃は、その夜だった。
第5章 彼の変化は何を意味するのか
火の手があがり、叫喚が聞こえる。
寝入りばなを大げさな気配に起こされて、ヴァルガーヴは不機嫌に、だがゆっくりと靴の紐を結んだ。
どうせ陽動だ。
本気で相手にするのも馬鹿らしい。
邸内に侵入者がないのは確認済みだ。昨日張った魔術の『眼』による探知システムは正しく機能していた。
窓を開け、軽く跳躍する。
爆音がしたのは東側の倉庫の方で、こんな時間に人がいるところではない。聞こえた叫び声はいずれも男のものばかり。こんな時に真っ先に上がるのはたいてい女の叫声で、第一発見者が男である可能性を考えても、未だに女の金切り声は聞こえてこない。したがってあれは陽動である可能性が大だ。
爆発自体も大したことはない---火薬の量も威力も大したことはない。
ジラスの作る爆弾に比べれば玩具も同然だ。
魔術の発達した『こちら側』では人を殺せるほど殺傷力のある爆発物は簡単には手に入らないし、手に入れる必要もないのだから。
それにしても素人くさい。
プロの暗殺者じゃなかったのか?
庭に隠れた(つもりでいる)幾人かの人の気配をヴァルガーヴは鼻で笑った。
誰が最初に出てくるか。
ことさらに挑発しながらヴァルガーヴは戦いやすい場所を選定し、移動した。
気配も一緒についてくる--なんと安易な。
背後からくるのはわかりきったことだったし、タイミングも予測していた。
小さく息を吐くと剣を腰から引き抜いて、振り下ろされた短剣を刀身で受けた。
カン、という乾いた音ともに相手の短剣が地に落ち、ついでにはずみで相手も地面に衝突する。
低く笑った時、金切り声が襲撃者の背後から聞こえた。
「ヴァルガーヴ!!!」
フィリアだ。そういえばここはフィリアの部屋の真下だった。
「バカ! 引っ込んでろ!!」
叫んだが、遅かった。
銀の刀身が閃き、フィリアに襲いかかる。
緑の光弾がそれをはじき返した。
右腕を押さえて襲撃者がこちらを振り返る。
とすん、とフィリアが腰を抜かした。
「人間ふぜいが……っ……!」
ヴァルガーヴは瞬間的に暴発した。
見えない何かをかき抱くような動作から、その手を解放した時には先の光弾よりわずかに大きい光の球が発生している。
密集する敵に向かって飛んだエメラルドの光球が熱と光をともなって弾けた時にはすでに立っている敵の数は半分に減っていた。
「!!」
襲撃者達の間に衝撃が走る。
それはそうだろう。魔術には大抵それにともなう動作や呪文が必要だ。ヴァルガーヴは呪文の詠唱なしで魔術以外ではありえない攻撃を行ったのだから。
「ヴァルガーヴ! ダメ!!」
腰をぬかしたままフィリアが叫んだ。
正体を怪しまれることは得策ではない。それに彼と人間とでは力の開きがありすぎて、下手をしなくても死人が出る。彼女なりの注意のつもりであった。
フィリアの一言でヴァルガーヴは我に返った。
魔術による攻撃を諦め、もう一度剣をかまえなおす。
半分に減った敵は自然、密集しつつあった。館の壁を背にしたヴァルガーヴを包囲する形をとる。
烏合の衆だが数が多い分、やっかいだ。
さっきの攻撃で余計な警戒心を抱かせてしまったのでなかなか次の攻撃がこない。かわりにじりじりと次第に包囲陣がせばめられていく。
(これ以上密集されたら数で押しつぶされるな--)
焦ってはいない--焦らされているような気がするだけだ。それが不快だった。
(人間ふぜいに---)
この感情は前にも感じた。
そして変化が起こった。
はじまりは、やけに大きく脈打った心臓の音だった。
(……?!)
ひゅうっ--と息を吸う音も聞こえた。
それが自分がしていることだという意識が彼にはなかった。
(……???)
今までと違うリズムでの呼吸を、身体が勝手にはじめたようだった。
その後起こった事--というより自分がしてしまった事についてはあまり意識がない。
がきんっ!!!
骨の折れる音が鈍く聞こえた。次の瞬間には目の前の若い男が足を抱えて絶叫していた。
(…………なんだ……?……)
思わず虚を突かれて、彼は無意識のうちに相手を蹴りつけた自分の足を見、ついでゆっくりと辺りを見渡した。
突然の、無謀ともいえるタイミングでしかけられた攻撃に、襲撃者達は全く反応できずにいる。
包囲の一辺をついたのだから、当然次は左右からの攻撃ということになる。
慌てたように振り下ろされる鎌と剣とを、ヴァルガーヴは飛び退いてよけようとした。--が、操られるように、身体は勝手な動きを始めていた。頭一個分だけ退いて、踏みとどまる。鼻先を掠めて剣と鎌とが空をきり、衝突した。目測を誤った攻撃者が体勢を立て直す余裕を、ヴァルガーヴは与えなかった。半歩踏み込んで鎌の持ち主の胸板に拳をたたき込む。相手が倒れるのを確認すらせず、反動を利用して、反対側の剣の持ち主の首に裏拳を決めた。
かかとが地面を蹴ってから、この動作までに実は10秒とかかっていない。傍目には何が何だか分かっていないだろう。
事実、フィリアはきょとん、としたようにこちらを見ている。
自身の掌をもう一度、ヴァルガーヴは見つめた。
(……なんだ……?)
襲撃者達は明らかに怯えている。
そして次の攻撃をしかけてこないヴァルガーヴを訝しげに見てもいた。
ふいにヴァルガーヴが大きく踏み込んだ。手近にいた相手の懐に飛び込むが如く--そして同時に、相手の腹に肘をたたき込む。力など入れていない。流れるような動作だった。
とさ……と草むらに音をたてて、男の身体が沈み込んだ。
しん、と周囲が静まり返っている。
(どういう……ことだ……?)
身体に異常は感じられない--以前の発作とは違う。むしろ、もっと--。
動悸まで聞こえるような心臓の音はもう、元の静かな状態に戻っている。
--心拍数が上がっていない。これだけ動いたのに。異常といえばそれが異常だ。
怒りも納まっていた。頭の奧にとても冷静な自分がいて、感覚もひどくシャープになっていた。今ならどんな音も、どんな気配も見逃さない確信があった。
(……以前より……強くなってないか? オレ……)
そんなばかな。
特に修練したわけでも、実戦で経験を積んだわけでもないはずだ。
ふいに笑い出したくなったが、声は出てこなかった。
頭を上げた時、彼以上に動揺している男達の姿が映った。軽く息を吐き、緩慢な動作で頭を掻く。
残りの十数人を片づけるのには5分とかからなかった。
「ヴァルガーヴ……」
フィリアが躊躇いがちに声をかけた時、ヴァルガーヴはやや呆然としているように--見えた。こちらの声も耳に入っていないらしいので、フィリアはもう一度呼びかけてみた。
「ヴァルガーヴ」
今度は反応があった。
ゆっくりと顔を上げ、我に返ってなんでもないような顔をする。
「……どうかしたんですか?」
「いや……なんでもねぇよ」
嘘つき。
フィリアは溜息をついて周囲を見渡す。
苦悶と涙まじりのうめき声。全員どうにか生きてはいるものの、一人として起きあがろうとする者はいない。
「ちょっと……やりすぎですよ? 手加減してあげないと……」
「したさ」
即答されてフィリアはヴァルガーヴを見返す。
嘘ではないようだが、それならこの惨状はどうなる?
それに戦い方もどこかおかしかったし。
これまで盗賊団だの追い剥ぎだのとやりあってきた時だってこれほどではなかった。今回襲ってきた人間達だって彼らと同レベル程度の相手だ。それなのに--この余裕のなさはなんだろう?
「ヴァルガーヴ……もしかしてどこか具合、悪いんじゃ……」
ふと悪い予感がして青ざめる。以前悩まされていたあの、発作。竜の血と魔族の血が反発しあって起こっていた---。
「いや……大丈夫だ。悪いところはどこもねぇよ」
安心させるように笑ってみせてくれても今ひとつ信用できない。
なにせやせ我慢がうまい人なのだから--。
フィリアは心配そうな表情のまま、ヴァルガーヴを観察する。
大丈夫という言葉に嘘はなさそうだったが、それ以上になにかに動揺しているようだった。でも、一体何に?
声もなく立ち尽くす二人。
館の警備隊はまだ来ない。消火活動に追われているらしい。
「ズーマとやらが来てないな」
ふいにヴァルガーヴが思い出したように言った。
「え? えぇ、そうみたいですね」
「妙だな……陽動まで用意しておいて……」
こちらの襲撃も囮かと思ったが、『眼』にはまだひっかかっていない。気配もしない。
どちらにせよ陽動から時間がたちすぎているから今さらやってくるとは思えなかった。
「……戻りましょう。アベルさんの方も確認しておいた方がいいでしょうし」
「そうだな」
釈然としないものを抱えたまま、二人は歩き出した。
「ええ、僕の方は全然大丈夫です」
あっけらかんとアベルは言い、ついで襲撃者達のことを聞いても笑みを崩すことはなかった。
「大変でしたね」の一言があっただけだ。
警備隊といっしょに消火活動にあたっていたのだという。
右往左往していて、侵入者達に気づきもしなかったというからあきれたものだ。
「全員、まとめてひっくくって裏に転がしてあるから尋問でもなんでもするんだな」
「ええ。ありがとうございます」
どうにも緊張感の欠けた標的と話をしていると肩が重くなる。ふいに疲労感--徒労感といった方が正しいか?--を覚えてヴァルガーヴは早々に部屋に戻った。
ベッドのへりに腰を下ろすと、フィリアがまだ心配そうに立っているのに気がついた。
「自分の部屋に戻れよ」
それだけ言って上着を脱ぐ。
半裸のヴァルガーヴにかまいもせず、フィリアは隣に腰を下ろした。
心配そうな眼差しで、腕に手をかけてくる。
「本当に、大丈夫なんですか?」
「ああ」
「でも、なんだか……とっても疲れているみたいです」
「疲れてる?」
「そうでなければ、心配事があるとか」
「……いや」
返事は短くて、しかも間があった。
何か隠してる。
直感でフィリアは悟ったが、頑なな横顔は、理由を話してくれそうもなかった。
裏庭の方で話し声が聞こえる。
警備隊が襲撃者達を連行しているらしい。
乱暴なやりとりも今の彼には障るような気がして、フィリアはカーテンを閉め、外の声を遮断した。
布団をひっかぶって無理矢理眠りに落ちようとしている彼の額に手を当てて、フィリアは悟られないようにこっそり神聖呪文をかける。せめて眠りの中では安らかであるように。
「ゆっくり休んで下さいね……そのための時間なんですから」
悩んだり、苦しんだり、苦しめられたり。そういうのはもう終わりにしてあげたかった。
未だに解消されてはいないのだろうか。滅んだ一族の呪いと、滅んだ魔族の意志と、神と魔の思惑と。背負い込むのが得意な誰かさんはやせ我慢まで上手だから、つい、もう大丈夫と錯覚してしまいそうになるのだ。
思いっきり抱きしめてしまいたくなって、フィリアは泣き出したくなった。
自分の生が。
罪の上にあると思い知るのはこんな時である。
フィリアが心底安心したことに。
その夜それ以上の襲撃はなかった。
第6章 いまはもういない主のために
何のために戦うのかと問われれば、彼は迷わず主のためと答えただろう。
存在を否定されることから始まった彼の生を、初めて肯定へと導いたのが主なら、生きることは戦いだと教えたのも主だった。
生きるために戦ったのだ。戦うために生きたわけではない。目的と手段をぎりぎりまで等価に近づけながら、それでも逆転することは決してなかった。
何のために生きるのかと問われたならば、彼は迷わず主のためと答えただろう--今はもういない、主のために。
陽動だけで終わった襲撃だったが、翌日には街中がその噂で持ちきりだった。
市場に出て簡単な身の回りの品を買い揃えながら、彼はそれとなくささやかな情報収集をしてみた。
おおむねアベル・ランザードに対する評価は悪くない。街の多くの者が気の毒がっている。父親が同じ相手に殺されているというのもその理由の一つらしい。
殺された護衛役たちはいずれも流れ者ばかりということであまり関心は払われていなかった。自分が殺されても(万が一にもそんなことはありえないという自信はあったが)多分ろくな同情はしてもらえないだろうなとヴァルガーヴは皮肉っぽく考えた。
(--あのお嬢さんをのぞけば、かな)
なりゆきで一緒にいることになってしまったが、いつかは別の道をとることになるだろう--お互い帰る場所をなくして、同じ道行きを辿っているだけだ。行き着く場所まで同じとは限らない。
(別に気にするようなことじゃねぇよな)
自分に言い聞かせるように心中で呟いた。
「ズーマとやらいうヤツの手掛かりは一切ナシなのかい? 9人も殺されたのに?」
フィリアへの土産がわりに買った白桃を受け取りながら、八百屋のおかみに声をかけると、首をひねるような返事が返ってきた。
「そうだねぇ……もう半年にもなるってぇのに、なーーんの進展もないよねぇ。全くうちの警備隊もだらしないったら」
「半年? そんなに長く?」
「ラドックさんが殺されなすってからだと……もう1年くらいにはなるかね」
妙な間隔のあき方に、ヴァルガーヴは眉をひそめる。最初にラドックが殺されたのが1年前。それから半年して、アベルの最初の護衛が殺された。同じ相手に。同じ依頼者に? こんなふうに分けるくらいなら、どうして最初から2人同時に始末しないのか。なぜ半年後?
アベル・ランザードに裏があることははなから承知だったが、1年も命を狙われていながら依頼主の正体を確かめることすらしないのは不自然だった。
街の者は誰も気付いていないらしい。人柄の良さがカムフラージュになっているのだ。
夕暮れの街を歩きながら、ヴァルガーヴは集めた情報からなんらかの結論を導き出そうとして諦めた。
(こーいうのはニガテなんだよな……)
目的に対して回り道をとるやり方は彼の性に合わなかったし、そういった思考の在り方もやはり理解できない。こういうのはゼロスあたりが好きそうだ。
ふいに主の事が思い出された。
(あの人ならどうしたかな……)
単純明快ではあったが、短絡的ではなかった。あの人ならどうすればいいか教えてくれただろう。理解できなくとも、打破できる。考えるのは後にしろ。動け。
----動け。
天の声と言うべきか?
彼が飛びすさった一瞬後、黒いナイフが地面に突き刺さっていた。
柄も黒なら、刀身まで黒。いかなる光も反射しないように作られている。
闇に紛れる暗殺者の為の剣だった。
(ようやくおいでなすったというわけか……)
二撃目を気配で探りながら、ヴァルガーヴは正面の闇を睨み付けた。
いつのまにか人気のない場所にきている。考え事をしていてつい知らない路地に入り込んだようだ。
姿勢を正し、ゆっくりと精神を高揚させる。自分で自分の士気を高めると魔力のポテンシャルも上がるのだ。魔族というのは単純でいい。
「やぁっと闘う気になったのか?」
挑発にのる気配はなかったが、ヴァルガーヴはそれでも言葉を継いだ。
「この間の陽動とは違うみたいだな」
油断なく視線を周囲に配りつつ、一歩踏み出した。
「オレはまだるっこしいのは嫌いでな……来るんならさっさとしな……」
その時、風が流れた。
間一髪で横なぎにきた鋭い刃を避ける。
彼の水色の髪が少しそがれた。黒い影はすぐに体勢を立て直し、気配が離れた。
一度では踏み込めない距離を充分に置いて、対峙する。
「ズーマ……だな?」
答えないことは先刻承知である。
「二度目のご対面だな……だが、暗殺者としちゃまずいんじゃないか? ここまで姿を見せるってぇのは」
「…………目撃者なら消せばいい」
くぐもった声がマスクの下から漏れる。
目だけが爛々と闇の中に浮かび上がる。どこか無機質なその瞳にヴァルガーヴは違和感を覚えた。
「……なるほど。それでオレを狙いにきたわけか」
「そうだ。だがそれだけではない」
言い終える前に、黒い闇が視界を覆った。
(黒霧炎(ダーク・ミスト)か!)
気配を完璧に絶ったズーマの拳が胸元に飛び込んでくる。
だが、巧妙な三撃目も彼はかわした。
かわせるとは思っていなかったのだが。
(やっぱり……)
自分の反応が以前より速くなっていることをヴァルガーヴは自覚した。
急激に訪れた身体の変化。原因は何だ?
一瞬だけ戦いから気を逸らしたのがまずかった。
左腕に鋭い痛みが走る。
(しまった……!)
執拗に、巧妙に、鋭い刃が彼の首筋めがけて繰り出される。
流れるような一連の動きを、だがヴァルガーヴは完璧に見切った。
ふりむきながら、かわし、かわしながら掌にためた魔力を解放する。
意識してセーブしたため、殺傷力にはかけるが、はじき飛ばすには充分だった。
ズーマの身体はまっすぐに飛び、壁に激突する。
がらがらと音を立てて、煉瓦積みの壁は崩れ、そらにその後ろの倉庫らしきものの壁もぶち抜いて、ズーマの身体はその奧に消えた。
その威力に驚いたのはヴァルガーヴ自身の方だった。
彼としてはズーマが体勢を崩すことを狙って、次の攻撃に移るつもりだったのだが……。
完全にセーブしきれなかった己の魔力にとまどいつつ、彼は崩れた壁の奧に目を凝らす。
気配は消えていた。
ついで辺りを覆っていた闇が少し薄らいだ。
月明かりが戻ってくる。
空を見上げて溜息を一つ。
くるりと身体を返して元きた道を引き返しかけたその時。
「いやあ……なんか前より強くなってるみたいですねぇ。ヴァルガーヴさん」
背後からできれば一生聞きたくなかった声が聞こえてきた。
見事な満月を背後に、足を組んで杖を手にした黒づくめのおかっぱ頭が一人。
獣神官ゼロスだった。
「…………………」
しらけた風が彼らの間を流れていった。
非常識にもふわふわと月夜に浮かれ飛んでいる男は彼の反応を待っているようだ。くるりときびすを返し、ヴァルガーヴはまっすぐ歩き出した。
「ちょっ、無視しないでくださいよぅ。ぼく、寂しいじゃないですかぁ」
どこで覚えたやら妙な言葉遣いで生ゴミがしゃべっている。
「オレの知り合いに空を飛ぶ生ゴミは存在しない。存在しないものは幻だ」
彼は足を止めずにきっぱりと言い捨てた。
「あーーーっ、そぉーーんなこと言っていいんですかぁーーー? せぇぇーーーっかく人が親切に教えてあげようっていうのにぃぃぃ」
「生ゴミに教わるようなことは何もない」
「ぼくは生ゴミじゃありませんっ!! その証拠にほらっ。火をつけても燃えないんですよぅ!」
妙な主張で、自分で自分を燃やすという奇矯な芸当をやってのけたゼロスに、ヴァルガーヴはうんざりしたように振り返った。
「わかった、わかった。わかったから火を止めろ。熱い」
「そう言えば、アナタ元々北国出身でしたっけ。暑いのダメなんですか?」
あついの字が違うわ、バカタレ。そう言いたかったが、彼はぐっと堪えた。この男のペースにうかうかとはまるととんでもないことになる。
「北国っていうな、キタキツネじゃあるまいし。なんか用があるんなら聞いてやるだけは聞いてやるからさっさと帰れ」
「いや別に用があるってわけじゃないんですが」
「あばよ」
くるりときびすを返すと、慌てたように呼び止められる。本当は慌ててなどいないくせに、と内心思いながら、ヴァルガーヴは振り返った。このへんで既に相手のペースにはまっているのかもしれない。
「なんなんだよ、てめーは」
「いえね、ちょっと用があってこの街に来てみたら見覚えのある人たちが揃っているじゃないですか。これはちょっと挨拶くらいしとかないと浮き世の義理ってもんが……」
純粋魔族のくせに義理、なんて言葉を使ってよく平気だなとヴァルガーヴはあきれたようにゼロスを見返す。
「別に義理も人情もねぇだろうがよ、オレ達にとっちゃ」
「まぁそれは言葉のアヤってやつで。お元気そうで何よりです。ヴァルガーヴさん。ところでズーマさんとはどういうご関係なんですか?」
前振りを長くしておいてさらりと核心に迫る話し方はどうやらこの魔族のくせであるらしい。
「別に。命を狙われてる男の護衛をやってて、命を狙われてるだけだよ」
「はぁあ。分かりにくくってシンプルなご関係なんですね」
「そういや、お前ズーマと以前にあったことあるはずだな」
以前リナ・インバースが自分と同じ護衛役になった件で、この魔族も絡んでいたはずだ。
「はぁ、まあ」
「どんなヤツなんだ、ありゃ」
おとなしく質問に答えるようなタマでないことはよく分かっていたので、あっさりした答えが返ってきたときには、ヴァルガーヴはいささか拍子抜けした。
「故人です」
「あ?」
「だから、僕の記憶によればズーマと名乗っていた人間は死んでいるはずなんですが。リナさんとの戦いのときに」
意外な言葉にヴァルガーヴは目を見張る。
「詳しく話せ」
「いいでしょう。ただし交換条件」
「交換?」
「僕の仕事を手伝って下さるならね」
「仕事?」
ヴァルガーヴは目を見張って、一歩後ずさった。
一瞬後、驚愕に満ちた響きが静かな夜を破って響きわたる。
「お前に仕事なんかあったのか!?」
夜空に浮かんだ獣神官の身体が、かくん、と月の中からずり落ちた。
「いっ、やああぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!」
静かでのどかな朝だった。
いきなりあがった悲鳴にすずめたちが飛び去り、館の使用人達は何事かと目を合わせる。
「……いやぁ、お久しぶりですね……フィリアさん……」
「いやっ、生ゴミがっ、生ゴミがしゃべってるわぁぁぁぁ!!」
両方の頬に手を当てて、フィリアは大げさに身を捩る。
ゼロスの笑顔がひくついているのも、フィリアがいやいやと身を捩るのも強引に無視してヴァルガーヴは濃いめの紅茶を喉に流し込んだ。
「……あいかわらずで、なによりです……ところで僕は一応ヴァルガーヴさんのお客人なんですがね……って聞いてませんね、アナタ」
「いやっいやっ誰かっ殺虫剤持ってきてくださいっ殺虫剤っ!」
「……そのへんにしとけ、フィリア」
ゼロスの額に青筋が浮かんでいるのを見て、ヴァルガーヴがようやく止めに入った。
「だってヴァルガーヴ……!」
鋭い視線にフィリアは反論を封じられてしまった。
不服そうにしぶしぶと、ようやく隣の椅子に腰を下ろす。
「……そろそろ始めてかまいませんか?」
それまで存在を無視されていたアベルがようやく朝食の開始を促した。
朝食が終わった後、ゼロスはあっさりと姿を消した。
フィリアはまたあの生ゴミがとぶつぶつ言っていたが、ヴァルガーヴは気にしなかった。いてもフィリアと子供じみた喧嘩をするだけだし、そのくらいならそのへんのアストラルサイドにでも引っ込んでいてくれた方がよほどいい。
どのみちあの男も今回のことに限っては情報といえるほどの情報は握っていないようで、それなら勝手に調べ回っていてくれた方が彼としても助かった。
(モチはモチ屋っていうしな)
ゼロスならこういうぐちゃぐちゃしたことを考えるのは得意だろうし、策謀陰謀の類に関する鼻も利く。
ゼロスの仕事とは、即ち魔竜王配下の残党狩りであった。
残党といってももはや魔族としての自我は残っていないだろうとゼロスは言った。もし残っているならば離反などするはずがないのだと。
元が竜族のヴァルガーヴと違い、純粋魔族である彼らは彼らを生み出した魔竜王ガーヴよりもさらに強い呪縛によって支配されている。即ちロード・オブ・ナイトメアという偉大なる「母」に。ガーヴがいなくなれば他の者の配下に入るだけのことだ。
魔竜王が滅んだことを告げに来たラルタークもそうだった。
彼はその時、ラルタークから竜神官の地位を貰い受けたのだ。
もはや有名無実化したとしても、その称号だけでも残したかった。魔竜王が存在した証しになるのなら。
『我らは従わなければならない---そのように作られているのだ』
ラルタークはそう言っていた。「魔族」という存在であるゆえに。彼らを生み出した魔竜王ではなく、そのヒエラルキーの頂点にいる「母」に。
その時初めて、ヴァルガーヴは魔族という存在に憐れみを感じた。
彼らは個体であると同時に「魔族」という「一つ」の存在なのだ。
彼らに個体としての意志はない。偉大なる母の元に還る、それだけが「魔族」の望み。魔族は夢を見ない。少なくとも「自分」の夢は見ない。
多分、彼らの中で、魔竜王だけが異端だった。何十、何百の部下がいても、所詮はみな「魔族」だった。
彼と同じ夢を見ることができたのは、自分だけではなかったか。
彼と違う夢を見ることができるのも、自分だけではなかったか。
「……だから、オレはあの人の意志を継いだんだ…………」
初めて見つけた答えのように、ヴァルガーヴは呆然とつぶやいていた。
立ち止まった彼に気付かず、少し先に進んでしまったフィリアが振り返った。
「え? ……なにか言いました?」
「いや……なんでもない」
返しながら、彼はやりきれないように笑っていた。
「ヴァルガーヴ?……」
「なんでもないんだ」
強い口調で言って首を振る。
うっかり過去の古傷を掘り起こしそうになるのを避けたくて、ヴァルガーヴは違う話題を口にした。
「あのズーマって男のことだがな……」
書棚にずらりと並ぶ本から何冊か興味のわきそうな物を物色していたフィリアが振り返った。
護衛役など襲撃がない限りヒマなので、いきおい時間を潰す場所が必要になる。幸いランザード邸には個人にしては大したコレクションの図書室があったので、彼らは用がない時はこの図書室を居場所にすることに決めていた。
「昨日、会った」
できるだけさりげなく口にしたつもりだったが、フィリアの目と口はまんまるに開かれた。
「どこで?! いつですか?! どうしてそんな大事なこと黙ってるんですか!」
「市から帰ってくる途中だよ……別に大したことじゃないだろ」
「何言ってるんです!! ケガでもしたら大変じゃないですか!!」
真剣に心配しているだけに、どこかズレた彼女の返答はヴァルガーヴを苦笑させた。やはり腕の傷を治しておいて正解だった。
「だから、無事に帰ってきてるだろ」
「それはそうですけど、でも……」
「ゼロスに聞いた話じゃ、ズーマってやつはもうとうに死んでるんだそうだ」
強引に話を元に戻したが、フィリアは逆に青ざめた。
「じゃあ……」
「どうも何か裏がありそう……」
「あなた、幽霊と喧嘩したんですか!?」
言いかけて遮られた悲鳴のような叫びはやっぱりどこかズレていた。
「……いや別に幽霊じゃない。ちゃんと足もあった」
「じゃあ、ゾンビ!?」
「……ゾンビでもネクロフィリアでもない。オレが闘った相手はちゃんと生きてる人間だ」
厳密にいえば「人間」でもないのだが、なんとなくそれは言わない方がいいような気がした。
「じゃあ、じゃあ……どういうことなんです?」
こくん、と首を傾げたフィリアの仕草は小動物を思わせた。
根が正直にできているからこういう時、死んだフリをしていた、とか別人がなりすましている、とかいう発想は出てこないらしい。まして生き返ったなどと自然の摂理に反するようなことは想像の外だ。……ゾンビが自然の摂理にかなっているかどうかはともかくとしてだが。
「さあな。ただゼロスの野郎の『仕事』とやらもそれにかんでるらしい」
「あの生ゴミが!?」
「そんなわけだからしばらく我慢してくれ。あれはあれで役には立つ」
フィリアの顔がふいに曇った。
「……そうですね。生ゴミだってリサイクルすれば役には立ちますものね……ええどうせ私は役立たずですよ、生ゴミ以下ですよ、どーせ、どーせ……」
なんだかわからないが拗ねてしまったようだ。
「何言ってんだ、あんた」
「どーせ、あなたには私なんて必要ないんでしょうよ、ええ、何でも一人で決めちゃって、何でも一人でやっちゃって、私なんて、私なんて……」
「あのなぁ……別に役に立つとか立たないとかじゃなくてな」
「やっぱり役立たずなんですね、そーなんだ、私なんて世間知らずで箱入りでお金だって稼げないし料理だってできないし……」
さり気に床にのの字なんか書き始める。
どうしたらよいものやらヴァルガーヴは途方に暮れた。
「拗ねるなよ……頼むから」
「じゃあ、言って下さい。何を悩んでるんですか」
振り返った彼女の瞳はいっそすがりつくかのように真剣だった。
「別に悩んでなんかいない」
「うそ」
「うそじゃねぇよ。なんでそんなふうに思うんだ?」
「だって最近一人でどっかいっちゃうことが多いし」
「オレと一緒にいると危険が多いからだよ。この間も下手に出てきてケガするところだっだろうが」
「帰ってくるのも夜遅いし。帰ってきてもお酒臭いし」
「情報収集には盛り場が手っ取り早いんだよ」
「ごはんだって、おかわりしないし」
「襲撃に備えて摂生してるだけだ」
「家にいるときもあんまりお話とかしてくれないじゃないですか」
「お話ってあのな……」
「私のことやっぱりまだ憎いですか?」
いきなり極論に走ってしまったフィリアにヴァルガーヴはまともに返答するべきかどうか迷った。
できれば聞かないでほしかったと彼は思う。
憎悪も悲嘆も郷愁も無念も何もかもいっぺんに昇華されてしまったあの瞬間を生き延びて、現実に引き戻された時には全てが曖昧になってしまっていた。
あれより以前の記憶を辿る度、無色透明な海を漂っているような気分に襲われる。果てなく、頼りなく、あてもなく、寄る辺ない、寂寥感。
それでも例えば---まるで波に光が閃く瞬間のように、かつての感情の残滓を見つけることもある。さきほどのように。
「わからねぇよ。昔は憎んでたし、今だってそうするべきだと思ってるさ。けど……よくわからねぇ。オレに聞くな。オレだってわからねぇんだ」
「ヴァルガーヴ……」
泣きそうな顔をしているのは分かっていたが、敢えて無視した。
「オレが悩んでるように見えるのはあんたが心配しているような理由でじゃない。……そうだな、話しといた方がいいか。じつは最近体調がおかしい」
その一言でフィリアの表情がまたしても変わった。
とりあえず昔のことは棚に上がったようなので、ヴァルガーヴは気をそらすためにさらに言葉を継いだ。
「どうも身体がふわふわするような感じなんだ。いや別に気分が悪いとか痛むとかいうのじゃないんだがな。妙に身体が軽くて、以前よりよく動けるし。自分の身体が自分の思う以上に反応するというか……」
書棚から取り出した『家庭の医学』なんぞをあせあせとめくりはじめるフィリア。
「魔力も以前より増してるような気がするしな。傷の治りも速いし……」
『症状別索引』と書かれた頁を一生懸命にめくっている彼女の姿を見るうちにヴァルガーヴはふと悪戯心を起こした。
「あと骨格なんかも以前より大きくなった感じだ。窓辺に立つと誰かが呼んでいる声が聞こえてきたり。夜中に月に向かって遠吠えなんかもしたりしたくなって、そうそう昨日起きてみたら背中の羽が5枚に増えてたっけ。明日辺り、尻尾も生えそうなかんじなんだ」
「幻聴……狼憑き……羽……羽……しっぽ…………?」
分厚い医学書を抱えた後ろ姿からフィリア自身の尻尾が見え隠れしはじめた。
ピンクのリボンが左右に揺れる。
「……………………ヴァルガぁーーーヴ!!!!」
彼女がフレアブレスを吐かなかったのは、奇跡といっていい。
第7章 変わりゆくもの、変わらないもの
「ひっ人が心配してるのにっ……あなたってひとはぁぁぁっ!!」
けれど彼女の激昂ぶりは彼を面白がらせるだけだった。
(マジにムキになるからおもしろいよな)
「ホントですねぇ」
いきなり耳元で囁かれて、ヴァルガーヴはとびすさった。
「「ゼロス!!」」
思わずフィリアとはもる。
「おや。そこまで驚いていただけるとわざわざアストラルサイドから出てきた甲斐がありますね」
「おまけに人の心んなかまで読みやがったな」
「油断大敵ですよ、ヴァルガーヴさん。今のあなたは無防備に過ぎます」
一瞬剣呑な笑顔が獣神官の本性を宿す。
「あなたもボクたちにとって貴重な戦力なんですから。神族とあんまり親しくなられるのも困ります」
「誰が、戦力だと?」
「あなたがですよ。今のあなたは確実にボクたち側のものになりつつあるんですから」
「なんですって?!」
その一言にフィリアが柳眉を逆立てた。
「あなたときたら……リナさんだけでは飽きたらずに、ヴァルガーヴまで毒牙にかけるつもりですかっ! 許しませんわよ、ぜっったいにっ!!」
そういいながら、ヴァルガーヴを背中にかばおうとする。華奢な身体で何ができるというわけでもないのだが。
「毒牙……?」
「ヴァルガーヴは渡しませんからね!!」
「……なんか、誤解してません? ボクはただ、ヴァルガーヴさんの身体が」
「身体が目当てですって!? なおのこと許せませんっっ。ヴァルガーヴはこれからまっとうな人生を歩むんですっ。昔の悪い仲間になんか……」
悪い仲間……。
ヴァルガーヴは一瞬眩暈を覚える。
(こいつ、やっぱりオレを更正させる気でいやがる……)
本人自身は別に善人にも悪党にもなったつもりはないのからフィリアの心配はどこかずれているとしか言いようがない。
「だれが身体が目当てですかっ!! だいたいボクはノーマルですっ! 多少お料理が趣味ってくらいでそこまで言われる筋合いはありませんよっ!!」
「趣味なのか……?……料理……」
「ええ、以前一回試作する機会があって、それ以来妙にはまっちゃいまして。食べてみます? 自信作なんです。ドラゴンのニャラニャラ鍋」
さらりと言われた言葉に、フィリアの顔が青ざめ、ふらりと意識が遠のいた。
「オレに共食いしろってぇのかよ」
「あ、そうなっちゃいますね。すみません」
全然すまなそうな顔で彼は謝った。
「でもアナタどっちかっていえば今はボクたち側に近くなりつつあるようですし」
「ボクたち側……? 魔族側ってことか?」
「そうですよ」
「随分勝手に決めつけてくれるじゃねぇか」
「決めつけてなどいませんよ」
「証拠は?」
「それはアナタ自身が分かってらっしゃるんじゃありませんか?」
絶やされない笑顔が返って不気味だった。
「…………」
「以前に比べてなんとなーーく身体が軽かったりしません? 魔力もアップしてるでしょう?」
「……だからなんだ」
「だからアナタ、精神体に近くなってきてるんですよ。というより本能が意識を凌駕してきてると申し上げたほうがより正確ですかね」
「本能……だと」
「魔族としての本能。即ち破壊と消滅への欲望。原胎回帰願望」
「オレは滅びを望んでなんかいない」
「意識体としてのアナタは、ね」
「…………」
「アナタにとってもボクたちの側にくる方が楽だと思うんですけどねぇ」
「確かにな」
「ヴァルガーヴ!」
一人会話に置き去りにされていたフィリアが悲鳴のような声を上げた。
「だがオレは根が苦労性なもんでな。たやすく手に入る人生ってやつはキライなんだよ」
「魔竜王と同じモノになれると言っても?」
「同じモノ……?」
「ボクの主に言わせますとね、今のアナタは赤眼の魔王(シャブラニグドゥ)様がお作りになられたばかりのころの魔竜王ガーヴ殿と非常に似た存在になりつつあるんだそうですよ」
「だからなんの根拠があるってんだよ」
「元々魔族というのは基本的に精神体ですからこちら側に現れる時の姿形はどうでもいいんです。獣王様にしたって、「獣」がつくから動物っぽいってわけでなし。それがどうして水竜王と心中できるほど神族と共通の要素を持つ「竜種」が出てきたのか、不思議に思いません? 現に魔竜王配下だったラーシャートさんやラルタークさんは別に竜(ドラゴン)ってわけじゃなかったでしょう?」
ゼロスは故意に彼の反論を無視して話を進めている。
彼自身にというより彼の側で震えているフィリアに聞かせているようにヴァルガーヴには思えた。
「そーいやそうだな。精神体なんだから別にわざわざ「竜」なんて名乗らせる必要はない……」
「そういうことです」
「…………じゃあ……じゃあ、どういうことなんです?」
フィリアが困惑したように彼とゼロスを見比べる。
「つまりですね。魔竜王という存在そのものが魔族の中では既に異端だったんですよ。元々「竜」なんて生き物はこの世界のどこにも存在していなかったものなんですから」
「存在していなかった……って……」
「ああ、もう説明するのめんどくさいから経緯ははしょって結論だけいいますとね。あなた方はもともとこの世界以外のところから召喚されてきたモノです。降魔大戦よりもずっとずっと前にね」
「召喚?」
「そうです。最初にあなた方を召喚したのは神族側のほうです。僕たち魔族は召喚なんて普通やりませんから。ただ呼び出されたあなた方は予想以上に強かったんで、赤眼の魔王様はちょっと自分でもやってみよっかなーーって気になられたらしいんですね。でも、ご存じの通り僕たちにとって「他力本願」っていうのはこりゃもうプライド傷つけられまくりの自尊心まるつぶれの自虐行為ですから。それだけで結構精神的にダメージきついです。だから……」
「最初から捨て石にするつもりで呼び出した」
氷点下の声でヴァルガーヴが続ける。
「召喚した上で記憶をいじくって魔族としての力や属性を植え付けてね」
ゼロスは平然と応じた。
くすくすと笑うその姿に、フィリアは吐き気すら覚える深刻な嫌悪を感じる。
「なぜ今さらそんなことを話す」
ヴァルガーヴの声はあくまで平静に聞こえるが、実際は激昂寸前だ。
「だから、ぼくらの側に来た方が楽だっていうんですよ」
「ふざけてんのか、てめぇ」
「ふざけてやしませんよ。いっときますけど、ボクは罪の意識なんかありませんよ。魔族だからっていうわけじゃないです。だって僕らは基本的にみーーんな一緒なんですから。ガーヴさん一人が捨て石になってるわけじゃないですしね」
だから悲しんでいるとかくやしいとか。
そんな感情はありはしないのだ。
それこそ魔族なんだから。
「アナタは魔竜王ガーヴから「魔族としての力」を受け継いだただ一人の「竜族」です。ただ竜族って純血種なだけに異なる血を体に受け入れるのにかなりの時間がかかるわけで。今までアンバランスだった力がやっとアナタの中で安定してきたんですよ。それがここんとこのパワーアップの原因」
「なるほどな」
「だからアナタは今までよりボクたちの側に近くなっているんです。このままいけば望み通り魔竜王ガーヴと同じモノになれますよ」
「望み通り……? バカかてめぇは」
「あれ、だってあなたガーヴさんのようになりたがってたでしょう?」
「……お前、やっぱりバカだな」
いや、魔族だからか。
ヴァルガーヴは嗤った。嗤うしかなかったので。
「オレは魔族になる気はない」
はっきり宣言した時、フィリアが背後で小さく溜息をついたのがわかった。
「はぁ、まぁ今は無理強いはしませんけどね。でも、協力くらいはしてくださいよ。夕べちゃんと約束したでしょ?」
「協力するって何をだ」
「前の仕事の続きなんです。残党狩り」
そういえばこいつ、最初はオレをおっかけてあの大陸まで来たんだっけ。
それも随分昔のことのような気がするが。それにしても獣王も気の長いことだ。
「……といっても一人だけですけど」
「誰なんだ」
「ご存じですか? 無貌のセイグラム」
「知らね」
「あらら」
ゼロスはまともにずっこけた。
「知らないって……あなた魔竜王ガーヴの配下でしょう?」
「ガーヴ様の部下だったやつでオレが直接知ってんのは3、4人くらいなんだよ。オレはもっぱら向こうの大陸でしか動いてないからな。こっちで動いてたヤツのことはよく知らねぇ」
「はぁ……そうですか。それなら仕方ないですけど……」
「どんなヤツか知らねぇが、お前ならわざわざオレの手を借りるまでもないだろ。オレは忙しいんだよ、帰った帰った」
しっしっと露骨に手をふるヴァルガーヴの背後でフィリアがにこやかに扉を開ける。お帰りはこちらといわんばかりの笑顔にゼロスの頭に一つ青筋が浮いた。
「わかりましたよ……でもセイグラムさんはあなたと接触する可能性の方が高いんです。今のあなたは先ほど申し上げたとおりガーヴさんに近い存在ですし。だから近づいてきたら必ず教えてくださいよ」
「…………………………………………………考えとく」
かなりイヤそうにヴァルガーヴは言ったが、ゼロスは意に介することなく姿を消した。断ったところでどうせどこからか見張っているにきまっていた。
「あ、それと」
さらりとした口調で天井から声だけが振ってきた。
「セイグラムはズーマさんと同一人物ですから、そこんとこよろしく」
「なに!?」
「以前とりついて、そのまんま死んだ筈なんです。それじゃ」
詳しい前後の説明をいっさい省いてゼロスは一方的に回線を切った。
「ヴァルガーヴ……」
溜息をついて頭を掻くヴァルガーヴにフィリアの躊躇いがちな声がかかる。
「いっちゃったり、しませんよね?」
「あ?」
「魔族なんかになったりしませんよね?」
今でも半分魔族だが、という言葉は呑み込んだ。
泣き出しそうな表情と視線がひたと彼に注がれている。
「…………」
『今のアナタはガーヴさんと同じモノになりつつあるんですよ。』
同じ、魔族に。
その一言がフィリアを怯えさせているのだろう。
彼は嗤った。
「ああ」
短く言われた一言にフィリアはやっと笑顔を見せる。
『アナタの望みだったでしょう?』
どこからかゼロスの声が響く。
(やっぱりバカだな)
けれどとても魔族らしいと彼は思った。
→未完